殷鑑遠からずとは
殷鑑遠からず
いんかんとおからず
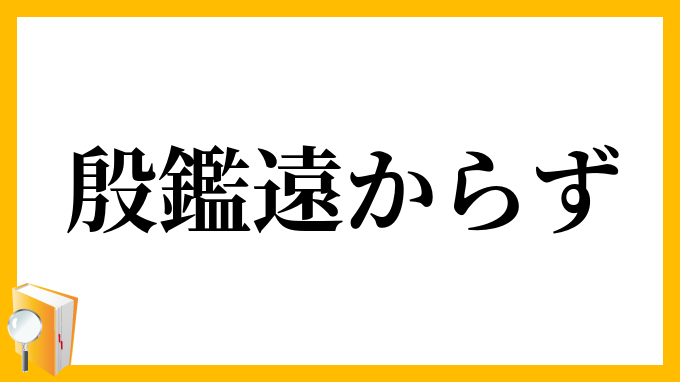
| 言葉 | 殷鑑遠からず |
|---|---|
| 読み方 | いんかんとおからず |
| 意味 | 戒めとなる失敗の例は、すぐ身近にあるというたとえ。
殷の国民が鑑(かがみ)とすべき手本は、遠い時代に求めなくても、前代の夏(か)の滅亡がよい戒めであるとの意から。 |
| 出典 | 『詩経』 |
| 使用漢字 | 殷 / 鑑 / 遠 |
「殷」を含むことわざ
- 殷鑑遠からず(いんかんとおからず)
「鑑」を含むことわざ
- 殷鑑遠からず(いんかんとおからず)
- 人を以て鑑と為す(ひとをもってかがみとなす)
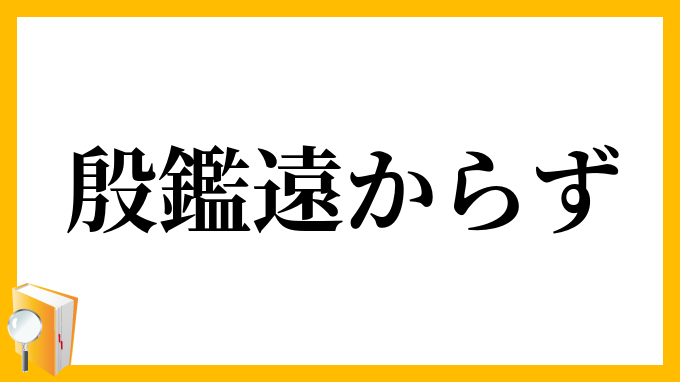
| 言葉 | 殷鑑遠からず |
|---|---|
| 読み方 | いんかんとおからず |
| 意味 | 戒めとなる失敗の例は、すぐ身近にあるというたとえ。
殷の国民が鑑(かがみ)とすべき手本は、遠い時代に求めなくても、前代の夏(か)の滅亡がよい戒めであるとの意から。 |
| 出典 | 『詩経』 |
| 使用漢字 | 殷 / 鑑 / 遠 |