大家と言えば親も同然、店子と言えば子も同然とは
大家と言えば親も同然、店子と言えば子も同然
おおやといえばおやもどうぜん、たなこといえばこもどうぜん
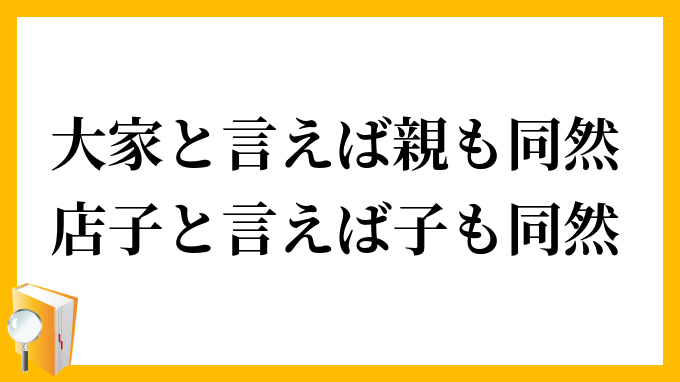
| 言葉 | 大家と言えば親も同然、店子と言えば子も同然 |
|---|---|
| 読み方 | おおやといえばおやもどうぜん、たなこといえばこもどうぜん |
| 意味 | 借家人にとって家主は親と同様の存在であり、家主にとって借家人は我が子同様の存在だということ。「店子」は、借家人の意。昔の大家と店子の関係をいった言葉。 |
| 使用語彙 | 大家 / 親 / 同然 |
| 使用漢字 | 大 / 家 / 言 / 親 / 同 / 然 / 店 / 子 |
「大」を含むことわざ
- 阿保の大食い(あほのおおぐい)
- 諍いをしいしい腹を大きくし(いさかいをしいしいはらをおおきくし)
- 一木いずくんぞ能く大廈を支えん(いちぼくいずくんぞよくたいかをささえん)
- 一木大廈の崩るるを支うる能わず(いちぼくたいかのくずるるをささうるあたわず)
- 井の中の蛙大海を知らず(いのなかのかわずたいかいをしらず)
- 上を下への大騒ぎ(うえをしたへのおおさわぎ)
- 独活の大木(うどのたいぼく)
- 独活の大木柱にならぬ(うどのたいぼくはしらにならぬ)
- 瓜の皮は大名に剝かせよ、柿の皮は乞食に剝かせよ(うりのかわはだいみょうにむかせよ、かきのかわはこじきにむかせよ)
- 江戸っ子の往き大名還り乞食(えどっこのゆきだいみょうかえりこじき)
「家」を含むことわざ
- 空き家で声嗄らす(あきやでこえからす)
- 空き家の雪隠(あきやのせっちん)
- 家鴨も鴨の気位(あひるもかものきぐらい)
- 家売らば縄の値(いえうらばなわのあたい)
- 家売れば釘の価(いえうればくぎのあたい)
- 家柄より芋茎(いえがらよりいもがら)
- 家柄よりも芋茎(いえがらよりもいもがら)
- 家給し人足る(いえきゅうしひとたる)
- 家に杖つく(いえにつえつく)
- 家に杖つく頃(いえにつえつくころ)
「言」を含むことわざ
- ああ言えばこう言う(ああいえばこういう)
- 合言葉にする(あいことばにする)
- 呆れて物が言えない(あきれてものがいえない)
- 明日の事を言えば鬼が笑う(あすのことをいえばおにがわらう)
- あっと言う間(あっというま)
- あっと言わせる(あっといわせる)
- 後から剝げる正月言葉(あとからはげるしょうがつことば)
- 穴を掘って言い入れる(あなをほっていいいれる)
- 有り体に言う(ありていにいう)
- 言い得て妙(いいえてみょう)
「親」を含むことわざ
- いつまでもあると思うな親と金(いつまでもあるとおもうなおやとかね)
- 命の親(いのちのおや)
- 打たれても親の杖(うたれてもおやのつえ)
- 打つも撫でるも親の恩(うつもなでるもおやのおん)
- 生みの親より育ての親(うみのおやよりそだてのおや)
- 親思う心にまさる親心(おやおもうこころにまさるおやごころ)
- 親方思いの主倒し(おやかたおもいのしゅたおし)
- 親方日の丸(おやかたひのまる)
- 親が親なら子も子(おやがおやならこもこ)
「同」を含むことわざ
- 畦から行くも田から行くも同じ(あぜからいくもたからいくもおなじ)
- いとこ同士は鴨の味(いとこどうしはかものあじ)
- 落ちれば同じ谷川の水(おちればおなじたにがわのみず)
- 落つれば同じ谷川の水(おつればおなじたにがわのみず)
- 同い年夫婦は火吹く力もない(おないどしみょうとはひふくちからもない)
- 同じ穴の狸(おなじあなのたぬき)
- 同じ穴の狐(おなじあなのむじな)
- 同じ穴の貉(おなじあなのむじな)
- 同じ釜の飯を食う(おなじかまのめしをくう)
「然」を含むことわざ
- 間然する所がない(かんぜんするところがない)
- 間然するところなし(かんぜんするところなし)
- 浩然の気(こうぜんのき)
- 浩然の気を養う(こうぜんのきをやしなう)
- 公然の秘密(こうぜんのひみつ)
- 然もあらばあれ(さもあらばあれ)
- 自然に帰れ(しぜんにかえれ)
- 然諾を重んずる(ぜんだくをおもんずる)
- 理の当然(りのとうぜん)
「店」を含むことわざ
- 大家と言えば親も同然、店子と言えば子も同然(おおやといえばおやもどうぜん、たなこといえばこもどうぜん)
- 千金を買う市あれど一文字を買う店なし(せんきんをかういちあれどいちもんじをかうみせなし)
- 店を閉める(みせをしめる)
- 店を畳む(みせをたたむ)
- 店を張る(みせをはる)



