いとこ同士は鴨の味とは
いとこ同士は鴨の味
いとこどうしはかものあじ
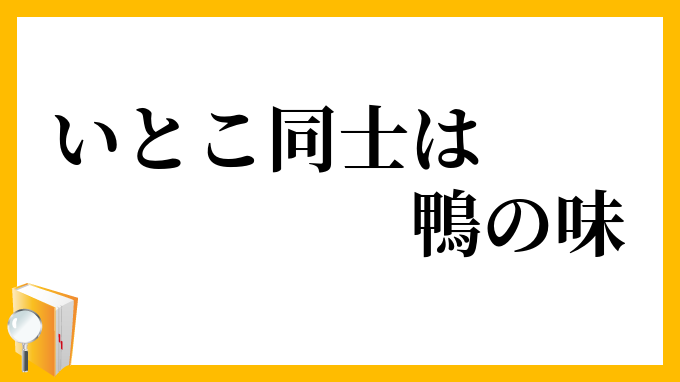
| 言葉 | いとこ同士は鴨の味 |
|---|---|
| 読み方 | いとこどうしはかものあじ |
| 意味 | いとこ同士の夫婦は、味がよいとされる鴨肉のように仲がよいということ。 |
| 場面用途 | 夫婦 / 親族 |
| 使用語彙 | 同士 |
| 使用漢字 | 同 / 士 / 鴨 / 味 |
「同」を含むことわざ
- 畦から行くも田から行くも同じ(あぜからいくもたからいくもおなじ)
- 大家と言えば親も同然、店子と言えば子も同然(おおやといえばおやもどうぜん、たなこといえばこもどうぜん)
- 落ちれば同じ谷川の水(おちればおなじたにがわのみず)
- 落つれば同じ谷川の水(おつればおなじたにがわのみず)
- 同い年夫婦は火吹く力もない(おないどしみょうとはひふくちからもない)
- 同じ穴の狸(おなじあなのたぬき)
- 同じ穴の狐(おなじあなのむじな)
- 同じ穴の貉(おなじあなのむじな)
- 同じ釜の飯を食う(おなじかまのめしをくう)
「士」を含むことわざ
- 一合取っても武士は武士(いちごうとってもぶしはぶし)
- 一富士、二鷹、三茄子(いちふじ、にたか、さんなすび)
- 来て見ればさほどでもなし富士の山(きてみればさほどでもなしふじのやま)
- 策士、策に溺れる(さくし、さくにおぼれる)
- 志士苦心多し(ししくしんおおし)
- 士族の商法(しぞくのしょうほう)
- 士は己を知る者の為に死す(しはおのれをしるもののためにしす)
- 好いた同士は泣いても連れる(すいたどうしはないてもつれる)
- 駿河の富士と一里塚(するがのふじといちりづか)
「鴨」を含むことわざ
- 逢い戻りは鴨の味(あいもどりはかものあじ)
- 家鴨も鴨の気位(あひるもかものきぐらい)
- いい鴨(いいかも)
- 鴨が葱を背負って来る(かもがねぎをしょってくる)
- 鴨葱(かもねぎ)
- 鴨の水搔き(かものみずかき)
- 献上の鴨(けんじょうのかも)
- 隣の貧乏鴨の味(となりのびんぼうかものあじ)
- 人の噂を言うは鴨の味(ひとのうわさをいうはかものあじ)



