犬も歩けば棒に当たるとは
犬も歩けば棒に当たる
いぬもあるけばぼうにあたる
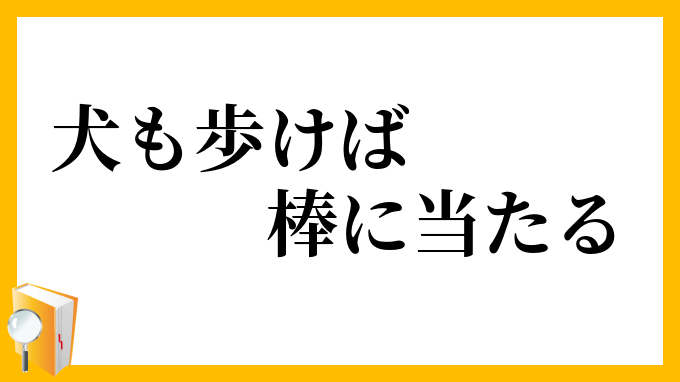
| 言葉 | 犬も歩けば棒に当たる |
|---|---|
| 読み方 | いぬもあるけばぼうにあたる |
| 意味 | 何かしようとすれば、災難に遭いやすいというたとえ。
または、何かをやっているうちに思わぬ幸運にめぐりあうことのたとえ。 犬はあちこち歩きまわり、人間の振り回す棒に当たる羽目になるということから、本来は出しゃばると思わぬ災難に遭うとの意味であったが、現在は幸運にめぐりあうとの意味でも用いられるため、幸運と災難のどちらの意味でも使われる言葉。 江戸いろはがるたの一つ。 |
| 使用漢字 | 犬 / 歩 / 棒 / 当 |
「犬」を含むことわざ
- 生きている犬は死んだライオンに勝る(いきているいぬはしんだらいおんにまさる)
- 一犬影に吠ゆれば百犬声に吠ゆ(いっけんかげにほゆればひゃっけんこえにほゆ)
- 犬一代に狸一匹(いぬいちだいにたぬきいっぴき)
- 犬が西向きゃ尾は東(いぬがにしむきゃおはひがし)
- 犬に論語(いぬにろんご)
- 犬の遠吠え(いぬのとおぼえ)
- 犬は人につき猫は家につく(いぬはひとにつきねこはいえにつく)
- 犬は三日飼えば三年恩を忘れぬ(いぬはみっかかえばさんねんおんをわすれぬ)
- 犬骨折って鷹の餌食(いぬほねおってたかのえじき)
「歩」を含むことわざ
- 歩く足には塵が付く(あるくあしにはちりがつく)
- 一歩譲る(いっぽゆずる)
- 一歩を踏み出す(いっぽをふみだす)
- 牛の歩み(うしのあゆみ)
- 蟹を縦に歩かせることはできない(かにをたてにあるかせることはできない)
- 邯鄲の歩み(かんたんのあゆみ)
- 五十歩百歩(ごじっぽひゃっぽ)
- 七歩の才(しちほのさい)
- 千里の道も一歩から(せんりのみちもいっぽから)
「棒」を含むことわざ
- 足が棒になる(あしがぼうになる)
- 足を棒にする(あしをぼうにする)
- 後棒を担ぐ(あとぼうをかつぐ)
- 争い果てての棒乳切り(あらそいはててのぼうちぎり)
- 飢えたる犬は棒を恐れず(うえたるいぬはぼうをおそれず)
- 嘘つきは泥棒の始まり(うそつきはどろぼうのはじまり)
- 近江泥棒伊勢乞食(おうみどろぼういせこじき)
- お先棒を担ぐ(おさきぼうをかつぐ)
- 鬼に金棒(おににかなぼう)



