千里の馬は常にあれども伯楽は常にはあらずとは
千里の馬は常にあれども伯楽は常にはあらず
せんりのうまはつねにあれどもはくらくはつねにはあらず
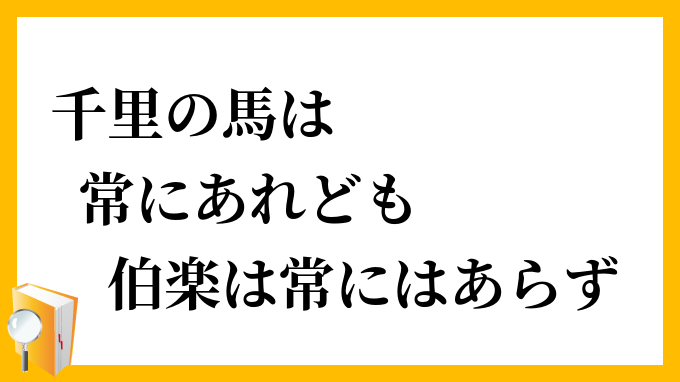
| 言葉 | 千里の馬は常にあれども伯楽は常にはあらず |
|---|---|
| 読み方 | せんりのうまはつねにあれどもはくらくはつねにはあらず |
| 意味 | 有能な人材はいつの世にもいるが、その能力を見出して育てる優れた指導者は少ないということのたとえ。
「千里の馬」は、一日に千里も走れるほどの優れた馬。転じて、優れた才能の人物。 「伯楽」は牛馬の良し悪しを見分ける名人のこと。転じて、人物を見抜いて、その才能を引き出し育てる優れた指導者のこと。 いつの時代にも、一日に千里を走るほどの優れた馬はいるが、その名馬の能力を引き出す伯楽は、いつもいるわけではないということから。 |
| 場面用途 | 才能・能力 / 馬 |
| 使用語彙 | 千 / 馬 / 伯楽 |
| 使用漢字 | 千 / 里 / 馬 / 常 / 伯 / 楽 |
「千」を含むことわざ
- 悪事千里を走る(あくじせんりをはしる)
- 朝起き千両、夜起き百両(あさおきせんりょう、よおきひゃくりょう)
- 値千金(あたいせんきん)
- あの世の千日、この世の一日(あのよのせんにち、このよのいちにち)
- 諍い果てての千切り木(いさかいはててのちぎりぎ)
- 一日千秋の思い(いちじつせんしゅうのおもい)
- 一髪、千鈞を引く(いっぱつ、せんきんをひく)
- 一匹の馬が狂えば千匹の馬も狂う(いっぴきのうまがくるえばせんびきのうまもくるう)
- 牛も千里馬も千里(うしもせんりうまもせんり)
- 後ろ千両前一文(うしろせんりょうまえいちもん)
「里」を含むことわざ
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 悪事千里を走る(あくじせんりをはしる)
- 朝茶は七里帰っても飲め(あさちゃはしちりかえってものめ)
- 牛も千里馬も千里(うしもせんりうまもせんり)
- 縁あれば千里(えんあればせんり)
- お里が知れる(おさとがしれる)
- 門松は冥土の旅の一里塚(かどまつはめいどのたびのいちりづか)
- 好事門を出でず、悪事千里を行く(こうじもんをいでず、あくじせんりをいく)
- 酒屋へ三里、豆腐屋へ二里(さかやへさんり、とうふやへにり)
- 囁き千里(ささやきせんり)
「馬」を含むことわざ
- 朝雨馬に鞍置け(あさあめうまにくらおけ)
- 鞍上人なく、鞍下馬なし(あんじょうひとなく、あんかうまなし)
- 生き馬の目を抜く(いきうまのめをぬく)
- 一番風呂は馬鹿が入る(いちばんぶろはばかがはいる)
- 一匹の馬が狂えば千匹の馬も狂う(いっぴきのうまがくるえばせんびきのうまもくるう)
- 牛は牛連れ、馬は馬連れ(うしはうしづれ、うまはうまづれ)
- 牛も千里馬も千里(うしもせんりうまもせんり)
- 牛を馬に乗り換える(うしをうまにのりかえる)
- 内で掃除せぬ馬は外で毛を振る(うちでそうじせぬうまはそとでけをふる)
- 馬が合う(うまがあう)
「常」を含むことわざ
- 過ちは人の常、許すは神の業(あやまちはひとのつね、ゆるすはかみのわざ)
- 奢る者は心常に貧し(おごるものはこころつねにまずし)
- 常軌を逸する(じょうきをいっする)
- 常が大事(つねがだいじ)
- 常に来る客は歓迎されず(つねにくるきゃくはかんげいされず)
- 日常茶飯事(にちじょうさはんじ)
- 無常の鬼が身を責むる(むじょうのおにがみをせむる)
- 無常の風は時を選ばず(むじょうのかぜはときをえらばず)
- 世の中は年中三月常月夜、嬶十七俺二十、負わず借らずに子三人(よのなかはねんじゅうさんがつじょうつきよ、かかあじゅうしちおれはたち、おわずからずにこさんにん)
「伯」を含むことわざ
- 千里の馬は常にあれども伯楽は常にはあらず(せんりのうまはつねにあれどもはくらくはつねにはあらず)
- 千里の馬も伯楽に会わず(せんりのうまもはくらくにあわず)
- 伯牙、琴を破る(はくが、ことをやぶる)
- 伯仲の間(はくちゅうのかん)
- 伯兪、杖に泣く(はくゆつえになく)
- 伯楽の一顧(はくらくのいっこ)



