赤子のうちは七国七里の者に似るとは
赤子のうちは七国七里の者に似る
あかごのうちはななくにななさとのものににる
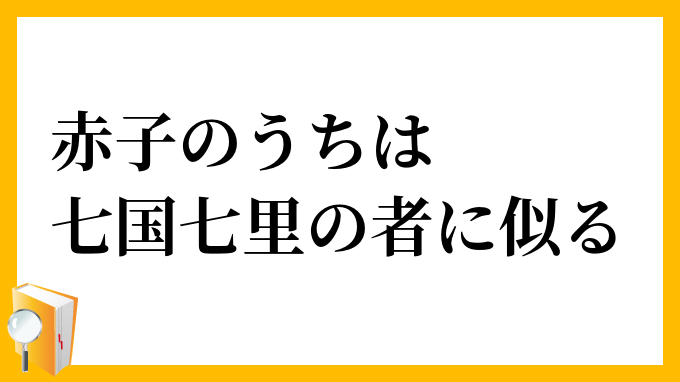
| 言葉 | 赤子のうちは七国七里の者に似る |
|---|---|
| 読み方 | あかごのうちはななくにななさとのものににる |
| 意味 | 赤ん坊ははっきりした特長がないので、似てると思って見ればあちこちの誰にでも似て見えるということ。「七国七里」は諸所方々のこと。 |
| 使用語彙 | 赤子 / 七 |
| 使用漢字 | 赤 / 子 / 七 / 国 / 里 / 者 / 似 |
「赤」を含むことわざ
- 赤いは酒の咎(あかいはさけのとが)
- 赤くなる(あかくなる)
- 赤子の腕を捩じる(あかごのうでをねじる)
- 赤子の手をねじる(あかごのてをねじる)
- 赤子の手を捩じるよう(あかごのてをねじるよう)
- 赤子の手を捻る(あかごのてをひねる)
- 赤子の手を捻るよう(あかごのてをひねるよう)
- 赤子は泣き泣き育つ(あかごはなきなきそだつ)
- 赤子を裸にしたよう(あかごをはだかにしたよう)
「子」を含むことわざ
- 赤子の腕を捩じる(あかごのうでをねじる)
- 赤子の手をねじる(あかごのてをねじる)
- 赤子の手を捩じるよう(あかごのてをねじるよう)
- 赤子の手を捻る(あかごのてをひねる)
- 赤子の手を捻るよう(あかごのてをひねるよう)
- 赤子は泣き泣き育つ(あかごはなきなきそだつ)
- 赤子を裸にしたよう(あかごをはだかにしたよう)
- 秋茄子は嫁に食わすな(あきなすはよめにくわすな)
- 秋の日と娘の子はくれぬようでくれる(あきのひとむすめのこはくれぬようでくれる)
「七」を含むことわざ
- 朝起きは七つの徳(あさおきはななつのとく)
- 朝茶は七里帰っても飲め(あさちゃはしちりかえってものめ)
- 伊勢へ七度、熊野へ三度(いせへななたび、くまのへみたび)
- 色の白いは七難隠す(いろのしろいはしちなんかくす)
- 浮き沈み七度(うきしずみななたび)
- 浮世は衣装七分(うきよはいしょうしちぶ)
- 兎も七日なぶれば噛みつく(うさぎもなぬかなぶればかみつく)
- 男心と秋の空は一夜に七度変わる(おとこごころとあきのそらはいちやにななたびかわる)
- 男は敷居を跨げば七人の敵あり(おとこはしきいをまたげばしちにんのてきあり)
「国」を含むことわざ
- 家に鼠、国に盗人(いえにねずみ、くににぬすびと)
- 一国一城の主(いっこくいちじょうのあるじ)
- 華胥の国に遊ぶ(かしょのくににあそぶ)
- 国に盗人、家に鼠(くににぬすびと、いえにねずみ)
- 国乱れて忠臣見る(くにみだれてちゅうしんあらわる)
- 国破れて山河在り(くにやぶれてさんがあり)
- 言葉は国の手形(ことばはくにのてがた)
- 三国一(さんごくいち)
- 修身斉家治国平天下(しゅうしんせいかちこくへいてんか)
「里」を含むことわざ
- 悪事、千里を走る(あくじ、せんりをはしる)
- 悪事、千里を行く(あくじせんりをいく)
- 朝茶は七里帰っても飲め(あさちゃはしちりかえってものめ)
- 一時違えば三里の遅れ(いっときちがえばさんりのおくれ)
- 牛も千里馬も千里(うしもせんりうまもせんり)
- 縁あれば千里(えんあればせんり)
- お里が知れる(おさとがしれる)
- 門松は冥土の旅の一里塚(かどまつはめいどのたびのいちりづか)
- 門松は冥途の旅の一里塚(かどまつはめいどのたびのいちりづか)
「者」を含むことわざ
- 愛出ずる者は愛返り、福往く者は福来る(あいいずるものはあいかえり、ふくゆくものはふくきたる)
- 青表紙を叩いた者にはかなわぬ(あおびょうしをたたいたものにはかなわぬ)
- 垢で死んだ者はない(あかでしんだものはない)
- 当たった者のふの悪さ(あたったもののふのわるさ)
- 新たに沐する者は必ず冠を弾く(あらたにもくするものはかならずかんむりをはじく)
- 医者が取るか坊主が取るか(いしゃがとるかぼうずがとるか)
- 医者寒からず儒者寒し(いしゃさむからずじゅしゃさむし)
- 医者上手にかかり下手(いしゃじょうずにかかりべた)
- 医者と味噌は古いほどよい(いしゃとみそはふるいほどよい)



