親に似ぬ子は鬼子とは
親に似ぬ子は鬼子
おやににぬこはおにご
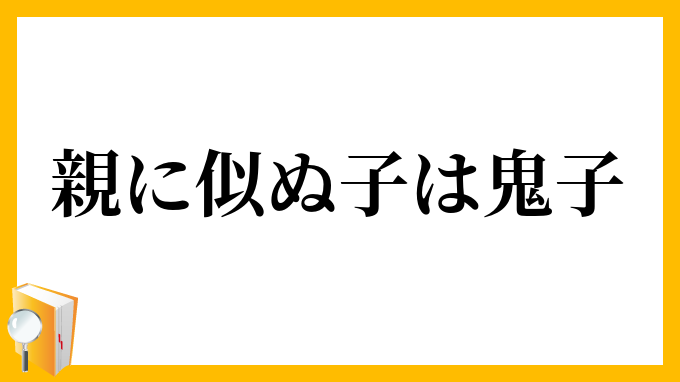
| 言葉 | 親に似ぬ子は鬼子 |
|---|---|
| 読み方 | おやににぬこはおにご |
| 意味 | 子どもは当然親に似るものであり、親に似ない子はいないということ。
親に似ない子は人間の子ではなく鬼の子であるとの意から。 |
| 異形 | 親に似ぬ子は鬼っ子(おやににぬこはおにっこ) |
| 場面用途 | 親子 / 親族 / 子ども |
| 使用語彙 | 親 / 鬼子 |
| 使用漢字 | 親 / 似 / 子 / 鬼 |
「親」を含むことわざ
- いつまでもあると思うな親と金(いつまでもあるとおもうなおやとかね)
- 命の親(いのちのおや)
- 打たれても親の杖(うたれてもおやのつえ)
- 打つも撫でるも親の恩(うつもなでるもおやのおん)
- 生みの親より育ての親(うみのおやよりそだてのおや)
- 大家と言えば親も同然、店子と言えば子も同然(おおやといえばおやもどうぜん、たなこといえばこもどうぜん)
- 親思う心にまさる親心(おやおもうこころにまさるおやごころ)
- 親方思いの主倒し(おやかたおもいのしゅたおし)
- 親方日の丸(おやかたひのまる)
- 親が親なら子も子(おやがおやならこもこ)
「似」を含むことわざ
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 鵜の真似をする烏(うのまねをするからす)
- 鵜の真似をする烏水に溺れる(うのまねをするからすみずにおぼれる)
- 鵜の真似をする烏水を呑む(うのまねをするからすみずをのむ)
- 往時渺茫としてすべて夢に似たり(おうじびょうぼうとしてすべてゆめににたり)
- 蟹は甲羅に似せて穴を掘る(かにはこうらににせてあなをほる)
- 烏が鵜の真似(からすがうのまね)
- 外面似菩薩、内心如夜叉(げめんじぼさつ、ないしんにょやしゃ)
「子」を含むことわざ
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 赤子の腕を捩じる(あかごのうでをねじる)
- 赤子の手をねじる(あかごのてをねじる)
- 赤子の手を捩じるよう(あかごのてをねじるよう)
- 赤子の手を捻る(あかごのてをひねる)
- 赤子の手を捻るよう(あかごのてをひねるよう)
- 赤子は泣き泣き育つ(あかごはなきなきそだつ)
- 赤子を裸にしたよう(あかごをはだかにしたよう)
- 秋茄子は嫁に食わすな(あきなすはよめにくわすな)
- 秋の日と娘の子はくれぬようでくれる(あきのひとむすめのこはくれぬようでくれる)



