千里の道も一歩からとは
千里の道も一歩から
せんりのみちもいっぽから
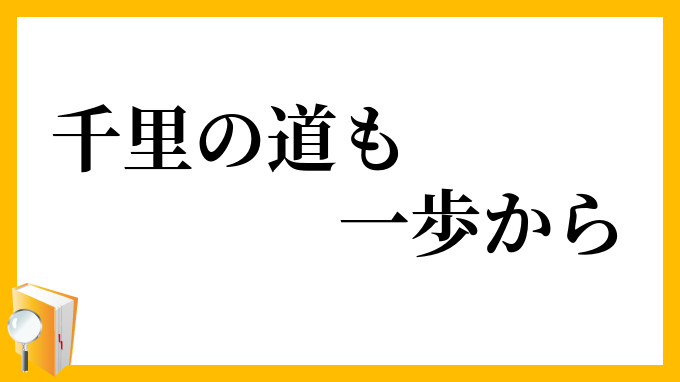
| 言葉 | 千里の道も一歩から |
|---|---|
| 読み方 | せんりのみちもいっぽから |
| 意味 | 大きな目標・目的を達成するためには、身近なことからこつこつと努力を積み重ねていくことが大切であるということ。
千里の道のりも踏み出した一歩から始まるとの意から。 「千里の行も足下より始まる」ともいう。 |
| 異形 | 千里の行も足下より始まる(せんりのこうもそっかよりはじまる) |
| 場面用途 | 積み重ね |
| 類句 | 遠きに行くは必ず近きよりす(とおきにゆくはかならずちかきよりす) |
| 高きに登るには低きよりす(たかきにのぼるにはひくきよりす) | |
| 使用語彙 | 千 / 一歩 |
| 使用漢字 | 千 / 里 / 道 / 一 / 歩 / 行 / 足 / 下 / 始 |
「千」を含むことわざ
- 悪事千里を走る(あくじせんりをはしる)
- 朝起き千両、夜起き百両(あさおきせんりょう、よおきひゃくりょう)
- 値千金(あたいせんきん)
- あの世の千日、この世の一日(あのよのせんにち、このよのいちにち)
- 諍い果てての千切り木(いさかいはててのちぎりぎ)
- 一日千秋の思い(いちじつせんしゅうのおもい)
- 一髪、千鈞を引く(いっぱつ、せんきんをひく)
- 一匹の馬が狂えば千匹の馬も狂う(いっぴきのうまがくるえばせんびきのうまもくるう)
- 牛も千里馬も千里(うしもせんりうまもせんり)
- 後ろ千両前一文(うしろせんりょうまえいちもん)
「里」を含むことわざ
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 悪事千里を走る(あくじせんりをはしる)
- 朝茶は七里帰っても飲め(あさちゃはしちりかえってものめ)
- 牛も千里馬も千里(うしもせんりうまもせんり)
- 縁あれば千里(えんあればせんり)
- お里が知れる(おさとがしれる)
- 門松は冥土の旅の一里塚(かどまつはめいどのたびのいちりづか)
- 好事門を出でず、悪事千里を行く(こうじもんをいでず、あくじせんりをいく)
- 酒屋へ三里、豆腐屋へ二里(さかやへさんり、とうふやへにり)
- 囁き千里(ささやきせんり)
「道」を含むことわざ
- 朝に道を聞かば夕べに死すとも可なり(あしたにみちをきかばゆうべにしすともかなり)
- 家を道端に作れば三年成らず(いえをみちばたにつくればさんねんならず)
- 意志のある所には道がある(いしのあるところにはみちがある)
- 鼬の道切り(いたちのみちきり)
- 一芸は道に通ずる(いちげいはみちにつうずる)
- 茨の道(いばらのみち)
- 老いたる馬は道を忘れず(おいたるうまはみちをわすれず)
- 学問に王道なし(がくもんにおうどうなし)
- 軌道に乗る(きどうにのる)
- 荊棘の道(けいきょくのみち)
「一」を含むことわざ
- 悪は一旦の事なり(あくはいったんのことなり)
- 欠伸を一緒にすれば三日従兄弟(あくびをいっしょにすればみっかいとこ)
- 朝顔の花一時(あさがおのはなひととき)
- 朝の一時は晩の二時に当たる(あさのひとときはばんのふたときにあたる)
- 薊の花も一盛り(あざみのはなもひとさかり)
- あの世の千日、この世の一日(あのよのせんにち、このよのいちにち)
- 危ない橋も一度は渡れ(あぶないはしもいちどはわたれ)
- 粟一粒は汗一粒(あわひとつぶはあせひとつぶ)
- 板子一枚下は地獄(いたごいちまいしたはじごく)
- 一瓜実に二丸顔(いちうりざねににまるがお)
「歩」を含むことわざ
- 歩く足には塵が付く(あるくあしにはちりがつく)
- 一歩譲る(いっぽゆずる)
- 一歩を踏み出す(いっぽをふみだす)
- 犬も歩けば棒に当たる(いぬもあるけばぼうにあたる)
- 牛の歩み(うしのあゆみ)
- 蟹を縦に歩かせることはできない(かにをたてにあるかせることはできない)
- 邯鄲の歩み(かんたんのあゆみ)
- 五十歩百歩(ごじっぽひゃっぽ)
- 七歩の才(しちほのさい)
「行」を含むことわざ
- 悪事千里を行く(あくじせんりをいく)
- 畦から行くも田から行くも同じ(あぜからいくもたからいくもおなじ)
- 後へも先へも行かぬ(あとへもさきへもいかぬ)
- 好い線を行く(いいせんをいく)
- 言うと行うとは別問題である(いうとおこなうとはべつもんだいである)
- 言うは易く行うは難し(いうはやすくおこなうはかたし)
- 行き当たりばったり(いきあたりばったり)
- 行き掛けの駄賃(いきがけのだちん)
- 行く行くの長居り(いくいくのながおり)
- 裏の裏を行く(うらのうらをいく)
「足」を含むことわざ
- 相手にとって不足はない(あいてにとってふそくはない)
- 足掻きが取れない(あがきがとれない)
- 揚げ足を取る(あげあしをとる)
- 足がある(あしがある)
- 足が重い(あしがおもい)
- 足が竦む(あしがすくむ)
- 足が地に着かない(あしがちにつかない)
- 足が付く(あしがつく)
- 足が出る(あしがでる)
- 足が遠のく(あしがとおのく)
「下」を含むことわざ
- 敢えて天下の先とならず(あえててんかのさきとならず)
- 商い上手の仕入れ下手(あきないじょうずのしいれべた)
- 上げたり下げたり(あげたりさげたり)
- 足下から鳥が立つ(あしもとからとりがたつ)
- 足下につけ込む(あしもとにつけこむ)
- 足下に火が付く(あしもとにひがつく)
- 足下にも及ばない(あしもとにもおよばない)
- 足下の明るいうち(あしもとのあかるいうち)
- 足下へも寄り付けない(あしもとへもよりつけない)
- 足下を固める(あしもとをかためる)



