足下から鳥が立つとは
足下から鳥が立つ
あしもとからとりがたつ
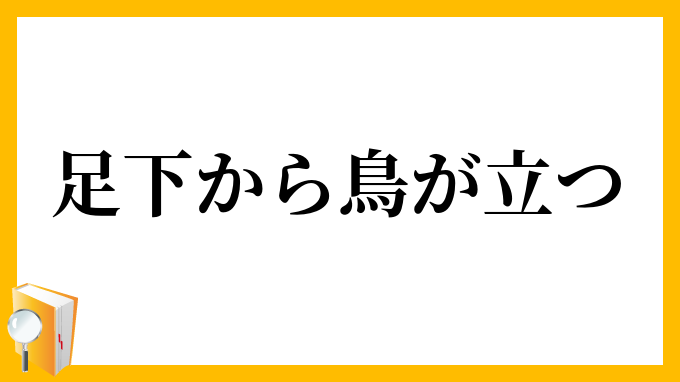
| 言葉 | 足下から鳥が立つ |
|---|---|
| 読み方 | あしもとからとりがたつ |
| 意味 | 身近なところで、突然思いもかけないことが起きることのたとえ。また、急に思い立って物事を始めるようす。 |
| 異形 | 足元から鳥が立つ(あしもとからとりがたつ) |
| 足許から鳥が立つ(あしもとからとりがたつ) | |
| 使用語彙 | 足下 / 鳥 / 足元 / 足許 |
| 使用漢字 | 足 / 下 / 鳥 / 立 / 元 / 許 |
「足」を含むことわざ
- 相手にとって不足はない(あいてにとってふそくはない)
- 足掻きが取れない(あがきがとれない)
- 挙げ足を取る(あげあしをとる)
- 揚げ足を取る(あげあしをとる)
- 足がある(あしがある)
- 足が重い(あしがおもい)
- 足が地に付かない(あしがちにつかない)
- 足が地に着かない(あしがちにつかない)
- 足が付く(あしがつく)
- 足が出る(あしがでる)
「下」を含むことわざ
- 敢えて天下の先とならず(あえててんかのさきとならず)
- 商い上手の仕入れ下手(あきないじょうずのしいれべた)
- 上げたり下げたり(あげたりさげたり)
- 足下につけ込む(あしもとにつけこむ)
- 足下に火が付く(あしもとにひがつく)
- 足下にも及ばない(あしもとにもおよばない)
- 足下にも寄りつけない(あしもとにもよりつけない)
- 足下の明るいうち(あしもとのあかるいうち)
- 足下へも寄り付けない(あしもとへもよりつけない)
「鳥」を含むことわざ
- 青い鳥(あおいとり)
- 飛鳥川の淵瀬(あすかがわのふちせ)
- あだし野の露、鳥辺野の煙(あだしののつゆ、とりべののけむり)
- 仇野の露、鳥辺野の煙(あだしののつゆ、とりべののけむり)
- 仇野の露、鳥部野の煙(あだしののつゆ、とりべののけむり)
- 徒野の露、鳥辺野の煙(あだしののつゆ、とりべののけむり)
- 徒野の露、鳥部野の煙(あだしののつゆ、とりべののけむり)
「立」を含むことわざ
- 開いた口に戸は立てられぬ(あいたくちにはとはたてられぬ)
- 愛立てないは祖母育ち(あいだてないはばばそだち)
- 間に立つ(あいだにたつ)
- 青筋を立てる(あおすじをたてる)
- 証が立つ(あかしがたつ)
- 証を立てる(あかしをたてる)
- 秋風が立つ(あきかぜがたつ)
- 商人と屏風は直ぐには立たぬ(あきんどとびょうぶはすぐにはたたぬ)
- 商人と屏風は曲がらねば立たぬ(あきんどとびょうぶはまがらねばたたぬ)
「元」を含むことわざ
- 商人の元値(あきんどのもとね)
- 足元に付け込む(あしもとにつけこむ)
- 足元に火が付く(あしもとにひがつく)
- 足元にも及ばない(あしもとにもおよばない)
- 足元の明るいうち(あしもとのあかるいうち)
- 足元へも寄り付けない(あしもとへもよりつけない)
- 足元を固める(あしもとをかためる)
- 足元を見る(あしもとをみる)
- 一日の計は朝にあり、一年の計は元旦にあり(いちじつのけいはあしたにあり、いちねんのけいはがんたんにあり)



