青い鳥とは
青い鳥
あおいとり
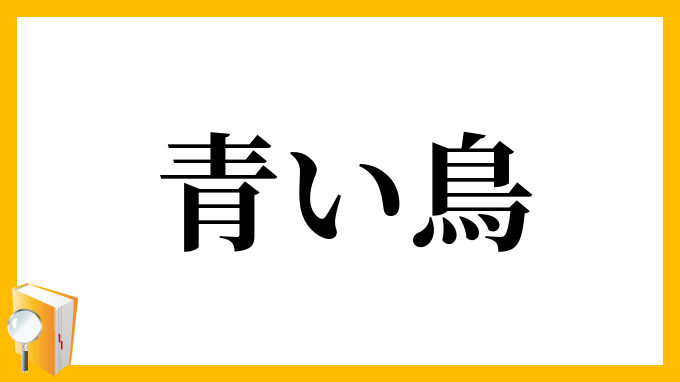
| 言葉 | 青い鳥 |
|---|---|
| 読み方 | あおいとり |
| 意味 | 身近にあって気づかない幸福のたとえ。チルチルとミチルの兄妹が、幸せを招くという青い鳥を探して旅に出るが、実は青い鳥は自分の家の鳥かごにいたというメーテルリンク作の童話劇「青い鳥」から。 |
| 使用語彙 | 青 / 鳥 |
| 使用漢字 | 青 / 鳥 |
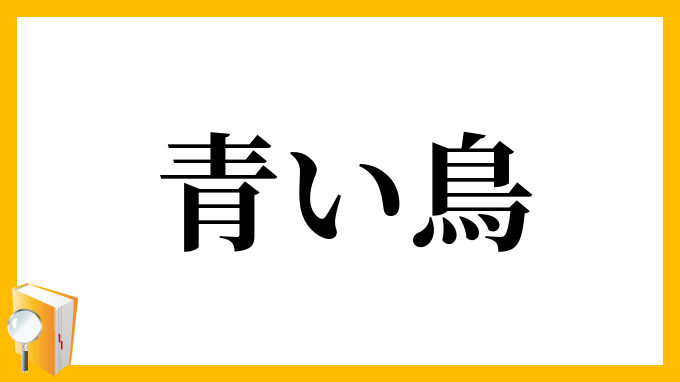
| 言葉 | 青い鳥 |
|---|---|
| 読み方 | あおいとり |
| 意味 | 身近にあって気づかない幸福のたとえ。チルチルとミチルの兄妹が、幸せを招くという青い鳥を探して旅に出るが、実は青い鳥は自分の家の鳥かごにいたというメーテルリンク作の童話劇「青い鳥」から。 |
| 使用語彙 | 青 / 鳥 |
| 使用漢字 | 青 / 鳥 |