青写真を描くとは
青写真を描く
あおじゃしんをえがく
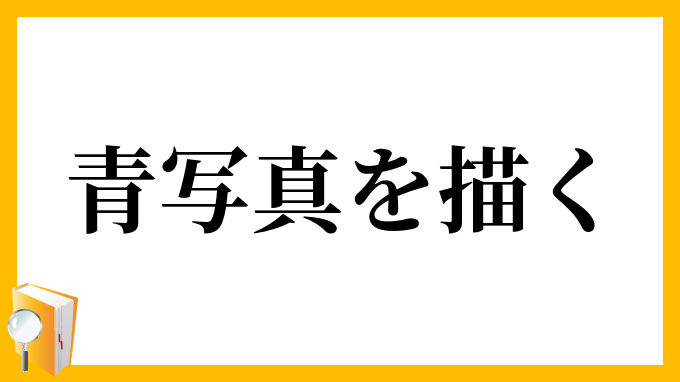
| 言葉 | 青写真を描く |
|---|---|
| 読み方 | あおじゃしんをえがく |
| 意味 | 将来の計画を具体的に考える。未来の姿を想像する。
「青写真」は、設計図の複写に用いられたことから、設計図のこと。 |
| 使用語彙 | 青写真 / 青 / 描く |
| 使用漢字 | 青 / 写 / 真 / 描 |
「青」を含むことわざ
- 青い鳥(あおいとり)
- 青柿が熟柿弔う(あおがきがじゅくしとむらう)
- 青くなる(あおくなる)
- 青筋を立てる(あおすじをたてる)
- 青田買い(あおたがい)
- 青菜に塩(あおなにしお)
- 青菜は男に見せな(あおなはおとこにみせな)
- 青菜は男に見せるな(あおなはおとこにみせるな)
- 青二才(あおにさい)
「写」を含むことわざ
- 青写真を描く(あおじゃしんをえがく)
- 十遍読むより一遍写せ(じっぺんよむよりいっぺんうつせ)
- 十読は一写に如かず(じゅうどくはいちしゃにしかず)
「真」を含むことわざ
- 鵜の真似をする烏(うのまねをするからす)
- 鵜の真似をする烏水に溺れる(うのまねをするからすみずにおぼれる)
- 鵜の真似をする烏水を呑む(うのまねをするからすみずをのむ)
- お先真っ暗(おさきまっくら)
- 烏が鵜の真似(からすがうのまね)
- 猿の人真似(さるのひとまね)
- 死ぬるばかりは真(しぬるばかりはまこと)
- 知らずば人真似(しらずばひとまね)
- 真に迫る(しんにせまる)



