虎を描いて狗に類すとは
虎を描いて狗に類す
とらをえがいていぬにるいす
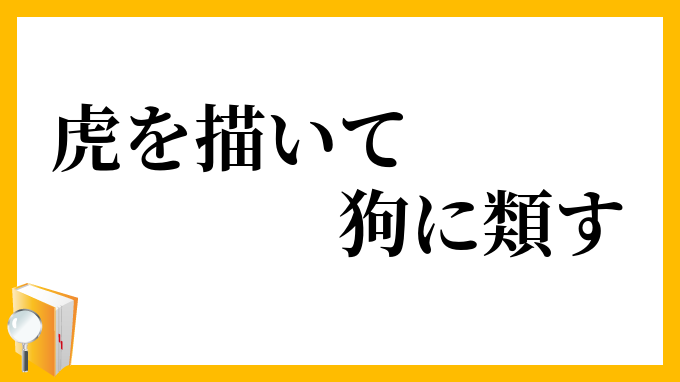
| 言葉 | 虎を描いて狗に類す |
|---|---|
| 読み方 | とらをえがいていぬにるいす |
| 意味 | 凡人が優れた人の真似をして、軽薄になることのたとえ。また、立派過ぎるものを求めて失敗することのたとえ。
虎を書こうとして犬の絵になってしまうということから。 |
| 出典 | 『後漢書』馬援 |
| 異形 | 虎を画きて狗に類す(とらをえがきていぬにるいす) |
| 類句 | 虎を描いて猫に類す(とらをえがいてねこにるいす) |
| 竜を画いて狗に類す(りゅうをえがいていぬにるいす) | |
| 使用語彙 | 虎 |
| 使用漢字 | 虎 / 描 / 狗 / 類 / 画 |
「虎」を含むことわざ
- 危うきこと虎の尾を踏むが如し(あやうきこととらのおをふむがごとし)
- 市に虎あり(いちにとらあり)
- 苛政は虎よりも猛し(かせいはとらよりもたけし)
- 騎虎の勢い(きこのいきおい)
- 狐虎の威を借る(きつねとらのいをかる)
- 狐虎の威を藉る(きつねとらのいをかる)
- 虎穴に入らずんば虎子を得ず(こけつにいらずんばこじをえず)
- 虎口(ここう)
- 虎口を脱する(ここうをだっする)
- 虎口を逃れて竜穴に入る(ここうをのがれてりゅうけつにいる)
「描」を含むことわざ
- 青写真を描く(あおじゃしんをえがく)
- 絵に描いた地震(えにかいたじしん)
- 絵に描いた餅(えにかいたもち)
- 絵に描いたよう(えにかいたよう)
- 氷に鏤め、脂に描く(こおりにちりばめあぶらにえがく)
- 氷に鏤め、水に描く(こおりにちりばめみずにえがく)
- 虎を描いて猫に類す(とらをえがいてねこにるいす)
- 猫でない証拠に竹を描いておき(ねこでないしょうこにたけをかいておき)
- 水に絵を描く(みずにえをかく)
「狗」を含むことわざ
- 狡兎死して走狗烹らる(こうとししてそうくにらる)
- 喪家の狗(そうかのいぬ)
- 鯛なくば狗母魚(たいなくばえそ)
- 天狗になる(てんぐになる)
- 天狗の飛び損ない(てんぐのとびそこない)
- 羊頭を掲げて狗肉を売る(ようとうをかかげてくにくをうる)
- 羊頭を掛けて狗肉を売る(ようとうをかけてくにくをうる)
- 竜を画いて狗に類す(りゅうをえがいていぬにるいす)
「類」を含むことわざ
- 悪獣もなおその類を思う(あくじゅうもなおそのるいをおもう)
- 遠くの親類より近くの他人(とおくのしんるいよりちかくのたにん)
- 虎を描いて猫に類す(とらをえがいてねこにるいす)
- 同類相求む(どうるいあいもとむ)
- 竜を画いて狗に類す(りゅうをえがいていぬにるいす)
- 竜を画きて狗に類す(りゅうをえがきていぬにるいす)
- 類は友を呼ぶ(るいはともをよぶ)
- 類を以て集まる(るいをもってあつまる)



