虎穴に入らずんば虎子を得ずとは
虎穴に入らずんば虎子を得ず
こけつにいらずんばこじをえず
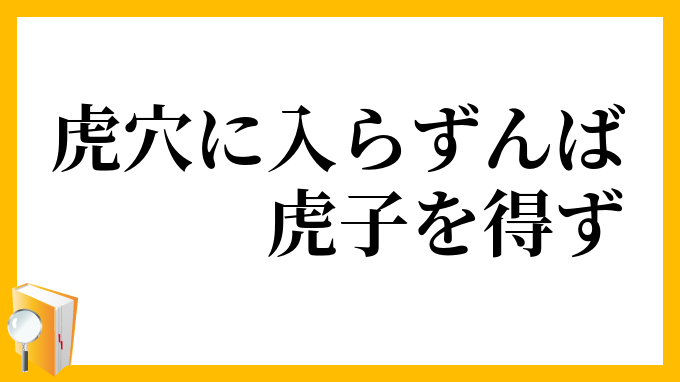
| 言葉 | 虎穴に入らずんば虎子を得ず |
|---|---|
| 読み方 | こけつにいらずんばこじをえず |
| 意味 | 危険なことも避けていては、大きな成功は得られないということ。
虎の住む穴に入らなければ、虎の子をつかまえることは出来ないとの意から。 |
| 出典 | 『後漢書』班超 |
| 場面用途 | 危険 |
| 類句 | 危ない橋も一度は渡れ(あぶないはしもいちどはわたれ) |
| 使用語彙 | 虎穴 |
| 使用漢字 | 虎 / 穴 / 入 / 子 / 得 |
「虎」を含むことわざ
- 危うきこと虎の尾を踏むが如し(あやうきこととらのおをふむがごとし)
- 苛政は虎よりも猛し(かせいはとらよりもたけし)
- 騎虎の勢い(きこのいきおい)
- 狐虎の威を藉る(きつねとらのいをかる)
- 虎口(ここう)
- 虎口を脱する(ここうをだっする)
- 虎口を逃れて竜穴に入る(ここうをのがれてりゅうけつにいる)
- 三人、市虎を成す(さんにん、しこをなす)
- 千里の野に虎を放つ(せんりののにとらをはなつ)
「穴」を含むことわざ
- 穴が開く(あながあく)
- 穴があったら入りたい(あながあったらはいりたい)
- 穴の開くほど(あなのあくほど)
- 穴の貉を値段する(あなのむじなをねだんする)
- 穴をあける(あなをあける)
- 穴を埋める(あなをうめる)
- 穴を掘って言い入れる(あなをほっていいいれる)
- 蟻の穴から堤も崩れる(ありのあなからつつみもくずれる)
- 慌てる蟹は穴へ入れぬ(あわてるかにはあなへはいれぬ)
- 同じ穴の貉(おなじあなのむじな)
「入」を含むことわざ
- 間に入る(あいだにはいる)
- 合いの手を入れる(あいのてをいれる)
- 赤を入れる(あかをいれる)
- 秋風と夫婦喧嘩は日が入りゃ止む(あきかぜとふうふげんかはひがいりゃやむ)
- 商い上手の仕入れ下手(あきないじょうずのしいれべた)
- 秋の入り日と年寄りはだんだん落ち目が早くなる(あきのいりひととしよりはだんだんおちめがはやくなる)
- 足を入れる(あしをいれる)
- 足を踏み入れる(あしをふみいれる)
- 頭に入れる(あたまにいれる)
- 新しき葡萄酒は新しき革袋に入れよ(あたらしきぶどうしゅはあたらしきかわぶくろにいれよ)
「子」を含むことわざ
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 赤子の腕を捩じる(あかごのうでをねじる)
- 赤子の手を捻る(あかごのてをひねる)
- 赤子は泣き泣き育つ(あかごはなきなきそだつ)
- 赤子を裸にしたよう(あかごをはだかにしたよう)
- 秋茄子は嫁に食わすな(あきなすはよめにくわすな)
- 秋の日と娘の子はくれぬようでくれる(あきのひとむすめのこはくれぬようでくれる)
- 商人の子は算盤の音で目を覚ます(あきんどのこはそろばんのおとでめをさます)
- 熱火子に払う(あつびこにはらう)
- 後先息子に中娘(あとさきむすこになかむすめ)



