伊勢へ七度、熊野へ三度とは
伊勢へ七度、熊野へ三度
いせへななたび、くまのへみたび
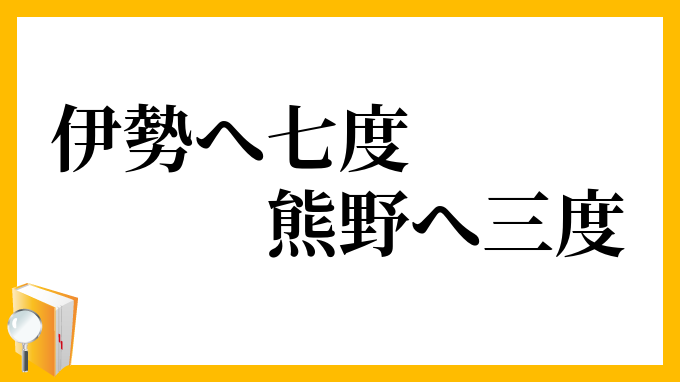
| 言葉 | 伊勢へ七度、熊野へ三度 |
|---|---|
| 読み方 | いせへななたび、くまのへみたび |
| 意味 | 信仰心が深いことのたとえ。
伊勢神宮へ七度、熊野三山へ三度もお参りするほど信仰深いとの意から。 このあと続けて「愛宕(あたご)様へは月参り」ともいう。 |
| 使用語彙 | 七 |
| 使用漢字 | 伊 / 勢 / 七 / 度 / 熊 / 野 / 三 |
「伊」を含むことわざ
- 遠慮ひだるし伊達寒し(えんりょひだるしだてさむし)
- 近江泥棒伊勢乞食(おうみどろぼういせこじき)
- 賢者ひだるし、伊達寒し(けんじゃひだるし、だてさむし)
- 伊達の薄着(だてのうすぎ)
- 伊達の素足もないから起こる、あれば天鵞絨の足袋も履く(だてのすあしもないからおこる、あればびろうどのたびもはく)
- 伊達の素足も貧から起こる(だてのすあしもひんからおこる)
- 難波の葦は伊勢の浜荻(なにわのあしはいせのはまおぎ)
「勢」を含むことわざ
- 近江泥棒伊勢乞食(おうみどろぼういせこじき)
- 騎虎の勢い(きこのいきおい)
- 旭日昇天の勢い(きょくじつしょうてんのいきおい)
- 虚勢を張る(きょせいをはる)
- 決河の勢い(けっかのいきおい)
- 姿勢を正す(しせいをただす)
- 多勢に無勢(たぜいにぶぜい)
- 多勢を頼む群鴉(たぜいをたのむむらがらす)
- 脱兎の勢い(だっとのいきおい)
「七」を含むことわざ
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 朝起きは七つの徳(あさおきはななつのとく)
- 朝茶は七里帰っても飲め(あさちゃはしちりかえってものめ)
- 色の白いは七難隠す(いろのしろいはしちなんかくす)
- 浮き沈み七度(うきしずみななたび)
- 浮世は衣装七分(うきよはいしょうしちぶ)
- 兎も七日なぶれば噛みつく(うさぎもなぬかなぶればかみつく)
- 男心と秋の空は一夜に七度変わる(おとこごころとあきのそらはいちやにななたびかわる)
- 男は敷居を跨げば七人の敵あり(おとこはしきいをまたげばしちにんのてきあり)
「度」を含むことわざ
- 危ない橋も一度は渡れ(あぶないはしもいちどはわたれ)
- 一度あることは二度ある(いちどあることはにどある)
- 一度死ねば二度死なぬ(いちどしねばにどしなぬ)
- 一度はままよ二度はよし(いちどはままよにどはよし)
- 一度焼けた山は二度は焼けぬ(いちどやけたやまはにどはやけぬ)
- 韋編三度絶つ(いへんみたびたつ)
- 浮き沈み七度(うきしずみななたび)
- 旨い事は二度考えよ(うまいことはにどかんがえよ)
- 縁なき衆生は度し難し(えんなきしゅじょうはどしがたし)
「熊」を含むことわざ
- 蟻の熊野参り(ありのくまのまいり)
- 伊勢へ七度、熊野へ三度(いせへななたび、くまのへみたび)
- 熊野松風は米の飯(ゆやまつかぜはこめのめし)
- 欲の熊鷹、股裂くる(よくのくまたか、またさくる)
「野」を含むことわざ
- あだし野の露、鳥辺野の煙(あだしののつゆ、とりべののけむり)
- 仇野の露、鳥辺野の煙(あだしののつゆ、とりべののけむり)
- 仇野の露、鳥部野の煙(あだしののつゆ、とりべののけむり)
- 徒野の露、鳥辺野の煙(あだしののつゆ、とりべののけむり)
- 徒野の露、鳥部野の煙(あだしののつゆ、とりべののけむり)
- 後は野となれ山となれ(あとはのとなれやまとなれ)
- 蟻の熊野参り(ありのくまのまいり)
- 言うだけ野暮(いうだけやぼ)
- 視野が広い(しやがひろい)



