危ない橋も一度は渡れとは
危ない橋も一度は渡れ
あぶないはしもいちどはわたれ
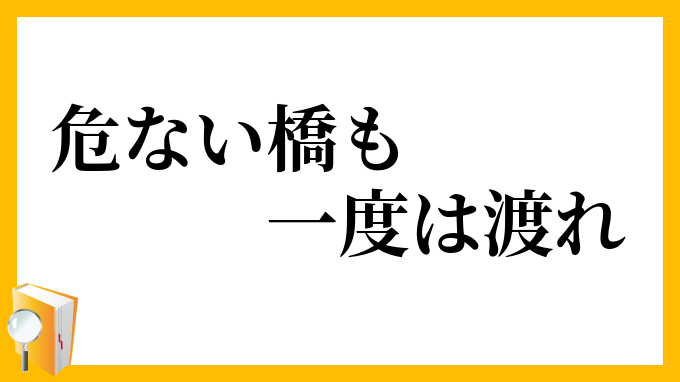
| 言葉 | 危ない橋も一度は渡れ |
|---|---|
| 読み方 | あぶないはしもいちどはわたれ |
| 意味 | 安全な方策ばかりとっていたのでは、成功することはできない。時には危険を冒してやってみるのも必要だということ。 |
| 場面用途 | 危険 |
| 類句 | 虎穴に入らずんば虎子を得ず(こけつにいらずんばこじをえず) |
| 危ない所に上がらねば熟柿は食えぬ | |
| 使用語彙 | 危ない / 橋 / 一度 |
| 使用漢字 | 危 / 橋 / 一 / 度 / 渡 |
「危」を含むことわざ
- 危ないことは怪我のうち(あぶないことはけがのうち)
- 危ない橋を渡る(あぶないはしをわたる)
- 危うきこと虎の尾を踏むが如し(あやうきこととらのおをふむがごとし)
- 危うきこと累卵の如し(あやうきことるいらんのごとし)
- 安に居て危を思う(あんにいてきをおもう)
- 危急存亡の秋(ききゅうそんぼうのとき)
- 危殆に瀕する(きたいにひんする)
- 首が危ない(くびがあぶない)
- 君子、危うきに近寄らず(くんし、あやうきにちかよらず)
「橋」を含むことわざ
- 危ない橋を渡る(あぶないはしをわたる)
- 石橋を叩いて渡る(いしばしをたたいてわたる)
- 江戸は八百八町、大坂は八百八橋(えどははっぴゃくやちょう、おおさかははっぴゃくやばし)
- 橋頭堡(きょうとうほ)
- 橋が無ければ渡られぬ(はしがなければわたられぬ)
- 夢の浮橋(ゆめのうきはし)
「一」を含むことわざ
- 悪は一旦の事なり(あくはいったんのことなり)
- 欠伸を一緒にすれば三日従兄弟(あくびをいっしょにすればみっかいとこ)
- 朝顔の花一時(あさがおのはなひととき)
- 朝の一時は晩の二時に当たる(あさのひとときはばんのふたときにあたる)
- 薊の花も一盛り(あざみのはなもひとさかり)
- あの世の千日、この世の一日(あのよのせんにち、このよのいちにち)
- 粟一粒は汗一粒(あわひとつぶはあせひとつぶ)
- 板子一枚下は地獄(いたごいちまいしたはじごく)
- 一瓜実に二丸顔(いちうりざねににまるがお)
「度」を含むことわざ
- 秋の空は七度半変わる(あきのそらはななたびはんかわる)
- 伊勢へ七度、熊野へ三度(いせへななたび、くまのへみたび)
- 一度あることは二度ある(いちどあることはにどある)
- 一度死ねば二度死なぬ(いちどしねばにどしなぬ)
- 一度はままよ二度はよし(いちどはままよにどはよし)
- 一度焼けた山は二度は焼けぬ(いちどやけたやまはにどはやけぬ)
- 韋編三度絶つ(いへんみたびたつ)
- 浮き沈み七度(うきしずみななたび)
- 旨い事は二度考えよ(うまいことはにどかんがえよ)



