君子、危うきに近寄らずとは
君子、危うきに近寄らず
くんし、あやうきにちかよらず
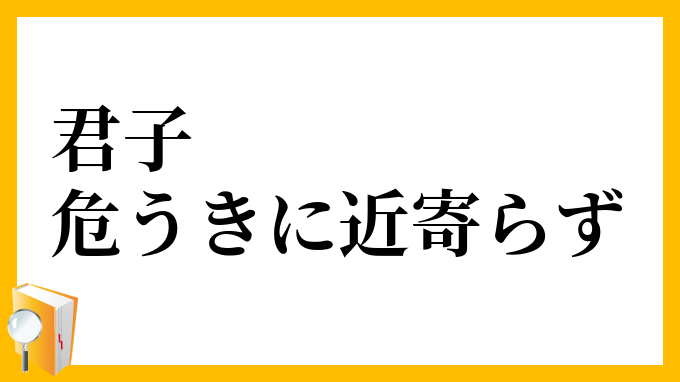
| 言葉 | 君子、危うきに近寄らず |
|---|---|
| 読み方 | くんし、あやうきにちかよらず |
| 意味 | 徳のある人は自分を大事にするので、危険なことには決して近づかないということ。 |
| 場面用途 | 危険 |
| 類句 | 危ないことは怪我のうち(あぶないことはけがのうち) |
| 使用語彙 | 君子 |
| 使用漢字 | 君 / 子 / 危 / 近 / 寄 |
「君」を含むことわざ
- 一天万乗の君(いってんばんじょうのきみ)
- 王は君臨すれども統治せず(おうはくんりんすれどもとうちせず)
- 君、君たらずと雖も臣は臣たらざるべからず(きみ、きみたらずといえどもしんはしんたらざるべからず)
- 君、辱めらるれば臣死す(きみ、はずかしめらるればしんしす)
- 君を思うも身を思う(きみをおもうもみをおもう)
- 君子に三戒あり(くんしにさんかいあり)
- 君子に三楽あり(くんしにさんらくあり)
- 君子の過ちは日月の食のごとし(くんしのあやまちはじつげつのしょくのごとし)
- 君子の三楽(くんしのさんらく)
「子」を含むことわざ
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 赤子の腕を捩じる(あかごのうでをねじる)
- 赤子の手をねじる(あかごのてをねじる)
- 赤子の手を捩じるよう(あかごのてをねじるよう)
- 赤子の手を捻る(あかごのてをひねる)
- 赤子の手を捻るよう(あかごのてをひねるよう)
- 赤子は泣き泣き育つ(あかごはなきなきそだつ)
- 赤子を裸にしたよう(あかごをはだかにしたよう)
- 秋茄子は嫁に食わすな(あきなすはよめにくわすな)
- 秋の日と娘の子はくれぬようでくれる(あきのひとむすめのこはくれぬようでくれる)
「危」を含むことわざ
- 危ないことは怪我のうち(あぶないことはけがのうち)
- 危ない橋も一度は渡れ(あぶないはしもいちどはわたれ)
- 危ない橋を渡る(あぶないはしをわたる)
- 危うきこと虎の尾を踏むが如し(あやうきこととらのおをふむがごとし)
- 危うきこと累卵の如し(あやうきことるいらんのごとし)
- 安に居て危を思う(あんにいてきをおもう)
- 危急存亡の秋(ききゅうそんぼうのとき)
- 危殆に瀕する(きたいにひんする)
- 首が危ない(くびがあぶない)
「近」を含むことわざ
- 遠水、近火を救わず(えんすい、きんかをすくわず)
- 遠慮なければ近憂あり(えんりょなければきんゆうあり)
- 近江泥棒伊勢乞食(おうみどろぼういせこじき)
- 学を好むは、知に近し(がくをこのむは、ちにちかし)
- 北に近ければ南に遠い(きたにちかければみなみにとおい)
- 剛毅朴訥、仁に近し(ごうきぼくとつ、じんにちかし)
- 酒と朝寝は貧乏の近道(さけとあさねはびんぼうのちかみち)
- 性相近し、習い相遠し(せいあいちかし、ならいあいとおし)
- 近くて見えぬは睫(ちかくてみえぬはまつげ)



