大水に飲み水なしとは
大水に飲み水なし
おおみずにのみみずなし
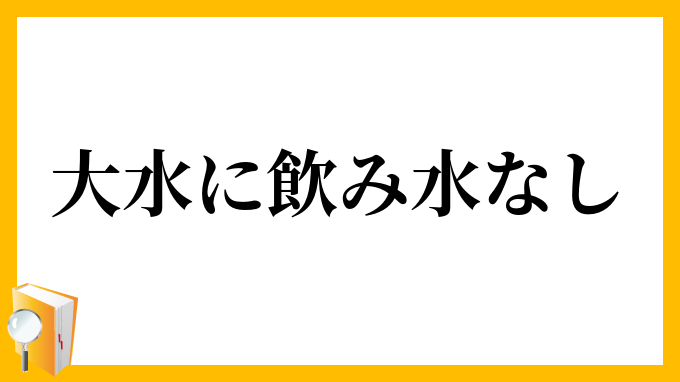
| 言葉 | 大水に飲み水なし |
|---|---|
| 読み方 | おおみずにのみみずなし |
| 意味 | 大勢の人がいても、本当に役に立つ人は少ないということ。
洪水の水はたくさんあっても、飲み水としては使えないとの意から。 「火事場に煙草の火なく大水に飲み水なし」ともいう。 |
| 異形 | 火事場に煙草の火なく大水に飲み水なし(かじばにたばこのひなくおおみずにのみみずなし) |
| 使用語彙 | 大水 |
| 使用漢字 | 大 / 水 / 飲 / 火 / 事 / 場 / 煙 / 草 |
「大」を含むことわざ
- 阿保の大食い(あほのおおぐい)
- 諍いをしいしい腹を大きくし(いさかいをしいしいはらをおおきくし)
- 一木いずくんぞ能く大廈を支えん(いちぼくいずくんぞよくたいかをささえん)
- 一木大廈の崩るるを支うる能わず(いちぼくたいかのくずるるをささうるあたわず)
- 井の中の蛙大海を知らず(いのなかのかわずたいかいをしらず)
- 上を下への大騒ぎ(うえをしたへのおおさわぎ)
- 独活の大木(うどのたいぼく)
- 独活の大木柱にならぬ(うどのたいぼくはしらにならぬ)
- 瓜の皮は大名に剝かせよ、柿の皮は乞食に剝かせよ(うりのかわはだいみょうにむかせよ、かきのかわはこじきにむかせよ)
- 江戸っ子の往き大名還り乞食(えどっこのゆきだいみょうかえりこじき)
「水」を含むことわざ
- 明日食う塩辛に今日から水を飲む(あすくうしおからにきょうからみずをのむ)
- 汗水垂らす(あせみずたらす)
- 汗水流す(あせみずながす)
- 汗水を流す(あせみずをながす)
- 頭から水を浴びたよう(あたまからみずをあびたよう)
- 頭から水を掛けられたよう(あたまからみずをかけられたよう)
- 魚心あれば水心(うおごころあればみずごころ)
- 魚と水(うおとみず)
- 魚の水に離れたよう(うおのみずにはなれたよう)
- 魚の水を得たよう(うおのみずをえたよう)
「飲」を含むことわざ
- 朝酒は門田を売っても飲め(あさざけはかどたをうってものめ)
- 朝茶は七里帰っても飲め(あさちゃはしちりかえってものめ)
- 明日食う塩辛に今日から水を飲む(あすくうしおからにきょうからみずをのむ)
- 一箪の食、一瓢の飲(いったんのし、いっぴょうのいん)
- 一杯は人酒を飲む、二杯は酒酒を飲む、三杯は酒人を飲む(いっぱいはひとさけをのむ、にはいはさけさけをのむ、さんばいはさけひとをのむ)
- 馬を水辺につれていけても水を飲ませることはできない(うまをみずべにつれていけてもみずをのませることはできない)
- 恨みを飲む(うらみをのむ)
- 渇しても盗泉の水を飲まず(かっしてもとうせんのみずをのまず)
「火」を含むことわざ
- 秋葉山から火事(あきばさんからかじ)
- 足下に火が付く(あしもとにひがつく)
- 足元に火が付く(あしもとにひがつく)
- 熱火子にかく(あつびこにかく)
- 熱火子に払う(あつびこにはらう)
- 油紙に火が付いたよう(あぶらがみにひがついたよう)
- 油紙に火の付いたよう(あぶらがみにひのついたよう)
- 油紙へ火の付いたよう(あぶらがみへひのついたよう)
- 暗夜に灯火を失う(あんやにともしびをうしなう)
- 家に女房なきは火のない炉のごとし(いえににょうぼうなきはひのないろのごとし)
「事」を含むことわざ
- 秋葉山から火事(あきばさんからかじ)
- 悪事、千里を走る(あくじ、せんりをはしる)
- 悪事、身にかえる(あくじ、みにかえる)
- 悪事、千里を行く(あくじせんりをいく)
- 悪は一旦の事なり(あくはいったんのことなり)
- 明日の事は明日案じよ(あすのことはあすあんじよ)
- 明日の事を言えば鬼が笑う(あすのことをいえばおにがわらう)
- 当て事と畚褌は先から外れる(あてことともっこふんどしはさきからはずれる)
- 当て事と越中褌は向こうから外れる(あてごととえっちゅうふんどしはむこうからはずれる)
- 当て事は向こうから外れる(あてごとはむこうからはずれる)
「場」を含むことわざ
- 足の踏み場もない(あしのふみばもない)
- 足場を失う(あしばをうしなう)
- 足場を固める(あしばをかためる)
- 一場の春夢(いちじょうのしゅんむ)
- 火事場の馬鹿力(かじばのばかぢから)
- 乞食も場所(こじきもばしょ)
- 修羅場(しゅらじょう)
- 修羅場(しゅらじょう)
- 尻の持って行き場がない(しりのもっていきばがない)
「煙」を含むことわざ
- あだし野の露、鳥辺野の煙(あだしののつゆ、とりべののけむり)
- 仇野の露、鳥辺野の煙(あだしののつゆ、とりべののけむり)
- 仇野の露、鳥部野の煙(あだしののつゆ、とりべののけむり)
- 徒野の露、鳥辺野の煙(あだしののつゆ、とりべののけむり)
- 徒野の露、鳥部野の煙(あだしののつゆ、とりべののけむり)
- 油を以って油煙を落とす(あぶらをもってゆえんをおとす)
- 煙霞の痼疾(えんかのこしつ)
- 煙霞の癖(えんかのへき)
- 煙幕を張る(えんまくをはる)



