諍いをしいしい腹を大きくしとは
諍いをしいしい腹を大きくし
いさかいをしいしいはらをおおきくし
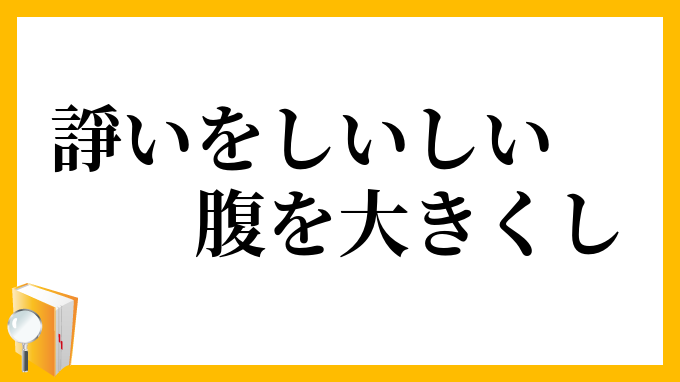
| 言葉 | 諍いをしいしい腹を大きくし |
|---|---|
| 読み方 | いさかいをしいしいはらをおおきくし |
| 意味 | 喧嘩ばかりしている夫婦なのに、子どもだけはよくできるということ。 |
| 場面用途 | 夫婦 / 親族 |
| 使用語彙 | 諍い |
| 使用漢字 | 諍 / 腹 / 大 |
「諍」を含むことわざ
- 諍い果てての乳切り木(いさかいはててのちぎりぎ)
- 諍い果てての千切り木(いさかいはててのちぎりぎ)
- 諍いをしいしい腹を大きくし(いさかいをしいしいはらをおおきくし)
「腹」を含むことわざ
- 後腹が病める(あとばらがやめる)
- 痛くもない腹を探られる(いたくもないはらをさぐられる)
- 言わねば腹ふくる(いわねばはらふくる)
- 海魚腹から川魚背から(うみうおはらからかわうおせから)
- 思うこと言わねば腹ふくる(おもうこといわねばはらふくる)
- 恩の腹は切らねど情けの腹は切る(おんのはらはきらねどなさけのはらはきる)
- 片腹痛い(かたはらいたい)
- 聞けば聞き腹(きけばききばら)
- 魚腹に葬らる(ぎょふくにほうむらる)



