大廈の倒れんとするは一木の支うる所に非ずとは
大廈の倒れんとするは一木の支うる所に非ず
たいかのたおれんとするはいちぼくのささうるところにあらず
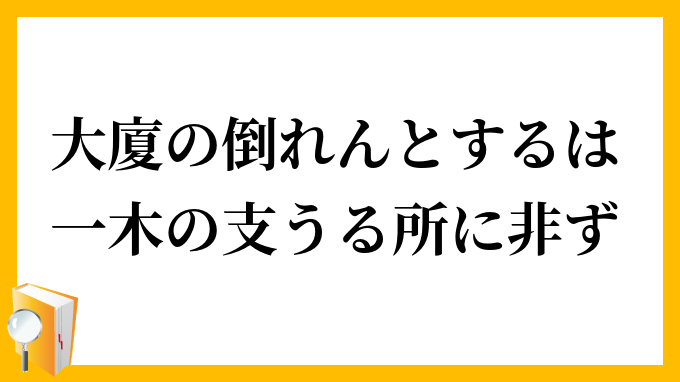
| 言葉 | 大廈の倒れんとするは一木の支うる所に非ず |
|---|---|
| 読み方 | たいかのたおれんとするはいちぼくのささうるところにあらず |
| 意味 | 大きな勢力の危機は、一人の力だけではどうすることもできないということ。
「大廈」は、大きな建物のこと。 大きな建物が倒れかけているのを、一本の木だけで支えることはできないとの意から。 「倒れんとする」は「顚れんとする」とも書く。 「一木大廈の崩るるを支うる能わず」「一木いずくんぞ能く大廈を支えん」ともいう。 |
| 出典 | 『文中子』事君 |
| 異形 | 大廈の顚れんとするは一木の支うる所に非ず(たいかのたおれんとするはいちぼくのささうるところにあらず) |
| 一木大廈の崩るるを支うる能わず(いちぼくたいかのくずるるをささうるあたわず) | |
| 一木いずくんぞ能く大廈を支えん(いちぼくいずくんぞよくたいかをささえん) | |
| 使用語彙 | 大廈 / とする / 非ず |
| 使用漢字 | 大 / 廈 / 倒 / 一 / 木 / 支 / 所 / 非 / 顚 / 崩 / 能 |
「大」を含むことわざ
- 諍いをしいしい腹を大きくし(いさかいをしいしいはらをおおきくし)
- 井の中の蛙大海を知らず(いのなかのかわずたいかいをしらず)
- 上を下への大騒ぎ(うえをしたへのおおさわぎ)
- 独活の大木(うどのたいぼく)
- 瓜の皮は大名に剝かせよ、柿の皮は乞食に剝かせよ(うりのかわはだいみょうにむかせよ、かきのかわはこじきにむかせよ)
- 江戸っ子の往き大名還り乞食(えどっこのゆきだいみょうかえりこじき)
- 江戸は八百八町、大坂は八百八橋(えどははっぴゃくやちょう、おおさかははっぴゃくやばし)
- お家の一大事(おいえのいちだいじ)
- 大当たりを取る(おおあたりをとる)
- 大嘘はつくとも小嘘はつくな(おおうそはつくともこうそはつくな)
「廈」を含むことわざ
- 大廈の倒れんとするは一木の支うる所に非ず(たいかのたおれんとするはいちぼくのささうるところにあらず)
「倒」を含むことわざ
- 一辺倒(いっぺんとう)
- 大阪の食い倒れ(おおさかのくいだおれ)
- 親方思いの主倒し(おやかたおもいのしゅたおし)
- 看板倒れ(かんばんだおれ)
- 京の着倒れ、大坂の食い倒れ(きょうのきだおれ、おおさかのくいだおれ)
- 狂瀾を既倒に廻らす(きょうらんをきとうにめぐらす)
- 食うに倒れず病むに倒れる(くうにたおれずやむにたおれる)
- 孔子の倒れ(くじのたおれ)
- 恋の山には孔子の倒れ(こいのやまにはくじのたおれ)
- 甲張り強くして家押し倒す(こうばりつよくしていえおしたおす)
「一」を含むことわざ
- 悪は一旦の事なり(あくはいったんのことなり)
- 欠伸を一緒にすれば三日従兄弟(あくびをいっしょにすればみっかいとこ)
- 朝顔の花一時(あさがおのはなひととき)
- 朝の一時は晩の二時に当たる(あさのひとときはばんのふたときにあたる)
- 薊の花も一盛り(あざみのはなもひとさかり)
- あの世の千日、この世の一日(あのよのせんにち、このよのいちにち)
- 危ない橋も一度は渡れ(あぶないはしもいちどはわたれ)
- 粟一粒は汗一粒(あわひとつぶはあせひとつぶ)
- 板子一枚下は地獄(いたごいちまいしたはじごく)
- 一瓜実に二丸顔(いちうりざねににまるがお)
「木」を含むことわざ
- 足を擂り粉木にする(あしをすりこぎにする)
- 諍い果てての乳切り木(いさかいはててのちぎりぎ)
- 石が流れて木の葉が沈む(いしがながれてこのはがしずむ)
- 移木の信(いぼくのしん)
- 植木屋の庭できが多い(うえきやのにわできがおおい)
- 魚の木に登るが如し(うおのきにのぼるがごとし)
- 独活の大木(うどのたいぼく)
- 埋もれ木に花咲く(うもれぎにはなさく)
- 榎の実は生らば生れ木は椋の木(えのみはならばなれきはむくのき)
- 老い木に花咲く(おいきにはなさく)
「支」を含むことわざ
- 支証の出し遅れ(ししょうのだしおくれ)
- 大廈の倒れんとするは一木の支うる所に非ず(たいかのたおれんとするはいちぼくのささうるところにあらず)
「所」を含むことわざ
- 余す所なく(あますところなく)
- 過ちは好む所にあり(あやまちはこのむところにあり)
- 意志のある所には道がある(いしのあるところにはみちがある)
- 痛い所をつく(いたいところをつく)
- 意のある所(いのあるところ)
- 柄のない所に柄をすげる(えのないところにえをすげる)
- 選ぶ所がない(えらぶところがない)
- 大所の犬になるとも小所の犬になるな(おおどころのいぬになるともこどころのいぬになるな)
- 己の欲する所を人に施せ(おのれのほっするところをひとにほどこせ)
- 己の欲せざる所は人に施すこと勿れ(おのれのほっせざるところはひとにほどこすことなかれ)
「非」を含むことわざ
- 神は非礼を受けず(かみはひれいをうけず)
- 千金の裘は一狐の腋に非ず(せんきんのきゅうはいっこのえきにあらず)
- 是が非でも(ぜがひでも)
- 是非に及ばず(ぜひにおよばず)
- 是非は道によって賢し(ぜひはみちによってかしこし)
- 是非も無い(ぜひもない)
- 天勾践を空しゅうすること莫れ、時に范蠡なきにしも非ず(てんこうせんをむなしゅうすることなかれ、ときにはんれいなきにしもあらず)
- 天道、是か非か(てんどう、ぜかひか)
- 無きにしも非ず(なきにしもあらず)
「顚」を含むことわざ
- 大廈の顚れんとするは一木の支うる所に非ず(たいかのたおれんとするはいちぼくのささうるところにあらず)
「崩」を含むことわざ
- 蟻の穴から堤も崩れる(ありのあなからつつみもくずれる)
- 一木大廈の崩るるを支うる能わず(いちぼくたいかのくずるるをささうるあたわず)
- 玉山崩る(ぎょくざんくずる)
- 相好を崩す(そうごうをくずす)
- 膝を崩す(ひざをくずす)
- 身を持ち崩す(みをもちくずす)



