効能書きの読めぬ所に効能ありとは
効能書きの読めぬ所に効能あり
こうのうがきのよめぬところにこうのうあり
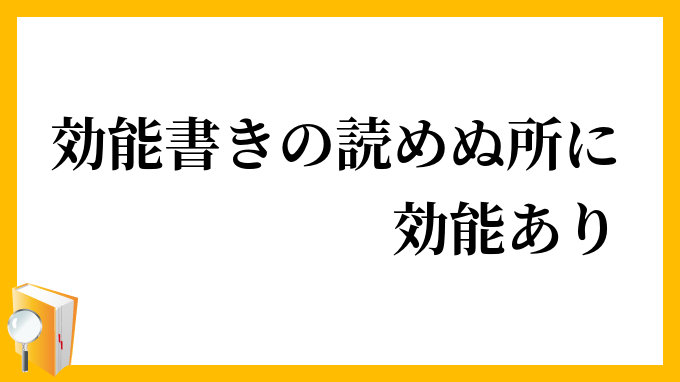
| 言葉 | 効能書きの読めぬ所に効能あり |
|---|---|
| 読み方 | こうのうがきのよめぬところにこうのうあり |
| 意味 | 薬の効能書きは難解だが、それがかえって効きそうな気にさせる。わかりにくいものほど、有難みがあるということのたとえ。また、効能書きの難解さへの皮肉にいう。 |
| 類句 | 能書きの読めぬ所に効き目あり(のうがきのよめぬところにききめあり) |
| 使用語彙 | 効能 |
| 使用漢字 | 効 / 能 / 書 / 読 / 所 |
「効」を含むことわざ
- 医者の自脈効き目なし(いしゃのじみゃくききめなし)
- 得手勝手は向こうには効かない(えてかってはむこうにはきかない)
- 薬が効く(くすりがきく)
- 薬は毒ほど効かぬ(くすりはどくほどきかぬ)
- 潰しが効く(つぶしがきく)
- 能書きの読めぬ所に効き目あり(のうがきのよめぬところにききめあり)
- 薬石効なし(やくせきこうなし)
「能」を含むことわざ
- 一木いずくんぞ能く大廈を支えん(いちぼくいずくんぞよくたいかをささえん)
- 一木大廈の崩るるを支うる能わず(いちぼくたいかのくずるるをささうるあたわず)
- 駟馬も追う能ず(しばもおうあたわず)
- 敵は本能寺にあり(てきはほんのうじにあり)
- 能ある鷹は爪を隠す(のうあるたかはつめをかくす)
- 能書きの読めぬ所に効き目あり(のうがきのよめぬところにききめあり)
- 能書きを垂れる(のうがきをたれる)
- 能書きを並べる(のうがきをならべる)
- 能書筆を択ばず(のうしょふでをえらばず)
「書」を含むことわざ
- 頭搔くか字を書くか(あたまかくかじをかくか)
- 急ぎの文は静かに書け(いそぎのふみはしずかにかけ)
- 売家と唐様で書く三代目(うりいえとからようでかくさんだいめ)
- 書いた物が物を言う(かいたものがものをいう)
- 顔に書いてある(かおにかいてある)
- 家書万金に抵る(かしょばんきんにあたる)
- 雁書(がんしょ)
- 尽く書を信ずれば書なきに如かず(ことごとくしょをしんずればしょなきにしかず)
- 尽く書を信ずれば則ち書無きに如かず(ことごとくしょをしんずればすなわちしょなきにしかず)
「読」を含むことわざ
- 顔色を読む(かおいろをよむ)
- 行間を読む(ぎょうかんをよむ)
- 先を読む(さきをよむ)
- 鯖を読む(さばをよむ)
- 十遍読むより一遍写せ(じっぺんよむよりいっぺんうつせ)
- 十読は一写に如かず(じゅうどくはいちしゃにしかず)
- 堂が歪んで経が読めぬ(どうがゆがんできょうがよめぬ)
- 読書百遍、意、自ずから通ず(どくしょひゃっぺん、い、おのずからつうず)
- 読書百遍、義、自ずから見る(どくしょひゃっぺん、ぎ、おのずからあらわる)



