井の中の蛙大海を知らずとは
井の中の蛙大海を知らず
いのなかのかわずたいかいをしらず
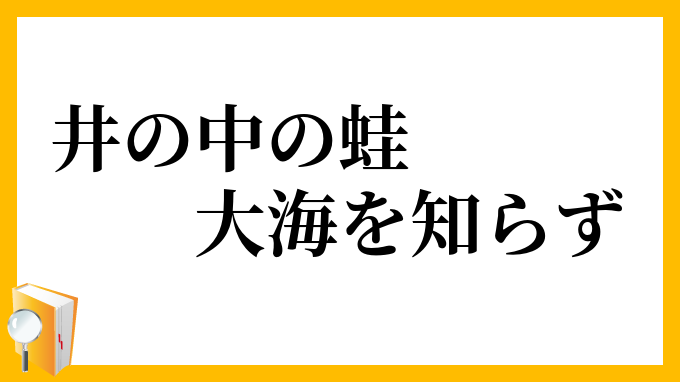
| 言葉 | 井の中の蛙大海を知らず |
|---|---|
| 読み方 | いのなかのかわずたいかいをしらず |
| 意味 | 他に広い世界があることを知らずに、自分の周りの狭い見識や知識にとらわれてこと。
小さな井戸に住んでいる蛙は、井戸の外の世界に大きな海があることなど知らないとの意から。 「坎井の蛙」「井底の蛙」「井蛙」などともいう。 |
| 異形 | 坎井の蛙(かんせいのあ) |
| 井底の蛙(せいていのあ) | |
| 井蛙(せいあ) | |
| 類句 | 夏の虫、氷を笑う(なつのむし、こおりをわらう) |
| 使用語彙 | 井 / 中 / 蛙 |
| 使用漢字 | 井 / 中 / 蛙 / 大 / 海 / 知 / 坎 / 底 |
「井」を含むことわざ
- 渇に臨みて井を穿つ(かつにのぞみていをうがつ)
- 渇に臨みて井を穿つ(かつにのぞみてせいをうがつ)
- 市井の徒(しせいのと)
- 天井から目薬(てんじょうからめぐすり)
- 天井知らず(てんじょうしらず)
- 天井を打つ(てんじょうをうつ )
「中」を含むことわざ
- 麻の中の蓬(あさのなかのよもぎ)
- 中らずと雖も遠からず(あたらずといえどもとおからず)
- 当て事と越中褌は向こうから外れる(あてごととえっちゅうふんどしはむこうからはずれる)
- 後先息子に中娘(あとさきむすこになかむすめ)
- 石の物言う世の中(いしのものいうよのなか)
- 意中の人(いちゅうのひと)
- 魚の釜中に遊ぶが如し(うおのふちゅうにあそぶがごとし)
- 海中より盃中に溺死する者多し(かいちゅうよりはいちゅうにできしするものおおし)
- 渦中に巻き込まれる(かちゅうにまきこまれる)
「蛙」を含むことわざ
- 越王、怒蛙に式す(えつおう、どあにしょくす)
- 蛙が飛べば石亀も地団駄(かえるがとべばいしがめもじだんだ)
- 蛙の子は蛙(かえるのこはかえる)
- 蛙の面に水(かえるのつらにみず)
- 蛙の目借り時(かえるのめかりどき)
- 蛙は口から呑まるる(かえるはくちからのまるる)
- 蛙は口ゆえ蛇に呑まるる(かえるはくちゆえへびにのまるる)
「大」を含むことわざ
- 阿保の大食い(あほのおおぐい)
- 諍いをしいしい腹を大きくし(いさかいをしいしいはらをおおきくし)
- 一木いずくんぞ能く大廈を支えん(いちぼくいずくんぞよくたいかをささえん)
- 一木大廈の崩るるを支うる能わず(いちぼくたいかのくずるるをささうるあたわず)
- 上を下への大騒ぎ(うえをしたへのおおさわぎ)
- 独活の大木(うどのたいぼく)
- 独活の大木柱にならぬ(うどのたいぼくはしらにならぬ)
- 瓜の皮は大名に剝かせよ、柿の皮は乞食に剝かせよ(うりのかわはだいみょうにむかせよ、かきのかわはこじきにむかせよ)
- 江戸っ子の往き大名還り乞食(えどっこのゆきだいみょうかえりこじき)
「海」を含むことわざ
- 海驢の番(あしかのばん)
- 海魚腹から川魚背から(うみうおはらからかわうおせから)
- 海に千年山に千年(うみにせんねんやまにせんねん)
- 海の事は漁師に問え(うみのことはりょうしにとえ)
- 海の物とも山の物ともつかぬ(うみのものともやまのものともつかぬ)
- 海老で鯛を釣る(えびでたいをつる)
- 貝殻で海を量る(かいがらでうみをはかる)
- 海賊が山賊の罪をあげる(かいぞくがさんぞくのつみをあげる)
- 海中より盃中に溺死する者多し(かいちゅうよりはいちゅうにできしするものおおし)
「知」を含むことわざ
- 相対のことはこちゃ知らぬ(あいたいのことはこちゃしらぬ)
- 明日知らぬ世(あすしらぬよ)
- 過ちを観て斯に仁を知る(あやまちをみてここにじんをしる)
- 過ちを観て仁を知る(あやまちをみてじんをしる)
- 息の臭きは主知らず(いきのくさきはぬししらず)
- いざ知らず(いざしらず)
- 衣食足りて栄辱を知る(いしょくたりてえいじょくをしる)
- 衣食足りて礼節を知る(いしょくたりてれいせつをしる)
- 衣食足れば則ち栄辱を知る(いしょくたればすなわちえいじょくをしる)
- 一文惜しみの百知らず(いちもんおしみのひゃくしらず)
「坎」を含むことわざ
- 坎井の蛙(かんせいのあ)



