管を以て天を窺うとは
管を以て天を窺う
くだをもっててんをうかがう
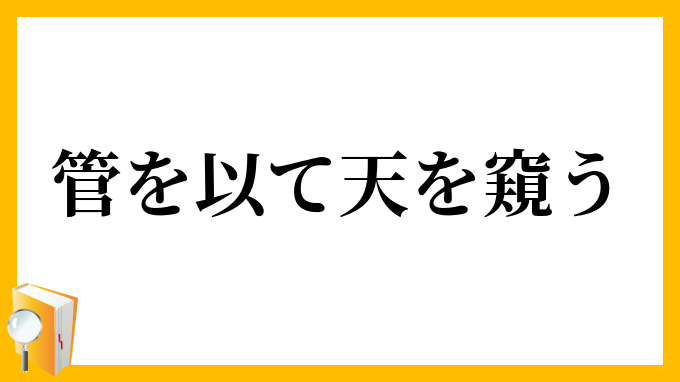
| 言葉 | 管を以て天を窺う |
|---|---|
| 読み方 | くだをもっててんをうかがう |
| 意味 | 自分の狭い見識で、大きな問題について勝手に判断することたとえ。
「管」は「かん」とも読む。 「管を以て大空を測る」「管の穴から天を覗く」「針の穴から天を覗く」ともいう。 |
| 出典 | 『荘子』秋水 |
| 異形 | 管を以て大空を測る(くだをもっておおぞらをはかる) |
| 管の穴から天を覗く(くだのあなからてんをのぞく) | |
| 針の穴から天を覗く(はりのあなからてんをのぞく) | |
| 類句 | 葦の髄から天井を覗く(よしのずいからてんじょうをのぞく) |
| 小知を以て大道を窺う | |
| 貝殻で海を量る(かいがらでうみをはかる) | |
| 大海を耳搔きで測る(たいかいをみみかきではかる) | |
| 使用語彙 | 窺う / 大空 |
| 使用漢字 | 管 / 以 / 天 / 窺 / 大 / 空 / 測 / 穴 / 覗 / 針 |
「管」を含むことわざ
- 管鮑の交わり(かんぽうのまじわり)
- 管の穴から天を覗く(くだのあなからてんをのぞく)
- 管を巻く(くだをまく)
- 管を以て大空を測る(くだをもっておおぞらをはかる)
- 管を以て天を窺う(くだをもっててんをうかがう)
「以」を含むことわざ
- 油を以って油煙を落とす(あぶらをもってゆえんをおとす)
- 佚を以って労を待つ(いつをもってろうをまつ)
- 夷を以て夷を制す(いをもっていをせいす)
- 怨みに報ゆるに徳を以てす(うらみにむくゆるにとくをもってす)
- 己を以て人を量る(おのれをもってひとをはかる)
- 恩を以て怨みに報ず(おんをもってうらみにほうず)
- 薫は香を以て自ら焼く(くんはこうをもってみずからやく)
- コンマ以下(こんまいか)
「天」を含むことわざ
- 敢えて天下の先とならず(あえててんかのさきとならず)
- 仰いで天に愧じず(あおいでてんにはじず)
- 頭の天辺から足の爪先まで(あたまのてっぺんからあしのつまさきまで)
- 天の邪鬼(あまのじゃく)
- 雨の降る日は天気が悪い(あめのふるひはてんきがわるい)
- 蟻の思いも天に届く(ありのおもいもてんにとどく)
- 蟻の思いも天に昇る(ありのおもいもてんにのぼる)
- 意気天を衝く(いきてんをつく)
- 韋駄天走り(いだてんばしり)
- 一念、天に通ず(いちねん、てんにつうず)
「窺」を含むことわざ
- 顔色を窺う(かおいろをうかがう)
- 管を以て天を窺う(くだをもっててんをうかがう)
- 寝息を窺う(ねいきをうかがう)
- 猫の額にある物を鼠が窺う(ねこのひたいにあるものをねずみがうかがう)
- 鼻息を窺う(はないきをうかがう)
「大」を含むことわざ
- 阿保の大食い(あほのおおぐい)
- 諍いをしいしい腹を大きくし(いさかいをしいしいはらをおおきくし)
- 一木いずくんぞ能く大廈を支えん(いちぼくいずくんぞよくたいかをささえん)
- 一木大廈の崩るるを支うる能わず(いちぼくたいかのくずるるをささうるあたわず)
- 井の中の蛙大海を知らず(いのなかのかわずたいかいをしらず)
- 上を下への大騒ぎ(うえをしたへのおおさわぎ)
- 独活の大木(うどのたいぼく)
- 独活の大木柱にならぬ(うどのたいぼくはしらにならぬ)
- 瓜の皮は大名に剝かせよ、柿の皮は乞食に剝かせよ(うりのかわはだいみょうにむかせよ、かきのかわはこじきにむかせよ)
- 江戸っ子の往き大名還り乞食(えどっこのゆきだいみょうかえりこじき)
「空」を含むことわざ
- 空樽は音が高い(あきだるはおとがたかい)
- 空き家で声嗄らす(あきやでこえからす)
- 空き家の雪隠(あきやのせっちん)
- 商人の空値(あきんどのそらね)
- 穴が空く(あながあく)
- 生きた空もない(いきたそらもない)
- えせ者の空笑い(えせもののそらわらい)
- 男心と秋の空(おとこごころとあきのそら)
- 男心と秋の空は一夜に七度変わる(おとこごころとあきのそらはいちやにななたびかわる)
- 女心と秋の空(おんなごころとあきのそら)
「測」を含むことわざ
- 管を以て大空を測る(くだをもっておおぞらをはかる)
- 大海を耳搔きで測る(たいかいをみみかきではかる)
- 測り難きは人心(はかりがたきはひとごころ)
「穴」を含むことわざ
- 穴が空く(あながあく)
- 穴が開く(あながあく)
- 穴があったら入りたい(あながあったらはいりたい)
- 穴の開くほど(あなのあくほど)
- 穴の開くほど見る(あなのあくほどみる)
- 穴の貉を値段する(あなのむじなをねだんする)
- 穴をあける(あなをあける)
- 穴を埋める(あなをうめる)
- 穴を掘って言い入れる(あなをほっていいいれる)
- 蟻の穴から堤も崩れる(ありのあなからつつみもくずれる)
「覗」を含むことわざ
- 網なくて淵を覗くな(あみなくてふちをのぞくな)
- 楽屋裏を覗く(がくやうらをのぞく)
- 管の穴から天を覗く(くだのあなからてんをのぞく)
- 針の穴から天を覗く(はりのあなからてんをのぞく)
- 葦の髄から天井を覗く(よしのずいからてんじょうをのぞく)



