江戸っ子の往き大名還り乞食とは
江戸っ子の往き大名還り乞食
えどっこのゆきだいみょうかえりこじき
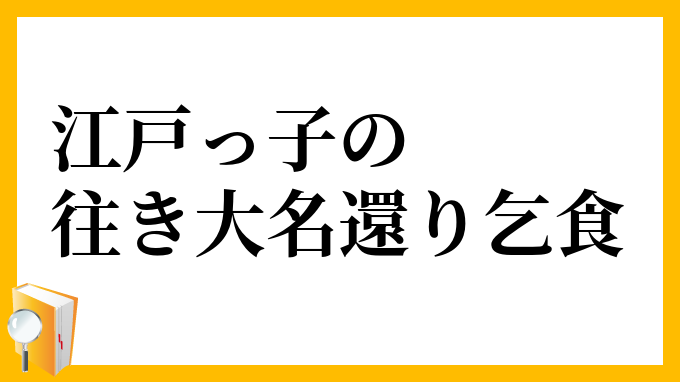
| 言葉 | 江戸っ子の往き大名還り乞食 |
|---|---|
| 読み方 | えどっこのゆきだいみょうかえりこじき |
| 意味 | 江戸っ子は気前がよく無計画なので、往きは大名のように贅沢をしてお金を使い果たし、帰りには乞食のように一文無しになるということ。 |
| 場面用途 | お金 |
| 類句 | 上り大名下り乞食 |
| 使用語彙 | 江戸っ子 / 子 / 往き / 乞食 |
| 使用漢字 | 江 / 戸 / 子 / 往 / 大 / 名 / 還 / 乞 / 食 |
「江」を含むことわざ
- 江戸っ子は五月の鯉の吹き流し(えどっこはさつきのこいのふきながし)
- 江戸っ子は宵越しの銭は使わぬ(えどっこはよいごしのぜにはつかわぬ)
- 江戸の敵を長崎で討つ(えどのかたきをながさきでうつ)
- 江戸は八百八町、大坂は八百八橋(えどははっぴゃくやちょう、おおさかははっぴゃくやばし)
- 江戸べらぼうに京どすえ(えどべらぼうにきょうどすえ)
- 近江泥棒伊勢乞食(おうみどろぼういせこじき)
- 火事と喧嘩は江戸の花(かじとけんかはえどのはな)
- 火事と喧嘩は江戸の華(かじとけんかはえどのはな)
- 俎上の魚江海に移る(そじょうのうおこうかいにうつる)
「戸」を含むことわざ
- 開いた口に戸は立てられぬ(あいたくちにはとはたてられぬ)
- 江戸っ子は五月の鯉の吹き流し(えどっこはさつきのこいのふきながし)
- 江戸っ子は宵越しの銭は使わぬ(えどっこはよいごしのぜにはつかわぬ)
- 江戸の敵を長崎で討つ(えどのかたきをながさきでうつ)
- 江戸は八百八町、大坂は八百八橋(えどははっぴゃくやちょう、おおさかははっぴゃくやばし)
- 江戸べらぼうに京どすえ(えどべらぼうにきょうどすえ)
- 火事と喧嘩は江戸の花(かじとけんかはえどのはな)
- 火事と喧嘩は江戸の華(かじとけんかはえどのはな)
- 九尺二間に戸が一枚(くしゃくにけんにとがいちまい)
「子」を含むことわざ
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 赤子の腕を捩じる(あかごのうでをねじる)
- 赤子の手をねじる(あかごのてをねじる)
- 赤子の手を捩じるよう(あかごのてをねじるよう)
- 赤子の手を捻る(あかごのてをひねる)
- 赤子の手を捻るよう(あかごのてをひねるよう)
- 赤子は泣き泣き育つ(あかごはなきなきそだつ)
- 赤子を裸にしたよう(あかごをはだかにしたよう)
- 秋茄子は嫁に食わすな(あきなすはよめにくわすな)
- 秋の日と娘の子はくれぬようでくれる(あきのひとむすめのこはくれぬようでくれる)
「往」を含むことわざ
- 愛出ずる者は愛返り、福往く者は福来る(あいいずるものはあいかえり、ふくゆくものはふくきたる)
- 往に跡へ行くとも死に跡へ行くな(いにあとへゆくともしにあとへゆくな)
- 往時渺茫としてすべて夢に似たり(おうじびょうぼうとしてすべてゆめににたり)
- 往生際が悪い(おうじょうぎわがわるい)
- 既往は咎めず(きおうはとがめず)
- 商売往来にない商売(しょうばいおうらいにないしょうばい)
- 千万人と雖も吾往かん(せんまんにんといえどもわれゆかん)
- 善人なおもて往生を遂ぐ、況んや悪人をや(ぜんにんなおもておうじょうをとぐ、いわんやあくにんをや)
- 立ち往生する(たちおうじょうする)
「大」を含むことわざ
- 阿保の大食い(あほのおおぐい)
- 諍いをしいしい腹を大きくし(いさかいをしいしいはらをおおきくし)
- 一木いずくんぞ能く大廈を支えん(いちぼくいずくんぞよくたいかをささえん)
- 一木大廈の崩るるを支うる能わず(いちぼくたいかのくずるるをささうるあたわず)
- 井の中の蛙大海を知らず(いのなかのかわずたいかいをしらず)
- 上を下への大騒ぎ(うえをしたへのおおさわぎ)
- 独活の大木(うどのたいぼく)
- 独活の大木柱にならぬ(うどのたいぼくはしらにならぬ)
- 瓜の皮は大名に剝かせよ、柿の皮は乞食に剝かせよ(うりのかわはだいみょうにむかせよ、かきのかわはこじきにむかせよ)
「名」を含むことわざ
- 相手のさする功名(あいてのさするこうみょう)
- 過ちの功名(あやまちのこうみょう)
- 言い勝ち功名(いいがちこうみょう)
- 浮き名を流す(うきなをながす)
- 瓜の皮は大名に剝かせよ、柿の皮は乞食に剝かせよ(うりのかわはだいみょうにむかせよ、かきのかわはこじきにむかせよ)
- 汚名を雪ぐ(おめいをすすぐ)
- 汚名を雪ぐ(おめいをそそぐ)
- 歌人は居ながらにして名所を知る(かじんはいながらにしてめいしょをしる)
- 勝ち名乗りを上げる(かちなのりをあげる)
「還」を含むことわざ
- 江戸っ子の往き大名還り乞食(えどっこのゆきだいみょうかえりこじき)
- 還暦(かんれき)
- 大吉は凶に還る(だいきちはきょうにかえる)
- 虎は千里往って千里還る(とらはせんりいってせんりかえる)
- 本卦還り(ほんけがえり)
- 本卦還りの三つ子(ほんけがえりのみつご)
「乞」を含むことわざ
- 慌てる乞食は貰いが少ない(あわてるこじきはもらいがすくない)
- 瓜の皮は大名に剝かせよ、柿の皮は乞食に剝かせよ(うりのかわはだいみょうにむかせよ、かきのかわはこじきにむかせよ)
- 浮気と乞食はやめられぬ(うわきとこじきはやめられぬ)
- 近江泥棒伊勢乞食(おうみどろぼういせこじき)
- 親苦、子楽、孫乞食(おやく、こらく、まごこじき)
- お椀を持たぬ乞食はない(おわんをもたぬこじきはない)
- 骸骨を乞う(がいこつをこう)
- 玉斧を乞う(ぎょくふをこう)
- 鍬を担げた乞食は来ない(くわをかたげたこじきはこない)



