夢は五臓の患いとは
夢は五臓の患い
ゆめはごぞうのわずらい
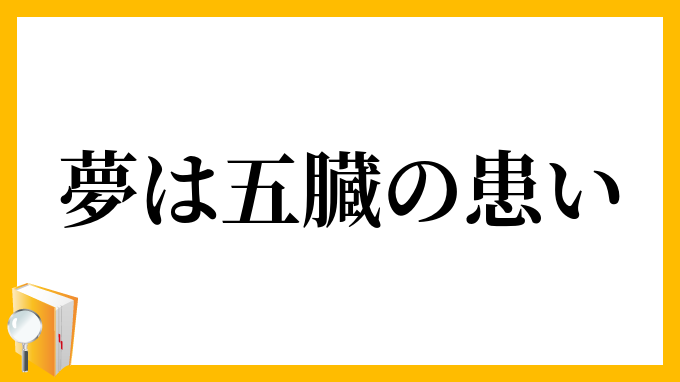
| 言葉 | 夢は五臓の患い |
|---|---|
| 読み方 | ゆめはごぞうのわずらい |
| 意味 | 夢を見るのは五臓(肝臓・心臓・脾臓・肺臓・腎臓)が疲れているのが原因だということ。
「患い」は「煩い」とも書く。 また、「夢は五臓の疲れ」ともいう。 |
| 異形 | 夢は五臓の煩い(ゆめはごぞうのわずらい) |
| 夢は五臓の疲れ(ゆめはごぞうのつかれ) | |
| 使用語彙 | 夢 / 五臓 / 五 |
| 使用漢字 | 夢 / 五 / 臓 / 患 / 煩 / 疲 |
「夢」を含むことわざ
- 一場の春夢(いちじょうのしゅんむ)
- 一炊の夢(いっすいのゆめ)
- 浮世は夢(うきよはゆめ)
- 栄華の夢(えいがのゆめ)
- 往時渺茫としてすべて夢に似たり(おうじびょうぼうとしてすべてゆめににたり)
- 槐安の夢(かいあんのゆめ)
- 槐夢(かいむ)
- 邯鄲の夢(かんたんのゆめ)
- 京の夢、大阪の夢(きょうのゆめ、おおさかのゆめ)
- 槿花一朝の夢(きんかいっちょうのゆめ)
「五」を含むことわざ
- 逢えば五厘の損がいく(あえばごりんのそんがいく)
- 会えば五厘の損がゆく(あえばごりんのそんがゆく)
- 朝起き三両始末五両(あさおきさんりょうしまつごりょう)
- 明日の百より今日の五十(あすのひゃくよりきょうのごじゅう)
- 一升の餅に五升の取り粉(いっしょうのもちにごしょうのとりこ)
- 一寸の虫にも五分の魂(いっすんのむしにもごぶのたましい)
- 江戸っ子は五月の鯉の吹き流し(えどっこはさつきのこいのふきながし)
- 男は二十五の暁まで育つ(おとこはにじゅうごのあかつきまでそだつ)
- 堪忍五両、思案十両(かんにんごりょう、しあんじゅうりょう)
- 堪忍五両、負けて三両(かんにんごりょう、まけてさんりょう)
「臓」を含むことわざ
「患」を含むことわざ
- 人生、字を識るは憂患の始め(じんせい、じをしるはゆうかんのはじめ)
- 無患子は三年磨いても黒い(むくろじはさんねんみがいてもくろい)
- 憂患に生き安楽に死す(ゆうかんにいきあんらくにしす)
- 夢は五臓の患い(ゆめはごぞうのわずらい)
「煩」を含むことわざ
- 手を煩わす(てをわずらわす)
- 手を煩わせる(てをわずらわせる)
- 煩悩の犬は追えども去らず(ぼんのうのいぬはおえどもさらず)
- 夢は五臓の煩い(ゆめはごぞうのわずらい)
「疲」を含むことわざ
- 鳥疲れて枝を選ばず(とりつかれてえだをえらばず)
- 夢は五臓の疲れ(ゆめはごぞうのつかれ)



