憂患に生き安楽に死すとは
憂患に生き安楽に死す
ゆうかんにいきあんらくにしす
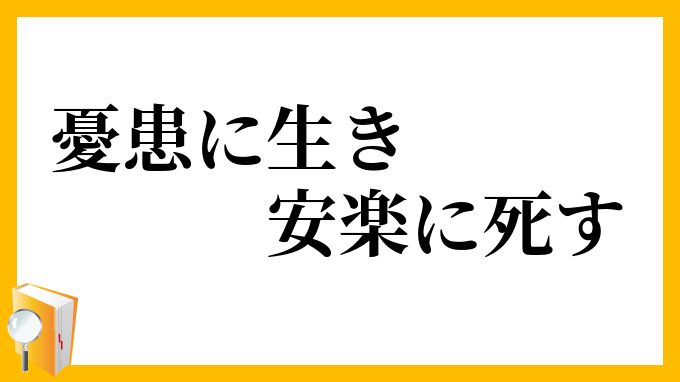
| 言葉 | 憂患に生き安楽に死す |
|---|---|
| 読み方 | ゆうかんにいきあんらくにしす |
| 意味 | 人は心配事がある時は心をいため、命を守る努力をするが、憂いがなくなると心がゆるみ、思わぬ死を招くこともあるということ。 |
| 出典 | 『孟子』 |
| 使用語彙 | 生き |
| 使用漢字 | 憂 / 患 / 生 / 安 / 楽 / 死 |
「憂」を含むことわざ
- 憂いも辛いも食うての上(ういもつらいもくうてのうえ)
- 憂き身をやつす(うきみをやつす)
- 憂き目に遭う(うきめにあう)
- 憂き目を見る(うきめをみる)
- 憂さを晴らす(うさをはらす)
- 憂いを掃う玉箒(うれいをはらうたまははき)
- 遠慮なければ近憂あり(えんりょなければきんゆうあり)
- 杞憂(きゆう)
- 君子は憂えず懼れず(くんしはうれえずおそれず)
- 後顧の憂い(こうこのうれい)
「患」を含むことわざ
- 人生、字を識るは憂患の始め(じんせい、じをしるはゆうかんのはじめ)
- 無患子は三年磨いても黒い(むくろじはさんねんみがいてもくろい)
- 憂患に生き安楽に死す(ゆうかんにいきあんらくにしす)
- 夢は五臓の患い(ゆめはごぞうのわずらい)
「生」を含むことわざ
- 諦めは心の養生(あきらめはこころのようじょう)
- 顎から先に生まれる(あごからさきにうまれる)
- 徒花に実は生らぬ(あだばなにみはならぬ)
- 生き馬の目を抜く(いきうまのめをぬく)
- 生き肝を抜く(いきぎもをぬく)
- 生き胆を抜く(いきぎもをぬく)
- 生きた心地もしない(いきたここちもしない)
- 生きた空もない(いきたそらもない)
- 生き血をしぼる(いきちをしぼる)
- 生き血を吸う(いきちをすう)
「安」を含むことわざ
- 安に居て危を思う(あんにいてきをおもう)
- 一抹の不安(いちまつのふあん)
- 燕雀安んぞ鴻鵠の志を知らんや(えんじゃくいずくんぞこうこくのこころざしをしらんや)
- お安い御用(おやすいごよう)
- お安くない(おやすくない)
- 槐安の夢(かいあんのゆめ)
- 現世安穏、後生善処(げんぜあんのん、ごしょうぜんしょ)
- 心安いは不和の基(こころやすいはふわのもと)
- 泰山の安きに置く(たいざんのやすきにおく)
- 高い舟借りて安い小魚釣る(たかいふねかりてやすいこざかなつる)
「楽」を含むことわざ
- あって地獄、なくて極楽(あってじごく、なくてごくらく)
- 親苦、子楽、孫乞食(おやく、こらく、まごこじき)
- 歓楽極まりて哀情多し(かんらくきわまりてあいじょうおおし)
- 楽屋裏を覗く(がくやうらをのぞく)
- 楽屋から火を出す(がくやからひをだす)
- 楽屋で声を嗄らす(がくやでこえをからす)
- 聞いて極楽、見て地獄(きいてごくらく、みてじごく)
- 曲肱の楽しみ(きょっこうのたのしみ)
- 苦あれば楽あり(くあればらくあり)
- 苦あれば楽あり、楽あれば苦あり(くあればらくあり、らくあればくあり)
「死」を含むことわざ
- 垢で死んだ者はない(あかでしんだものはない)
- 朝に道を聞かば夕べに死すとも可なり(あしたにみちをきかばゆうべにしすともかなり)
- 慌てる蟹は穴の口で死ぬ(あわてるかにはあなのくちでしぬ)
- 生きている犬は死んだライオンに勝る(いきているいぬはしんだらいおんにまさる)
- 生き身は死に身(いきみはしにみ)
- 生きるべきか死すべきかそれが問題だ(いきるべきかしすべきかそれがもんだいだ)
- 一度死ねば二度死なぬ(いちどしねばにどしなぬ)
- 往に跡へ行くとも死に跡へ行くな(いにあとへゆくともしにあとへゆくな)
- 運を待つは死を待つに等し(うんをまつはしをまつにひとし)
- 親が死んでも食休み(おやがしんでもしょくやすみ)



