生きた心地もしないとは
生きた心地もしない
いきたここちもしない
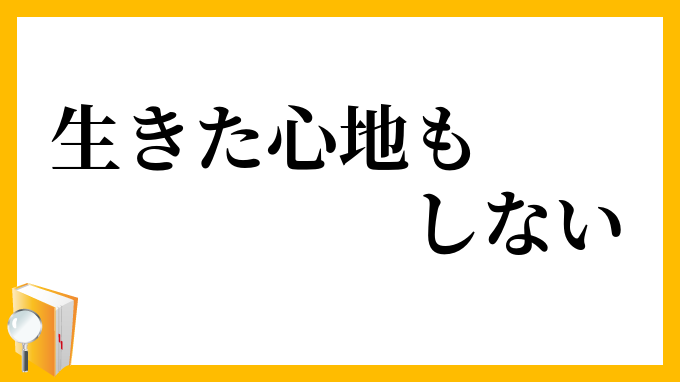
| 言葉 | 生きた心地もしない |
|---|---|
| 読み方 | いきたここちもしない |
| 意味 | 恐ろしさのあまり、生きているという感じがしないさま。 |
| 類句 | 生きた空もない(いきたそらもない) |
| 使用語彙 | 生き / 心地 |
| 使用漢字 | 生 / 心 / 地 |
「生」を含むことわざ
- 諦めは心の養生(あきらめはこころのようじょう)
- 顎から先に生まれる(あごからさきにうまれる)
- 徒花に実は生らぬ(あだばなにみはならぬ)
- 生き馬の目を抜く(いきうまのめをぬく)
- 生き肝を抜く(いきぎもをぬく)
- 生き胆を抜く(いきぎもをぬく)
- 生きた空もない(いきたそらもない)
- 生き血をしぼる(いきちをしぼる)
- 生き血を吸う(いきちをすう)
「心」を含むことわざ
- 諦めは心の養生(あきらめはこころのようじょう)
- 明日ありと思う心の仇桜(あすありとおもうこころのあだざくら)
- 頭剃るより心を剃れ(あたまそるよりこころをそれ)
- 網心あれば魚心(あみごころあればうおごごろ)
- 過つは人の性、許すは神の心(あやまつはひとのさが、ゆるすはかみのこころ)
- 怒り心頭に発する(いかりしんとうにはっする)
- 一心岩を通す(いっしんいわをとおす)
- 一心岩をも通す(いっしんいわをもとおす)
- 色は心の外(いろはこころのほか)



