現世安穏、後生善処とは
現世安穏、後生善処
げんぜあんのん、ごしょうぜんしょ
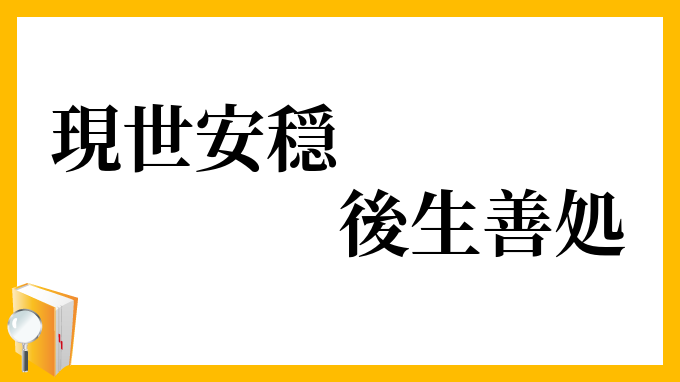
| 言葉 | 現世安穏、後生善処 |
|---|---|
| 読み方 | げんぜあんのん、ごしょうぜんしょ |
| 意味 | 法華経を信じる人は、この世では安穏に生活でき、あの世ではよい世界に生まれるということ。 |
| 使用語彙 | 安穏 / 後生 / 善処 |
| 使用漢字 | 現 / 世 / 安 / 穏 / 後 / 生 / 善 / 処 |
「現」を含むことわざ
- 現を抜かす(うつつをぬかす)
- 思い内にあれば色外に現る(おもいうちにあればいろそとにあらわる)
- 隠すより現る(かくすよりあらわる)
- 隠れたるより現るるはなし(かくれたるよりあらわるるはなし)
- 酒は本心を現す(さけはほんしんをあらわす)
- 姿は俗性を現す(すがたはぞくしょうをあらわす)
- 頭角を現す(とうかくをあらわす)
- 馬脚を現す(ばきゃくをあらわす)
「世」を含むことわざ
- 明日知らぬ世(あすしらぬよ)
- あの世の千日、この世の一日(あのよのせんにち、このよのいちにち)
- 石の物言う世の中(いしのものいうよのなか)
- 一世を風靡する(いっせいをふうびする)
- いらぬお世話の蒲焼(いらぬおせわのかばやき)
- 有為転変は世の習い(ういてんぺんはよのならい)
- 浮世の風(うきよのかぜ)
- 浮世は衣装七分(うきよはいしょうしちぶ)
- 浮世は回り持ち(うきよはまわりもち)
- 浮世は夢(うきよはゆめ)
「安」を含むことわざ
- 安に居て危を思う(あんにいてきをおもう)
- 一抹の不安(いちまつのふあん)
- 燕雀安んぞ鴻鵠の志を知らんや(えんじゃくいずくんぞこうこくのこころざしをしらんや)
- お安い御用(おやすいごよう)
- お安くない(おやすくない)
- 槐安の夢(かいあんのゆめ)
- 心安いは不和の基(こころやすいはふわのもと)
- 泰山の安きに置く(たいざんのやすきにおく)
- 高い舟借りて安い小魚釣る(たかいふねかりてやすいこざかなつる)
「穏」を含むことわざ
- 現世安穏、後生善処(げんぜあんのん、ごしょうぜんしょ)
「後」を含むことわざ
- 明後日の方(あさってのほう)
- 後足で砂をかける(あとあしですなをかける)
- 後味が悪い(あとあじがわるい)
- 後押しをする(あとおしをする)
- 後から剝げる正月言葉(あとからはげるしょうがつことば)
- 後がない(あとがない)
- 後釜に据える(あとがまにすえる)
- 後釜に座る(あとがまにすわる)
- 後釜に据わる(あとがまにすわる)
- 後口が悪い(あとくちがわるい)
「生」を含むことわざ
- 諦めは心の養生(あきらめはこころのようじょう)
- 顎から先に生まれる(あごからさきにうまれる)
- 徒花に実は生らぬ(あだばなにみはならぬ)
- 生き馬の目を抜く(いきうまのめをぬく)
- 生き肝を抜く(いきぎもをぬく)
- 生き胆を抜く(いきぎもをぬく)
- 生きた心地もしない(いきたここちもしない)
- 生きた空もない(いきたそらもない)
- 生き血をしぼる(いきちをしぼる)
- 生き血を吸う(いきちをすう)
「善」を含むことわざ
- 悪に強きは善にも強し(あくにつよきはぜんにもつよし)
- 悪人あればこそ善人も顕る(あくにんあればこそぜんにんもあらわる)
- 悪の裏は善(あくのうらはぜん)
- 牛に引かれて善光寺参り(うしにひかれてぜんこうじまいり)
- 正直は最善の策(しょうじきはさいぜんのさく)
- 小人閑居して不善をなす(しょうじんかんきょしてふぜんをなす)
- 積善の家には必ず余慶あり(せきぜんのいえにはかならずよけいあり)
- 善悪の報いは影の形に随うが如し(ぜんあくのむくいはかげのかたちにしたがうがごとし)
- 善悪は友による(ぜんあくはともによる)



