良薬は口に苦しとは
良薬は口に苦し
りょうやくはくちににがし
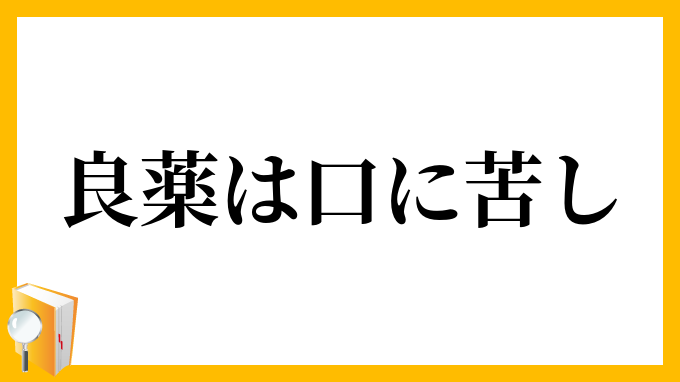
| 言葉 | 良薬は口に苦し |
|---|---|
| 読み方 | りょうやくはくちににがし |
| 意味 | よく効く薬ほど苦くて飲みにくいこと。ためになる忠告ほど、当人は耳が痛くて聞きづらいというたとえ。 |
| 出典 | 『孔子家語』 |
| 使用漢字 | 良 / 薬 / 口 / 苦 |
「良」を含むことわざ
- 悪貨は良貨を駆逐する(あっかはりょうかをくちくする)
- 家貧しくして良妻を思う(いえまずしくしてりょうさいをおもう)
- 入り船に良い風出船に悪い(いりふねによいかぜでふねにわるい)
- 遅かりし由良之助(おそかりしゆらのすけ)
- 親と月夜はいつも良い(おやとつきよはいつもよい)
- 金は良き召し使いなれど悪しき主なり(かねはよきめしつかいなれどあしきしゅなり)
- 杞梓連抱にして数尺の朽有るも良工は棄てず(きしれんぽうにしてすうせきのくちあるもりょうこうはすてず)
- 苦する良かろう楽する悪かろう(くするよかろうらくするわるかろう)
- 勝れて良き物は勝れて悪し(すぐれてよきものはすぐれてあし)
- 節制は最良の薬なり(せっせいはさいりょうのくすりなり)
「薬」を含むことわざ
- 青葉は目の薬(あおばはめのくすり)
- 姉女房は身代の薬(あねにょうぼうはしんだいのくすり)
- いい薬になる(いいくすりになる)
- 医者の薬も匙加減(いしゃのくすりもさじかげん)
- 一に看病、二に薬(いちにかんびょう、ににくすり)
- 生まれたあとの早め薬(うまれたあとのはやめぐすり)
- 大きい薬缶は沸きが遅い(おおきいやかんはわきがおそい)
- 薬師は人を殺せど薬人を殺さず(くすしはひとをころせどくすりひとをころさず)
- 薬が効く(くすりがきく)
- 薬になる(くすりになる)
「口」を含むことわざ
- 開いた口が塞がらない(あいたくちがふさがらない)
- 開いた口に戸は立てられぬ(あいたくちにはとはたてられぬ)
- 開いた口へ牡丹餅(あいたくちへぼたもち)
- 開いた口へ餅(あいたくちへもち)
- あったら口に風邪ひかす(あったらくちにかぜひかす)
- あったら口に風邪をひかす(あったらくちにかぜをひかす)
- 可惜口に風ひかす(あったらくちにかぜをひかす)
- 後口が悪い(あとくちがわるい)
- 慌てる蟹は穴の口で死ぬ(あわてるかにはあなのくちでしぬ)
- 言う口の下から(いうくちのしたから)



