医者の薬も匙加減とは
医者の薬も匙加減
いしゃのくすりもさじかげん
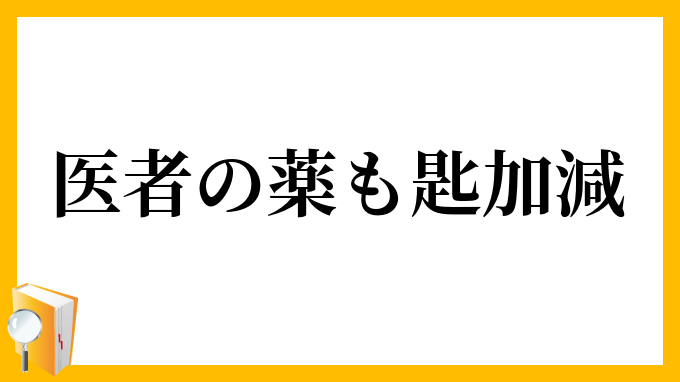
| 言葉 | 医者の薬も匙加減 |
|---|---|
| 読み方 | いしゃのくすりもさじかげん |
| 意味 | 何事も加減が大事だというたとえ。
医者がどんなに良い薬を使っても、分量が適切でなければ効き目がないということ。 |
| 使用語彙 | 医者 / 匙加減 / 加減 |
| 使用漢字 | 医 / 者 / 薬 / 匙 / 加 / 減 |
「医」を含むことわざ
- 医者が取るか坊主が取るか(いしゃがとるかぼうずがとるか)
- 医者寒からず儒者寒し(いしゃさむからずじゅしゃさむし)
- 医者上手にかかり下手(いしゃじょうずにかかりべた)
- 医者と味噌は古いほどよい(いしゃとみそはふるいほどよい)
- 医者の自脈効き目なし(いしゃのじみゃくききめなし)
- 医者の只今(いしゃのただいま)
- 医者の不養生(いしゃのふようじょう)
- 医者よ自らを癒せ(いしゃよみずからをいやせ)
- 医は仁術(いはじんじゅつ)
「者」を含むことわざ
- 愛出ずる者は愛返り、福往く者は福来る(あいいずるものはあいかえり、ふくゆくものはふくきたる)
- 青表紙を叩いた者にはかなわぬ(あおびょうしをたたいたものにはかなわぬ)
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 垢で死んだ者はない(あかでしんだものはない)
- 悪女の賢者ぶり(あくじょのけんじゃぶり)
- 当たった者のふの悪さ(あたったもののふのわるさ)
- 新たに沐する者は必ず冠を弾く(あらたにもくするものはかならずかんむりをはじく)
- 医者が取るか坊主が取るか(いしゃがとるかぼうずがとるか)
- 医者寒からず儒者寒し(いしゃさむからずじゅしゃさむし)
- 医者上手にかかり下手(いしゃじょうずにかかりべた)
「薬」を含むことわざ
- 青葉は目の薬(あおばはめのくすり)
- 姉女房は身代の薬(あねにょうぼうはしんだいのくすり)
- いい薬になる(いいくすりになる)
- 一に看病、二に薬(いちにかんびょう、ににくすり)
- 生まれたあとの早め薬(うまれたあとのはやめぐすり)
- 大きい薬缶は沸きが遅い(おおきいやかんはわきがおそい)
- 薬師は人を殺せど薬人を殺さず(くすしはひとをころせどくすりひとをころさず)
- 薬が効く(くすりがきく)
- 薬になる(くすりになる)
「匙」を含むことわざ
- 医者の薬も匙加減(いしゃのくすりもさじかげん)
- 匙の先より口の先(さじのさきよりくちのさき)
- 匙を投げる(さじをなげる)
- 切匙で腹を切る(せっかいではらをきる)



