新たに沐する者は必ず冠を弾くとは
新たに沐する者は必ず冠を弾く
あらたにもくするものはかならずかんむりをはじく
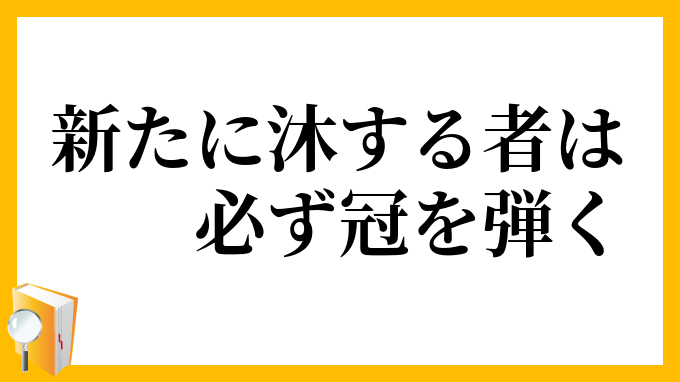
| 言葉 | 新たに沐する者は必ず冠を弾く |
|---|---|
| 読み方 | あらたにもくするものはかならずかんむりをはじく |
| 意味 | 潔白な人ほど自分の身を汚すおそれのあるものを避けるということ。
「沐」は髪を洗うこと。 髪を洗ったばかりの人は、必ず冠のちりを払ってから頭にのせるとの意から。 |
| 使用語彙 | 新た / 必ず / 弾く |
| 使用漢字 | 新 / 沐 / 者 / 必 / 冠 / 弾 |
「新」を含むことわざ
- 新しい酒は新しい革袋に盛れ(あたらしいさけはあたらしいかわぶくろにもれ)
- 新しい酒を古い革袋に盛る(あたらしいさけをふるいかわぶくろにもる)
- 新しき葡萄酒は新しき革袋に入れよ(あたらしきぶどうしゅはあたらしきかわぶくろにいれよ)
- 新規蒔き直し(しんきまきなおし)
- 女房と畳は新しいほうがよい(にょうぼうとたたみはあたらしいほうがよい)
- 日の下に新しきものなし(ひのもとにあたらしきものなし)
- 故きを温ねて新しきを知る(ふるきをたずねてあたらしきをしる)
- 面目を一新する(めんぼくをいっしんする)
- 装いを新たにする(よそおいをあらたにする)
「沐」を含むことわざ
- 新たに沐する者は必ず冠を弾く(あらたにもくするものはかならずかんむりをはじく)
- 風に櫛り雨に沐う(かぜにくしけずりあめにかみあらう)
- 沐猴にして冠す(もっこうにしてかんす)
「者」を含むことわざ
- 愛出ずる者は愛返り、福往く者は福来る(あいいずるものはあいかえり、ふくゆくものはふくきたる)
- 青表紙を叩いた者にはかなわぬ(あおびょうしをたたいたものにはかなわぬ)
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 垢で死んだ者はない(あかでしんだものはない)
- 当たった者のふの悪さ(あたったもののふのわるさ)
- 医者が取るか坊主が取るか(いしゃがとるかぼうずがとるか)
- 医者寒からず儒者寒し(いしゃさむからずじゅしゃさむし)
- 医者上手にかかり下手(いしゃじょうずにかかりべた)
- 医者と味噌は古いほどよい(いしゃとみそはふるいほどよい)
「必」を含むことわざ
- 陰徳あれば必ず陽報あり(いんとくあればかならずようほうあり)
- 三人行えば必ずわが師あり(さんにんおこなえばかならずわがしあり)
- 生者必滅、会者定離(しょうじゃひつめつ、えしゃじょうり)
- 小人の過つや必ず文る(しょうじんのあやまつやかならずかざる)
- 末大なれば必ず折る(すえだいなればかならずおる)
- 生ある者は必ず死あり(せいあるものはかならずしあり)
- 積悪の家には必ず余殃あり(せきあくのいえにはかならずよおうあり)
- 積善の家には必ず余慶あり(せきぜんのいえにはかならずよけいあり)
- 遠き慮りなき者は必ず近き憂えあり(とおきおもんぱかりなきものはかならずちかきうれえあり)
「冠」を含むことわざ
- お冠(おかんむり)
- 瓜田に履を納れず、李下に冠を正さず(かでんにくつをいれず、りかにかんむりをたださず)
- 冠蓋相望む(かんがいあいのぞむ)
- 冠を挂く(かんむりをかく)
- 冠を曲げる(かんむりをまげる)
- 鶏冠に来る(とさかにくる)
- 怒髪、冠を衝く(どはつ、かんむりをつく)
- 怒髪、冠を衝く(どはつ、かんをつく)
- 無冠の帝王(むかんのていおう)



