五指のこもごも弾くは捲手の一挃に若かずとは
五指のこもごも弾くは捲手の一挃に若かず
ごしのこもごもはじくはけんしゅのいっちつにしかず
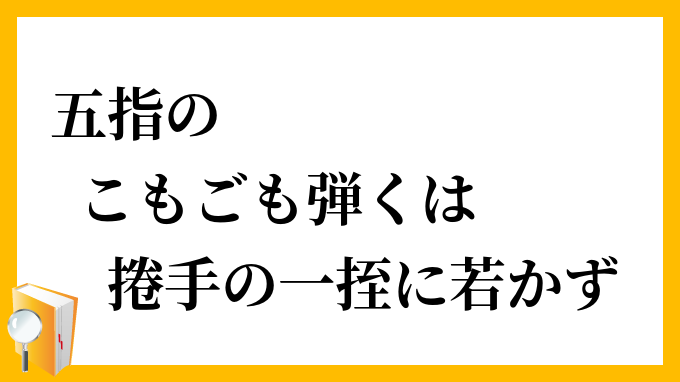
| 言葉 | 五指のこもごも弾くは捲手の一挃に若かず |
|---|---|
| 読み方 | ごしのこもごもはじくはけんしゅのいっちつにしかず |
| 意味 | ばらばらな個々の力は、団結した力には及ばないことのたとえ。
五本の指をばらばらにはじく力は、握りこぶしで叩いた一撃には及ばないとの意から。 |
| 出典 | 『淮南子』兵略訓 |
| 使用漢字 | 五 / 指 / 弾 / 捲 / 手 / 一 / 挃 / 若 |
「五」を含むことわざ
- 逢えば五厘の損がいく(あえばごりんのそんがいく)
- 会えば五厘の損がゆく(あえばごりんのそんがゆく)
- 朝起き三両始末五両(あさおきさんりょうしまつごりょう)
- 明日の百より今日の五十(あすのひゃくよりきょうのごじゅう)
- 一升の餅に五升の取り粉(いっしょうのもちにごしょうのとりこ)
- 一寸の虫にも五分の魂(いっすんのむしにもごぶのたましい)
- 江戸っ子は五月の鯉の吹き流し(えどっこはさつきのこいのふきながし)
- 男は二十五の暁まで育つ(おとこはにじゅうごのあかつきまでそだつ)
- 堪忍五両、思案十両(かんにんごりょう、しあんじゅうりょう)
- 堪忍五両、負けて三両(かんにんごりょう、まけてさんりょう)
「指」を含むことわざ
- 一指を染める(いっしをそめる)
- 後ろ指を指される(うしろゆびをさされる)
- 五指に余る(ごしにあまる)
- 五指に入る(ごしにはいる)
- 五本の指に入る(ごほんのゆびにはいる)
- 鹿を指して馬と言う(しかをさしてうまという)
- 鹿を指して馬となす(しかをさしてうまとなす)
- 指呼の間(しこのかん)
- 食指が動く(しょくしがうごく)
「弾」を含むことわざ
- 新たに沐する者は必ず冠を弾く(あらたにもくするものはかならずかんむりをはじく)
- 息を弾ませる(いきをはずませる)
- 牛に対して琴を弾ず(うしにたいしてことをだんず)
- 気が弾む(きがはずむ)
- 声が弾む(こえがはずむ)
- 心が弾む(こころがはずむ)
- 三味線を弾く(しゃみせんをひく)
- 銃弾に倒れる(じゅうだんにたおれる)
- 弾丸黒子の地(だんがんこくしのち)
「捲」を含むことわざ
- 朝雨と女の腕捲り(あさあめとおんなのうでまくり)
- 尻を捲る(けつをまくる)
- 五指のこもごも弾くは捲手の一挃に若かず(ごしのこもごもはじくはけんしゅのいっちつにしかず)
- 尻を捲る(しりをまくる)
- 俄雨と女の腕捲り(にわかあめとおんなのうでまくり)
「手」を含むことわざ
- 相手変われど手前変わらず(あいてかわれどてまえかわらず)
- 相手変われど主変わらず(あいてかわれどぬしかわらず)
- 相手にとって不足はない(あいてにとってふそくはない)
- 相手のさする功名(あいてのさするこうみょう)
- 相手のない喧嘩はできぬ(あいてのないけんかはできぬ)
- 相手見てからの喧嘩声(あいてみてからのけんかごえ)
- 合いの手を入れる(あいのてをいれる)
- 赤子の手をねじる(あかごのてをねじる)
- 赤子の手を捩じるよう(あかごのてをねじるよう)
- 赤子の手を捻る(あかごのてをひねる)
「一」を含むことわざ
- 悪は一旦の事なり(あくはいったんのことなり)
- 朝顔の花一時(あさがおのはないっとき)
- 朝の一時は晩の二時に当たる(あさのひとときはばんのふたときにあたる)
- 薊の花も一盛り(あざみのはなもひとさかり)
- あの世の千日、この世の一日(あのよのせんにち、このよのいちにち)
- 危ない橋も一度は渡れ(あぶないはしもいちどはわたれ)
- 粟一粒は汗一粒(あわひとつぶはあせひとつぶ)
- 板子一枚下は地獄(いたごいちまいしたはじごく)
- 一瓜実に二丸顔(いちうりざねににまるがお)
- 一応も二応も(いちおうもにおうも)
「挃」を含むことわざ
- 五指のこもごも弾くは捲手の一挃に若かず(ごしのこもごもはじくはけんしゅのいっちつにしかず)



