医者上手にかかり下手とは
医者上手にかかり下手
いしゃじょうずにかかりべた
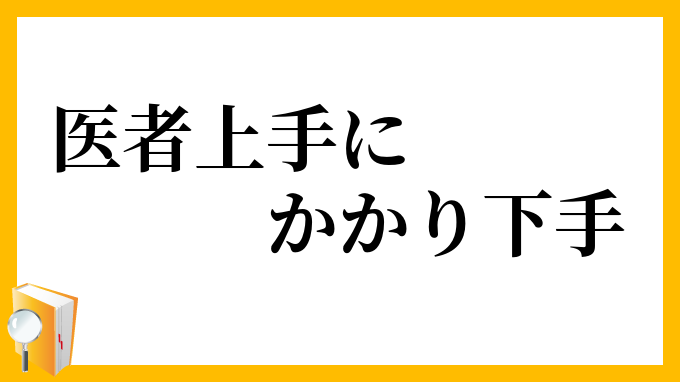
| 言葉 | 医者上手にかかり下手 |
|---|---|
| 読み方 | いしゃじょうずにかかりべた |
| 意味 | 物事はうまく行うためには相手を信用しなければならないというたとえ。
どんな名医でも、患者が信頼して従わなければ病気を治すことは出来ないとの意から。 |
| 使用語彙 | 医者 / 上手 |
| 使用漢字 | 医 / 者 / 上 / 手 / 下 |
「医」を含むことわざ
- 医者が取るか坊主が取るか(いしゃがとるかぼうずがとるか)
- 医者寒からず儒者寒し(いしゃさむからずじゅしゃさむし)
- 医者と味噌は古いほどよい(いしゃとみそはふるいほどよい)
- 医者の薬も匙加減(いしゃのくすりもさじかげん)
- 医者の自脈効き目なし(いしゃのじみゃくききめなし)
- 医者の只今(いしゃのただいま)
- 医者の不養生(いしゃのふようじょう)
- 医者よ自らを癒せ(いしゃよみずからをいやせ)
- 医は仁術(いはじんじゅつ)
「者」を含むことわざ
- 愛出ずる者は愛返り、福往く者は福来る(あいいずるものはあいかえり、ふくゆくものはふくきたる)
- 青表紙を叩いた者にはかなわぬ(あおびょうしをたたいたものにはかなわぬ)
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 垢で死んだ者はない(あかでしんだものはない)
- 悪女の賢者ぶり(あくじょのけんじゃぶり)
- 当たった者のふの悪さ(あたったもののふのわるさ)
- 新たに沐する者は必ず冠を弾く(あらたにもくするものはかならずかんむりをはじく)
- 医者が取るか坊主が取るか(いしゃがとるかぼうずがとるか)
- 医者寒からず儒者寒し(いしゃさむからずじゅしゃさむし)
「上」を含むことわざ
- 商い上手の仕入れ下手(あきないじょうずのしいれべた)
- 上げ潮に乗る(あげしおにのる)
- 上げ膳据え膳(あげぜんすえぜん)
- 上げたり下げたり(あげたりさげたり)
- 顎が干上がる(あごがひあがる)
- 梓に上す(あずさにのぼす)
- 頭押さえりゃ尻上がる(あたまおさえりゃしりあがる)
- 頭が上がらない(あたまがあがらない)
- 頭に血が上る(あたまにちがのぼる)
- 頭の上の蠅も追われぬ(あたまのうえのはえもおわれぬ)
「手」を含むことわざ
- 相手変われど主変わらず(あいてかわれどぬしかわらず)
- 相手にとって不足はない(あいてにとってふそくはない)
- 相手のさする功名(あいてのさするこうみょう)
- 相手のない喧嘩はできぬ(あいてのないけんかはできぬ)
- 相手見てからの喧嘩声(あいてみてからのけんかごえ)
- 合いの手を入れる(あいのてをいれる)
- 赤子の手を捻る(あかごのてをひねる)
- 商い上手の仕入れ下手(あきないじょうずのしいれべた)
- 開けて悔しき玉手箱(あけてくやしきたまてばこ)
- あの手この手(あのてこのて)



