陰徳あれば必ず陽報ありとは
陰徳あれば必ず陽報あり
いんとくあればかならずようほうあり
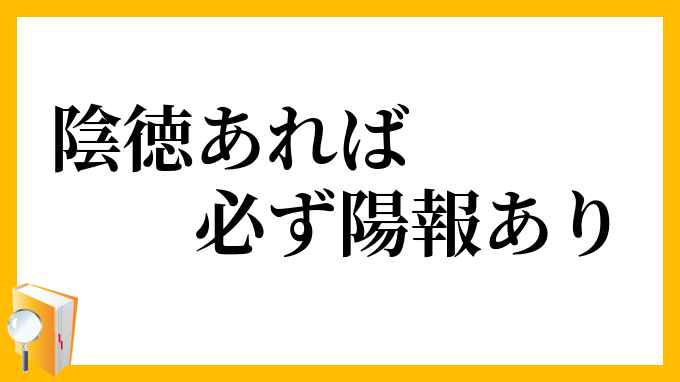
| 言葉 | 陰徳あれば必ず陽報あり |
|---|---|
| 読み方 | いんとくあればかならずようほうあり |
| 意味 | 人知れず善い行いをする者には、必ず善い報いがあるということ。 |
| 出典 | 『淮南子』 |
| 使用語彙 | 徳 / 必ず / 陽報 |
| 使用漢字 | 陰 / 徳 / 必 / 陽 / 報 |
「陰」を含むことわざ
- 暑さ忘れて陰忘る(あつさわすれてかげわする)
- 暑さ忘れれば陰忘れる(あつさわすれればかげわすれる)
- 一樹の陰一河の流れも他生の縁(いちじゅのかげいちがのながれもたしょうのえん)
- 一寸の光陰軽んずべからず(いっすんのこういんかろんずべからず)
- 陰影に富む(いんえいにとむ)
- 陰に籠もる(いんにこもる)
- 陰に陽に(いんにように)
- 豌豆は日陰でもはじける(えんどうはひかげでもはじける)
- 陰陽師、身の上知らず(おんようじ、みのうえしらず)
「徳」を含むことわざ
- 朝起きは三文の徳(あさおきはさんもんのとく)
- 朝起きは七つの徳(あさおきはななつのとく)
- 一目山随徳寺(いちもくさんずいとくじ)
- 一升徳利こけても三分(いっしょうどっくりこけてもさんぶ)
- 一升徳利に二升は入らぬ(いっしょうどっくりににしょうははいらぬ)
- 怨みに報ゆるに徳を以てす(うらみにむくゆるにとくをもってす)
- 落とした物は拾い徳(おとしたものはひろいどく)
- 隠れての信は顕われての徳(かくれてのしんはあらわれてのとく)
- 後生は徳の余り(ごしょうはとくのあまり)
「必」を含むことわざ
- 新たに沐する者は必ず冠を弾く(あらたにもくするものはかならずかんむりをはじく)
- 三人行えば必ずわが師あり(さんにんおこなえばかならずわがしあり)
- 生者必滅、会者定離(しょうじゃひつめつ、えしゃじょうり)
- 小人の過つや必ず文る(しょうじんのあやまつやかならずかざる)
- 末大なれば必ず折る(すえだいなればかならずおる)
- 生ある者は必ず死あり(せいあるものはかならずしあり)
- 積悪の家には必ず余殃あり(せきあくのいえにはかならずよおうあり)
- 積善の家には必ず余慶あり(せきぜんのいえにはかならずよけいあり)
- 遠き慮りなき者は必ず近き憂えあり(とおきおもんぱかりなきものはかならずちかきうれえあり)
「陽」を含むことわざ
- 陰に陽に(いんにように)
- 陰陽師、身の上知らず(おんようじ、みのうえしらず)
- 陽炎稲妻月の影(かげろういなずまつきのかげ)
- 陽炎稲妻水の月(かげろういなずまみずのつき)
- 太陽の照っているうちに干し草を作れ(たいようのてっているうちにほしくさをつくれ)
- 陽の照っているうちに干し草を作れ(ひのてっているうちにほしくさをつくれ)
- 陽気発する処、金石も亦透る(ようきはっするところ、きんせきもまたとおる)
- 洛陽の紙価を高める(らくようのしかをたかめる)



