隠れての信は顕われての徳とは
隠れての信は顕われての徳
かくれてのしんはあらわれてのとく
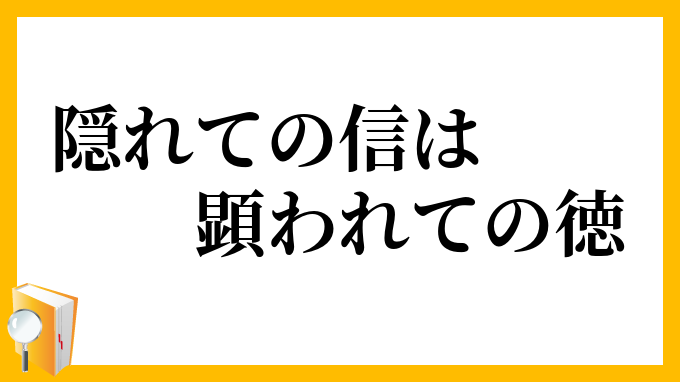
| 言葉 | 隠れての信は顕われての徳 |
|---|---|
| 読み方 | かくれてのしんはあらわれてのとく |
| 意味 | 心中に秘めている誠実さは、いつか自然に外にあらわれて自分自身の利得になるということ。
心中に神仏への信仰心があれば、必ずご利益があるとの意から。 「隠れたる信あらば顕われたる利生」「隠れたる信あらば顕われたる験」ともいう。 |
| 異形 | 隠れたる信あらば顕われたる利生(かくれたるしんあらばあらわれたるりしよう) |
| 隠れたる信あらば顕われたる験(かくれたるしんあらばあらわれたるしるし) | |
| 場面用途 | 無意識・自然に |
| 使用語彙 | 徳 |
| 使用漢字 | 隠 / 信 / 顕 / 徳 / 利 / 生 / 験 |
「隠」を含むことわざ
- 空き家の雪隠(あきやのせっちん)
- 頭隠して尻隠さず(あたまかくしてしりかくさず)
- 色の白いは七難隠す(いろのしろいはしちなんかくす)
- 隠密の沙汰は高く言え(おんみつのさたはたかくいえ)
- 隠すより現る(かくすよりあらわる)
- 隠れたるより現るるはなし(かくれたるよりあらわるるはなし)
- 隠れ蓑にする(かくれみのにする)
「信」を含むことわざ
- 赤信号が付く(あかしんごうがつく)
- 赤信号が点く(あかしんごうがつく)
- 移木の信(いぼくのしん)
- 鰯の頭も信心から(いわしのあたまもしんじんから)
- 韓信の股くぐり(かんしんのまたくぐり)
- 尽く書を信ずれば書なきに如かず(ことごとくしょをしんずればしょなきにしかず)
- 尽く書を信ずれば則ち書無きに如かず(ことごとくしょをしんずればすなわちしょなきにしかず)
「顕」を含むことわざ
- 悪人あればこそ善人も顕る(あくにんあればこそぜんにんもあらわる)
- 家貧しくして孝子顕る(いえまずしくしてこうしあらわる)
- 隠れたる信あらば顕われたる験(かくれたるしんあらばあらわれたるしるし)
- 隠れたる信あらば顕われたる利生(かくれたるしんあらばあらわれたるりしよう)
- 隠れての信は顕われての徳(かくれてのしんはあらわれてのとく)
- 桜は花に顕われる(さくらははなにあらわれる)
「徳」を含むことわざ
- 朝起きは三文の徳(あさおきはさんもんのとく)
- 朝起きは七つの徳(あさおきはななつのとく)
- 一目山随徳寺(いちもくさんずいとくじ)
- 一升徳利こけても三分(いっしょうどっくりこけてもさんぶ)
- 一升徳利に二升は入らぬ(いっしょうどっくりににしょうははいらぬ)
- 陰徳あれば必ず陽報あり(いんとくあればかならずようほうあり)
- 怨みに報ゆるに徳を以てす(うらみにむくゆるにとくをもってす)
- 落とした物は拾い徳(おとしたものはひろいどく)
- 後生は徳の余り(ごしょうはとくのあまり)
「利」を含むことわざ
- 一升徳利こけても三分(いっしょうどっくりこけてもさんぶ)
- 一升徳利に二升は入らぬ(いっしょうどっくりににしょうははいらぬ)
- 腕が利く(うでがきく)
- 大きな口を利く(おおきなくちをきく)
- 押さえが利く(おさえがきく)
- 押しが利く(おしがきく)
- 男冥利に尽きる(おとこみょうりにつきる)
- 親の意見と冷や酒は後で利く(おやのいけんとひやざけはあとできく)
- 女冥利に尽きる(おんなみょうりにつきる)
- 顔が利く(かおがきく)
「生」を含むことわざ
- 諦めは心の養生(あきらめはこころのようじょう)
- 顎から先に生まれる(あごからさきにうまれる)
- 徒花に実は生らぬ(あだばなにみはならぬ)
- 生き馬の目を抜く(いきうまのめをぬく)
- 生き肝を抜く(いきぎもをぬく)
- 生き胆を抜く(いきぎもをぬく)
- 生きた心地もしない(いきたここちもしない)
- 生きた空もない(いきたそらもない)
- 生き血をしぼる(いきちをしぼる)
- 生き血を吸う(いきちをすう)
「験」を含むことわざ
- 隠れたる信あらば顕われたる験(かくれたるしんあらばあらわれたるしるし)
- 経験は愚か者の師(けいけんはおろかもののし)
- 経験は知恵の父記憶の母(けいけんはちえのちちきおくのはは)
- 験がいい(げんがいい)
- 験を担ぐ(げんをかつぐ)



