隠密の沙汰は高く言えとは
隠密の沙汰は高く言え
おんみつのさたはたかくいえ
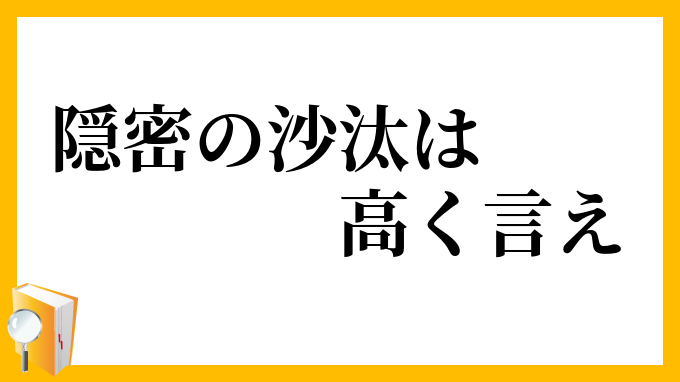
| 言葉 | 隠密の沙汰は高く言え |
|---|---|
| 読み方 | おんみつのさたはたかくいえ |
| 意味 | 秘密の話はこそこそ言わずに大きな声で話せということ。
ひそひそ話は人の好奇心をかきたて注意をひきやすいので、普通に話しているほうが目立たず秘密が守れるとの意から。 |
| 使用語彙 | 沙汰 |
| 使用漢字 | 隠 / 密 / 沙 / 汰 / 高 / 言 |
「隠」を含むことわざ
- 空き家の雪隠(あきやのせっちん)
- 頭隠して尻隠さず(あたまかくしてしりかくさず)
- 色の白いは七難隠す(いろのしろいはしちなんかくす)
- 隠すより現る(かくすよりあらわる)
- 隠れたるより現るるはなし(かくれたるよりあらわるるはなし)
- 隠れての信は顕われての徳(かくれてのしんはあらわれてのとく)
- 隠れ蓑にする(かくれみのにする)
- 隠れもない(かくれもない)
- 考えは雪隠(かんがえはせっちん)
「密」を含むことわざ
- 隠密の沙汰は高く言え(おんみつのさたはたかくいえ)
- 公然の秘密(こうぜんのひみつ)
- 謀は密なるを貴ぶ(はかりごとはみつなるをたっとぶ)
「沙」を含むことわざ
- 胡乱の沙汰(うろんのさた)
- 遠慮は無沙汰(えんりょはぶさた)
- 音沙汰が無い(おとざたがない)
- 沙汰の限り(さたのかぎり)
- 沙中の偶語(さちゅうのぐうご)
- 沙弥から長老(しゃみからちょうろう)
- 沙弥から長老にはなれぬ(しゃみからちょうろうにはなれぬ)
- 地獄の沙汰も金次第(じごくのさたもかねしだい)
- 仏の沙汰も銭(ほとけのさたもぜに)
「汰」を含むことわざ
- 胡乱の沙汰(うろんのさた)
- 遠慮は無沙汰(えんりょはぶさた)
- 音沙汰が無い(おとざたがない)
- 沙汰の限り(さたのかぎり)
- 地獄の沙汰も金次第(じごくのさたもかねしだい)
- 隣の糂汰味噌(となりのじんだみそ)
- 仏の沙汰も銭(ほとけのさたもぜに)
「高」を含むことわざ
- 空樽は音が高い(あきだるはおとがたかい)
- お高くとまる(おたかくとまる)
- 勘定高い(かんじょうだかい)
- 気位が高い(きぐらいがたかい)
- 食わず貧楽高枕(くわずひんらくたかまくら)
- 計算高い(けいさんだかい)
- 桂馬の高上がり(けいまのたかあがり)
- 高閣に束ねる(こうかくにつかねる)
- 高山の巓には美木なし(こうざんのいただきにはびぼくなし)



