移木の信とは
移木の信
いぼくのしん
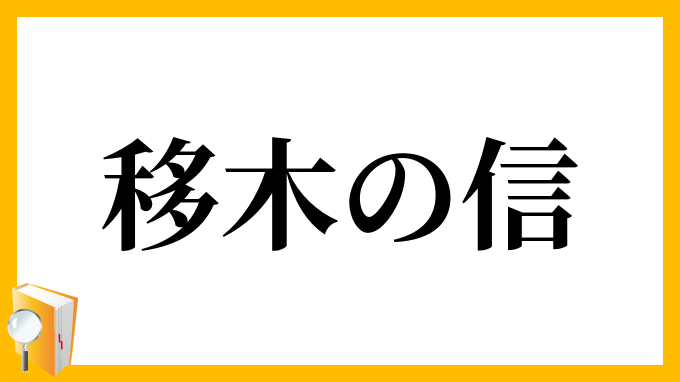
| 言葉 | 移木の信 |
|---|---|
| 読み方 | いぼくのしん |
| 意味 | 約束を確実に実行すること。中国秦の商鞅は法令を徹底させるために、都の南門に立てた木を北門に移した者に懸賞金を与えると布告し、その約束を守り人民を欺かないと実証したという故事から。 |
| 出典 | 『史記』 |
| 使用漢字 | 移 / 木 / 信 |
「移」を含むことわざ
- 移り変わるは浮き世の習い(うつりかわるはうきよのならい)
- 移れば変わる世の習い(うつればかわるよのならい)
- 居は気を移す(きょはきをうつす)
- 愚公、山を移す(ぐこう、やまをうつす)
- 心を移す(こころをうつす)
- 情が移る(じょうがうつる)
- 上知と下愚とは移らず(じょうちとかぐとはうつらず)
- 俎上の魚江海に移る(そじょうのうおこうかいにうつる)
- 時を移さず(ときをうつさず)
「木」を含むことわざ
- 足を擂り粉木にする(あしをすりこぎにする)
- 諍い果てての乳切り木(いさかいはててのちぎりぎ)
- 諍い果てての千切り木(いさかいはててのちぎりぎ)
- 石が流れて木の葉が沈む(いしがながれてこのはがしずむ)
- 一木いずくんぞ能く大廈を支えん(いちぼくいずくんぞよくたいかをささえん)
- 一木大廈の崩るるを支うる能わず(いちぼくたいかのくずるるをささうるあたわず)
- 植木屋の庭できが多い(うえきやのにわできがおおい)
- 植木屋の庭で気が多い(うえきやのにわできがおおい)
- 魚の木に登るが如し(うおのきにのぼるがごとし)



