上知と下愚とは移らずとは
上知と下愚とは移らず
じょうちとかぐとはうつらず
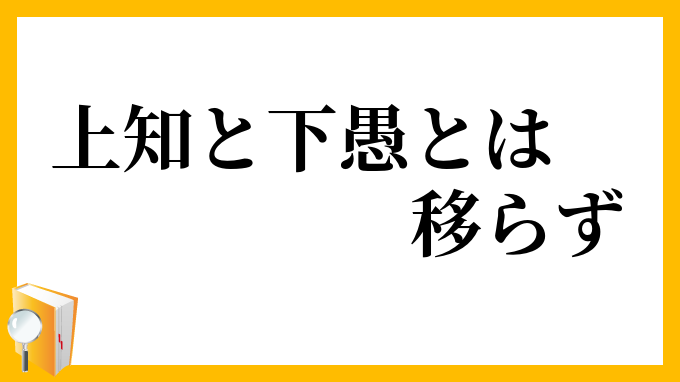
| 言葉 | 上知と下愚とは移らず |
|---|---|
| 読み方 | じょうちとかぐとはうつらず |
| 意味 | 生まれつき賢い者、また、生まれつき愚かな者はあとからの教育や環境で変わるものではないということ。「上知」はすぐれた知恵、「下愚」はきわめて愚かなこと。 |
| 出典 | 『論語』陽貨 |
| 場面用途 | 生まれつき・生まれながら |
| 使用漢字 | 上 / 知 / 下 / 愚 / 移 |
「上」を含むことわざ
- 商い上手の仕入れ下手(あきないじょうずのしいれべた)
- 上げ潮に乗る(あげしおにのる)
- 上げ膳据え膳(あげぜんすえぜん)
- 上げ膳に据え膳(あげぜんにすえぜん)
- 上げたり下げたり(あげたりさげたり)
- 顎が干上がる(あごがひあがる)
- 梓に上す(あずさにのぼす)
- 頭押さえりゃ尻上がる(あたまおさえりゃしりあがる)
- 頭が上がらない(あたまがあがらない)
- 頭に血が上る(あたまにちがのぼる)
「知」を含むことわざ
- 相対のことはこちゃ知らぬ(あいたいのことはこちゃしらぬ)
- 明日知らぬ世(あすしらぬよ)
- 過ちを観て斯に仁を知る(あやまちをみてここにじんをしる)
- 過ちを観て仁を知る(あやまちをみてじんをしる)
- 息の臭きは主知らず(いきのくさきはぬししらず)
- いざ知らず(いざしらず)
- 衣食足りて栄辱を知る(いしょくたりてえいじょくをしる)
- 衣食足りて礼節を知る(いしょくたりてれいせつをしる)
- 衣食足れば則ち栄辱を知る(いしょくたればすなわちえいじょくをしる)
- 一文惜しみの百知らず(いちもんおしみのひゃくしらず)
「下」を含むことわざ
- 敢えて天下の先とならず(あえててんかのさきとならず)
- 商い上手の仕入れ下手(あきないじょうずのしいれべた)
- 上げたり下げたり(あげたりさげたり)
- 足下から鳥が立つ(あしもとからとりがたつ)
- 足下につけ込む(あしもとにつけこむ)
- 足下に火が付く(あしもとにひがつく)
- 足下にも及ばない(あしもとにもおよばない)
- 足下にも寄りつけない(あしもとにもよりつけない)
- 足下の明るいうち(あしもとのあかるいうち)
- 足下へも寄り付けない(あしもとへもよりつけない)
「愚」を含むことわざ
- 言うも愚か(いうもおろか)
- 愚か者に福あり(おろかものにふくあり)
- 愚公、山を移す(ぐこう、やまをうつす)
- 愚者にも一得(ぐしゃにもいっとく)
- 愚者の一得(ぐしゃのいっとく)
- 愚者の百行より知者の居眠り(ぐしゃのひゃっこうよりちしゃのいねむり)
- 愚者も一得(ぐしゃもいっとく)
- 愚者も千慮に一得有り(ぐしゃもせんりょにいっとくあり )
- 愚痴をこぼす(ぐちをこぼす)
- 愚の骨頂(ぐのこっちょう)



