生者必滅、会者定離とは
生者必滅、会者定離
しょうじゃひつめつ、えしゃじょうり
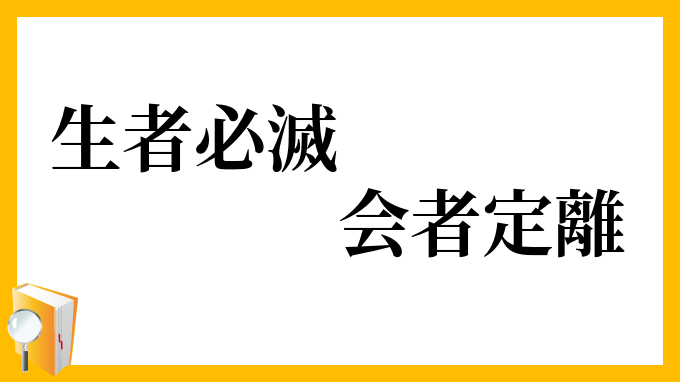
| 言葉 | 生者必滅、会者定離 |
|---|---|
| 読み方 | しょうじゃひつめつ、えしゃじょうり |
| 意味 | 命ある者はいつか必ず死に、出会った者はいずれ別れるのがこの世の定めであるということ。 |
| 類句 | 生き身は死に身(いきみはしにみ) |
| 生ある者は必ず死あり(せいあるものはかならずしあり) | |
| 使用漢字 | 生 / 者 / 必 / 滅 / 会 / 定 / 離 |
「生」を含むことわざ
- 諦めは心の養生(あきらめはこころのようじょう)
- 徒花に実は生らぬ(あだばなにみはならぬ)
- 生き馬の目を抜く(いきうまのめをぬく)
- 生き肝を抜く(いきぎもをぬく)
- 生きた心地もしない(いきたここちもしない)
- 生きた空もない(いきたそらもない)
- 生き血を吸う(いきちをすう)
- 生きている犬は死んだライオンに勝る(いきているいぬはしんだらいおんにまさる)
- 生きとし生けるもの(いきとしいけるもの)
- 生き恥を曝す(いきはじをさらす)
「者」を含むことわざ
- 愛出ずる者は愛返り、福往く者は福来る(あいいずるものはあいかえり、ふくゆくものはふくきたる)
- 青表紙を叩いた者にはかなわぬ(あおびょうしをたたいたものにはかなわぬ)
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 垢で死んだ者はない(あかでしんだものはない)
- 悪女の賢者ぶり(あくじょのけんじゃぶり)
- 当たった者のふの悪さ(あたったもののふのわるさ)
- 新たに沐する者は必ず冠を弾く(あらたにもくするものはかならずかんむりをはじく)
- 医者が取るか坊主が取るか(いしゃがとるかぼうずがとるか)
- 医者寒からず儒者寒し(いしゃさむからずじゅしゃさむし)
- 医者上手にかかり下手(いしゃじょうずにかかりべた)
「必」を含むことわざ
- 新たに沐する者は必ず冠を弾く(あらたにもくするものはかならずかんむりをはじく)
- 陰徳あれば必ず陽報あり(いんとくあればかならずようほうあり)
- 三人行えば必ずわが師あり(さんにんおこなえばかならずわがしあり)
- 小人の過つや必ず文る(しょうじんのあやまつやかならずかざる)
- 末大なれば必ず折る(すえだいなればかならずおる)
- 生ある者は必ず死あり(せいあるものはかならずしあり)
- 積悪の家には必ず余殃あり(せきあくのいえにはかならずよおうあり)
- 積善の家には必ず余慶あり(せきぜんのいえにはかならずよけいあり)
- 遠き慮りなき者は必ず近き憂えあり(とおきおもんぱかりなきものはかならずちかきうれえあり)
「滅」を含むことわざ
- 気が滅入る(きがめいる)
- 唇滅びて歯寒し(くちびるほろびてはさむし)
- 心頭滅却すれば火もまた涼し(しんとうめっきゃくすればひもまたすずし)
- 大義、親を滅す(たいぎ、しんをめっす)
- 大徳は小怨を滅ぼす(だいとくはしょうえんをほろぼす)
- 灯滅せんとして光を増す(とうめっせんとしてひかりをます)
- 平家を滅ぼすは平家(へいけをほろぼすはへいけ)
- 兵強ければ則ち滅ぶ(へいつよければすなわちほろぶ)
- 滅相もない(めっそうもない)
「会」を含むことわざ
- 会うは別れの始め(あうはわかれのはじめ)
- 会えば五厘の損がゆく(あえばごりんのそんがゆく)
- 会わせる顔がない(あわせるかおがない)
- 一堂に会する(いちどうにかいする)
- 遠慮会釈もない(えんりょえしゃくもない)
- 会うた時に笠を脱げ(おうたときにかさをぬげ)
- 会稽の恥(かいけいのはじ)
- 会稽の恥を雪ぐ(かいけいのはじをすすぐ)
- 会心の笑みをもらす(かいしんのえみをもらす)
- 今度と化け物には行き会った事がない(こんどとばけものにはいきあったことがない)
「定」を含むことわざ
- 生まれる前の襁褓定め(うまれるまえのむつきさだめ)
- 小田原評定(おだわらひょうじょう)
- 勘定合って銭足らず(かんじょうあってぜにたらず)
- 勘定高い(かんじょうだかい)
- 勘定に入れる(かんじょうにいれる)
- 棺を蓋いて事定まる(かんをおおいてことさだまる)
- 三度目は定の目(さんどめはじょうのめ)
- 丼勘定(どんぶりかんじょう)
- 狙いを定める(ねらいをさだめる)



