末大なれば必ず折るとは
末大なれば必ず折る
すえだいなればかならずおる
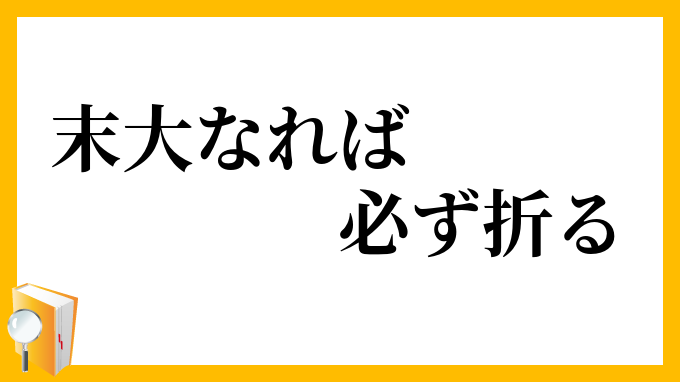
| 言葉 | 末大なれば必ず折る |
|---|---|
| 読み方 | すえだいなればかならずおる |
| 意味 | 下の者の勢力が強くなると、上の者は必ず倒されてしまうということ。
松葉が茂り重くなると、強い幹も折れてしまうとの意から。 |
| 出典 | 『春秋左氏伝』 |
| 場面用途 | 松 |
| 類句 | 尾大掉わず(びだいふるわず) |
| 使用語彙 | 末 / 必ず |
| 使用漢字 | 末 / 大 / 必 / 折 |
「末」を含むことわざ
- 朝起き三両始末五両(あさおきさんりょうしまつごりょう)
- 縁と浮き世は末を待て(えんとうきよはすえをまて)
- 三代続けば末代続く(さんだいつづけばまつだいつづく)
- 始末が悪い(しまつがわるい)
- 始末に負えない(しまつにおえない)
- 始末を付ける(しまつをつける)
- 末四十より今の三十(すえしじゅうよりいまのさんじゅう)
- 末始終より今の三十(すえしじゅうよりいまのさんじゅう)
- 末の露、本の雫(すえのつゆ、もとのしずく)
「大」を含むことわざ
- 阿保の大食い(あほのおおぐい)
- 諍いをしいしい腹を大きくし(いさかいをしいしいはらをおおきくし)
- 一木いずくんぞ能く大廈を支えん(いちぼくいずくんぞよくたいかをささえん)
- 一木大廈の崩るるを支うる能わず(いちぼくたいかのくずるるをささうるあたわず)
- 井の中の蛙大海を知らず(いのなかのかわずたいかいをしらず)
- 上を下への大騒ぎ(うえをしたへのおおさわぎ)
- 独活の大木(うどのたいぼく)
- 独活の大木柱にならぬ(うどのたいぼくはしらにならぬ)
- 瓜の皮は大名に剝かせよ、柿の皮は乞食に剝かせよ(うりのかわはだいみょうにむかせよ、かきのかわはこじきにむかせよ)
- 江戸っ子の往き大名還り乞食(えどっこのゆきだいみょうかえりこじき)
「必」を含むことわざ
- 新たに沐する者は必ず冠を弾く(あらたにもくするものはかならずかんむりをはじく)
- 陰徳あれば必ず陽報あり(いんとくあればかならずようほうあり)
- 三人行えば必ずわが師あり(さんにんおこなえばかならずわがしあり)
- 生者必滅、会者定離(しょうじゃひつめつ、えしゃじょうり)
- 小人の過つや必ず文る(しょうじんのあやまつやかならずかざる)
- 生ある者は必ず死あり(せいあるものはかならずしあり)
- 積悪の家には必ず余殃あり(せきあくのいえにはかならずよおうあり)
- 積善の家には必ず余慶あり(せきぜんのいえにはかならずよけいあり)
- 遠き慮りなき者は必ず近き憂えあり(とおきおもんぱかりなきものはかならずちかきうれえあり)



