瓜田に履を納れず、李下に冠を正さずとは
瓜田に履を納れず、李下に冠を正さず
かでんにくつをいれず、りかにかんむりをたださず
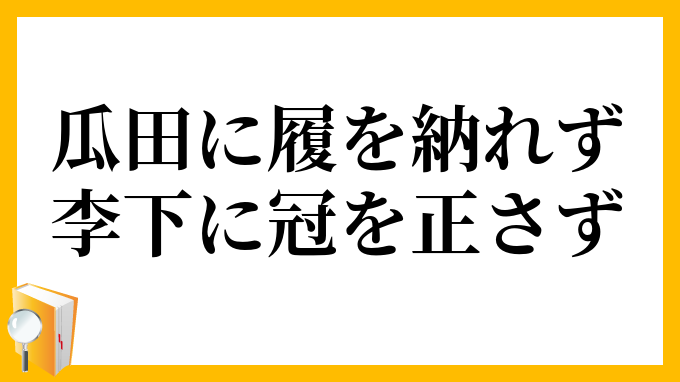
| 言葉 | 瓜田に履を納れず、李下に冠を正さず |
|---|---|
| 読み方 | かでんにくつをいれず、りかにかんむりをたださず |
| 意味 | 人から疑われるような行動は避けるべきであるという戒めの言葉。
「瓜田」は、瓜(うり)を育てている畑。 「李下」は、李(すもも)の木の下。 瓜を盗むのではないかと疑われるので瓜田では靴を履きなおしてはいけない、李を盗むのではないかと疑われるので李の木の下では冠をかぶりなおしてはいけないということ。 単に「瓜田に履を納れず」「李下に冠を正さず」ともいう。 また、「李下の冠、瓜田の履」ともいう。 |
| 出典 | 『古楽府』 |
| 異形 | 瓜田に履を納れず(かでんにくつをいれず) |
| 李下に冠を正さず(りかにかんむりをたださず) | |
| 李下の冠、瓜田の履(りかのかんむり、かでんのくつ) | |
| 使用語彙 | 瓜田 / 李下 |
| 使用漢字 | 瓜 / 田 / 履 / 納 / 李 / 下 / 冠 / 正 |
「瓜」を含むことわざ
- 一瓜実に二丸顔(いちうりざねににまるがお)
- 瓜に爪あり爪に爪なし(うりにつめありつめにつめなし)
- 瓜の皮は大名に剝かせよ、柿の皮は乞食に剝かせよ(うりのかわはだいみょうにむかせよ、かきのかわはこじきにむかせよ)
- 瓜の蔓に茄子は生らぬ(うりのつるになすびはならぬ)
- 瓜二つ(うりふたつ)
- 南瓜に目鼻(かぼちゃにめはな)
- 西瓜は土で作れ南瓜は手で作れ(すいかはつちでつくれかぼちゃはてでつくれ)
- 爪に爪なく瓜に爪あり(つめにつめなくうりにつめあり)
- 破瓜の年(はかのとし)
「田」を含むことわざ
- 青田買い(あおたがい)
- 朝酒は門田を売っても飲め(あさざけはかどたをうってものめ)
- 畦から行くも田から行くも同じ(あぜからいくもたからいくもおなじ)
- 田舎の学問より京の昼寝(いなかのがくもんよりきょうのひるね)
- 小田原評定(おだわらひょうじょう)
- 京に田舎あり(きょうにいなかあり)
- 句を作るより田を作れ(くをつくるよりたをつくれ)
- 甲由田申は筆者の誤り、十点千字は継母の謀(こうゆでんしんはひっしゃのあやまり、じってんせんじはけいぼのはかりごと)
- 三十振袖、四十島田(さんじゅうふりそで、しじゅうしまだ)
「履」を含むことわざ
- 足駄を履いて首ったけ(あしだをはいてくびったけ)
- 足駄を履く(あしだをはく)
- 下駄を履かせる(げたをはかせる)
- 霜を履んで堅氷至る(しもをふんでけんぴょういたる)
- 草履に灸(ぞうりにきゅう)
- 草履履き際で仕損じる(ぞうりはきぎわでしそんじる)
- 伊達の素足もないから起こる、あれば天鵞絨の足袋も履く(だてのすあしもないからおこる、あればびろうどのたびもはく)
- 二足の草鞋を履く(にそくのわらじをはく)
- 薄氷を履むが如し(はくひょうをふむがごとし)
「納」を含むことわざ
- 瓜田に履を納れず、李下に冠を正さず(かでんにくつをいれず、りかにかんむりをたださず)
- 納所から和尚(なっしょからおしょう)
- 年貢の納め時(ねんぐのおさめどき)
- 胸三寸に納める(むねさんずんにおさめる)
「李」を含むことわざ
- 瓜田に履を納れず、李下に冠を正さず(かでんにくつをいれず、りかにかんむりをたださず)
- 桃李もの言わざれども下自ずから蹊を成す(とうりものいわざれどもしたおのずからけいをなす)
「下」を含むことわざ
- 敢えて天下の先とならず(あえててんかのさきとならず)
- 商い上手の仕入れ下手(あきないじょうずのしいれべた)
- 上げたり下げたり(あげたりさげたり)
- 足下から鳥が立つ(あしもとからとりがたつ)
- 足下につけ込む(あしもとにつけこむ)
- 足下に火が付く(あしもとにひがつく)
- 足下にも及ばない(あしもとにもおよばない)
- 足下の明るいうち(あしもとのあかるいうち)
- 足下へも寄り付けない(あしもとへもよりつけない)
- 足下を固める(あしもとをかためる)
「冠」を含むことわざ
- 新たに沐する者は必ず冠を弾く(あらたにもくするものはかならずかんむりをはじく)
- お冠(おかんむり)
- 冠蓋相望む(かんがいあいのぞむ)
- 冠を挂く(かんむりをかく)
- 冠を曲げる(かんむりをまげる)
- 鶏冠に来る(とさかにくる)
- 怒髪、冠を衝く(どはつ、かんむりをつく)
- 無冠の帝王(むかんのていおう)
- 沐猴にして冠す(もっこうにしてかんす)



