桃李もの言わざれども下自ずから蹊を成すとは
桃李もの言わざれども下自ずから蹊を成す
とうりものいわざれどもしたおのずからけいをなす
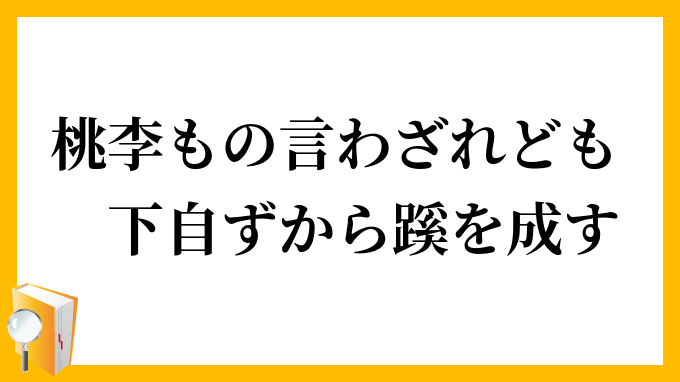
| 言葉 | 桃李もの言わざれども下自ずから蹊を成す |
|---|---|
| 読み方 | とうりものいわざれどもしたおのずからけいをなす |
| 意味 | 徳のある人のもとへは、自然に人々が集まることのたとえ。
桃や李(すもも)は何も言わないがその花や実に惹かれて人が集まり、木の下には自然に小道ができるとの意から。 「蹊」は小道のこと。 「成蹊」ともいう。 |
| 出典 | 『史記』 |
| 異形 | 成蹊(せいけい) |
| 場面用途 | 無意識・自然に |
| 使用語彙 | 自ずから / 成す |
| 使用漢字 | 桃 / 李 / 言 / 下 / 自 / 蹊 / 成 |
「桃」を含むことわざ
- 驚き、桃の木、山椒の木(おどろき、もものき、さんしょのき)
- 桃源(とうげん)
- 桃源郷(とうげんきょう)
- 桃李もの言わざれども下自ずから蹊を成す(とうりものいわざれどもしたおのずからけいをなす)
- 桃栗三年柿八年(ももくりさんねんかきはちねん)
- 余桃の罪(よとうのつみ)
「李」を含むことわざ
- 瓜田に履を納れず、李下に冠を正さず(かでんにくつをいれず、りかにかんむりをたださず)
- 桃李もの言わざれども下自ずから蹊を成す(とうりものいわざれどもしたおのずからけいをなす)
- 李下に冠を正さず(りかにかんむりをたださず)
- 李下の冠、瓜田の履(りかのかんむり、かでんのくつ)
「言」を含むことわざ
- ああ言えばこう言う(ああいえばこういう)
- 合言葉にする(あいことばにする)
- 呆れて物が言えない(あきれてものがいえない)
- 明日の事を言えば鬼が笑う(あすのことをいえばおにがわらう)
- あっと言う間(あっというま)
- あっと言わせる(あっといわせる)
- 後から剝げる正月言葉(あとからはげるしょうがつことば)
- 穴を掘って言い入れる(あなをほっていいいれる)
- 有り体に言う(ありていにいう)
- 言い得て妙(いいえてみょう)
「下」を含むことわざ
- 敢えて天下の先とならず(あえててんかのさきとならず)
- 商い上手の仕入れ下手(あきないじょうずのしいれべた)
- 上げたり下げたり(あげたりさげたり)
- 足下から鳥が立つ(あしもとからとりがたつ)
- 足下につけ込む(あしもとにつけこむ)
- 足下に火が付く(あしもとにひがつく)
- 足下にも及ばない(あしもとにもおよばない)
- 足下にも寄りつけない(あしもとにもよりつけない)
- 足下の明るいうち(あしもとのあかるいうち)
- 足下へも寄り付けない(あしもとへもよりつけない)
「自」を含むことわざ
- 相惚れ自惚れ片惚れ岡惚れ(あいぼれうぬぼれかたぼれおかぼれ)
- 医者の自脈効き目なし(いしゃのじみゃくききめなし)
- 医者よ自らを癒せ(いしゃよみずからをいやせ)
- 自惚れと瘡気のない者はない(うぬぼれとかさけのないものはない)
- 勝った自慢は負けての後悔(かったじまんはまけてのこうかい)
- 神は自ら助くる者を助く(かみはみずからたすくるものをたすく)
- 口自慢の仕事下手(くちじまんのしごとべた)
- 薫は香を以て自ら焼く(くんはこうをもってみずからやく)
- 怪我と弁当は自分持ち(けがとべんとうはじぶんもち)
- 剛戻自ら用う(ごうれいみずからもちう)
「蹊」を含むことわざ
- 成蹊(せいけい)
- 桃李もの言わざれども下自ずから蹊を成す(とうりものいわざれどもしたおのずからけいをなす)



