陽の照っているうちに干し草を作れとは
陽の照っているうちに干し草を作れ
ひのてっているうちにほしくさをつくれ
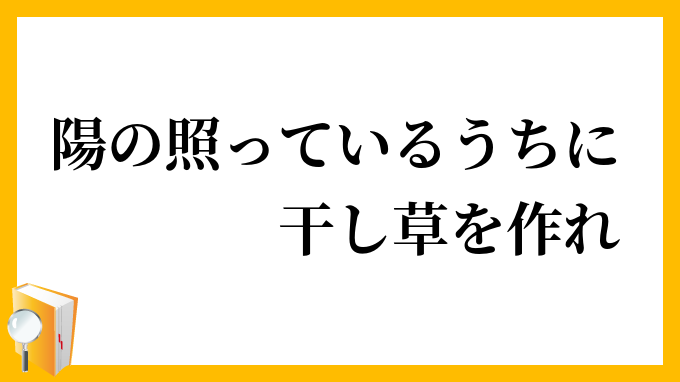
| 言葉 | 陽の照っているうちに干し草を作れ |
|---|---|
| 読み方 | ひのてっているうちにほしくさをつくれ |
| 意味 | 好機は逃さずに役に立てよということ。
「太陽の照っているうちに干し草を作れ」ともいう。 |
| 異形 | 太陽の照っているうちに干し草を作れ(たいようのてっているうちにほしくさをつくれ) |
| 類句 | 好機逸すべからず(こうきいっすべからず) |
| 使用漢字 | 陽 / 照 / 干 / 草 / 作 / 太 |
「陽」を含むことわざ
- 陰徳あれば必ず陽報あり(いんとくあればかならずようほうあり)
- 陰に陽に(いんにように)
- 陰陽師、身の上知らず(おんようじ、みのうえしらず)
- 陽炎稲妻月の影(かげろういなずまつきのかげ)
- 陽炎稲妻水の月(かげろういなずまみずのつき)
- 陽気発する処、金石も亦透る(ようきはっするところ、きんせきもまたとおる)
- 洛陽の紙価を高める(らくようのしかをたかめる)
「照」を含むことわざ
- 片山曇れば片山日照る(かたやまくもればかたやまひてる)
- 肝胆相照らす(かんたんあいてらす)
- ここばかりに日は照らぬ(ここばかりにひはてらぬ)
- 破鏡再び照らさず(はきょうふたたびてらさず)
- 明鏡も裏を照らさず(めいきょうもうらをてらさず)
- 落花枝に帰らず、破鏡再び照らさず(らっかえだにかえらず、はきょうふたたびてらさず)
- 落花枝に返らず、破鏡再び照らさず(らっかえだにかえらず、はきょうふたたびてらさず)
- 瑠璃も玻璃も照らせば光る(るりもはりもてらせばひかる)
「干」を含むことわざ
- 顎が干上がる(あごがひあがる)
- 干戈を交える(かんかをまじえる)
- 干天の慈雨(かんてんのじう)
- 口が干上がる(くちがひあがる)
- 甲羅を干す(こうらをほす)
- 雪駄の土用干し(せったのどようぼし)
- 干潟の鰯(ひがたのいわし)
「草」を含むことわざ
- 商いは草の種(あきないはくさのたね)
- お医者様でも草津の湯でも惚れた病は治りゃせぬ(おいしゃさまでもくさつのゆでもほれたやまいはなおりゃせぬ)
- おじが甥の草を刈る(おじがおいのくさをかる)
- 駕籠に乗る人担ぐ人、そのまた草鞋を作る人(かごにのるひとかつぐひと、そのまたわらじをつくるひと)
- 火事場に煙草の火なく大水に飲み水なし(かじばにたばこのひなくおおみずにのみみずなし)
- 金の草鞋で捜す(かねのわらじでさがす)
- 金の草鞋で尋ねる(かねのわらじでたずねる)
- 草木も靡く(くさきもなびく)
- 草木も眠る(くさきもねむる)
- 草木も眠る丑三つ時(くさきもねむるうしみつどき)
「作」を含むことわざ
- 秋荒れ半作(あきあれはんさく)
- 秋日和半作(あきびよりはんさく)
- 悪妻は百年の不作(あくさいはひゃくねんのふさく)
- 悪妻は六十年の不作(あくさいはろくじゅうねんのふさく)
- 家を道端に作れば三年成らず(いえをみちばたにつくればさんねんならず)
- 一生の不作(いっしょうのふさく)
- 色を作す(いろをなす)
- 顔を作る(かおをつくる)
- 垣を作る(かきをつくる)
- 駕籠に乗る人担ぐ人、そのまた草鞋を作る人(かごにのるひとかつぐひと、そのまたわらじをつくるひと)



