悪妻は六十年の不作とは
悪妻は六十年の不作
あくさいはろくじゅうねんのふさく
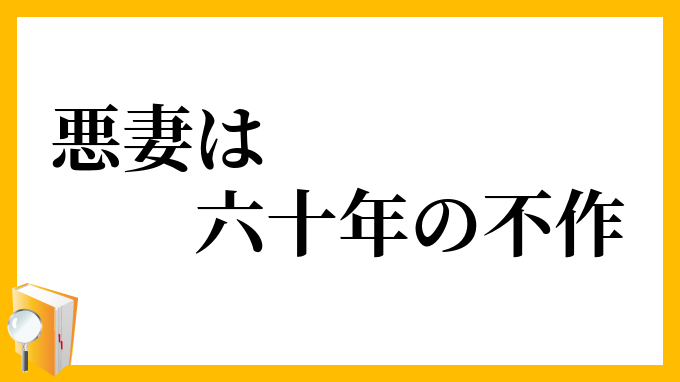
| 言葉 | 悪妻は六十年の不作 |
|---|---|
| 読み方 | あくさいはろくじゅうねんのふさく |
| 意味 | 悪い妻は夫を一生不幸にするということ。
「悪妻は百年の不作」ともいう。 |
| 異形 | 悪妻は百年の不作(あくさいはひゃくねんのふさく) |
| 場面用途 | 夫婦 / 親族 |
| 使用語彙 | 悪妻 |
| 使用漢字 | 悪 / 妻 / 六 / 十 / 年 / 不 / 作 / 百 |
「悪」を含むことわざ
- 合性が悪い(あいしょうがわるい)
- 相性が悪い(あいしょうがわるい)
- 愛は憎悪の始め(あいはぞうおのはじめ)
- 悪縁契り深し(あくえんちぎりふかし)
- 悪事、千里を走る(あくじ、せんりをはしる)
- 悪事、身にかえる(あくじ、みにかえる)
- 悪事、千里を行く(あくじせんりをいく)
- 悪獣もなおその類を思う(あくじゅうもなおそのるいをおもう)
「妻」を含むことわざ
- 家貧しくして良妻を思う(いえまずしくしてりょうさいをおもう)
- 男は妻から(おとこはめから)
- 陽炎稲妻月の影(かげろういなずまつきのかげ)
- 陽炎稲妻水の月(かげろういなずまみずのつき)
- 荊妻(けいさい)
- 喧嘩に負けて妻の面を張る(けんかにまけてつまのつらをはる)
- 妻子を置く所が故郷(さいしをおくところがこきょう)
- 相撲に負けて妻の面張る(すもうにまけてつまのつらはる)
「六」を含むことわざ
- 一日一字を学べば三百六十字(いちにちいちじをまなべばさんびゃくろくじゅうじ)
- 一の裏は六(いちのうらはろく)
- 後生願いの六性悪(ごしょうねがいのろくしょうあく)
- 五臓六腑に沁みわたる(ごぞうろっぷにしみわたる)
- 三十六計逃げるに如かず(さんじゅうろっけいにげるにしかず)
- 総領の甚六(そうりょうのじんろく)
- 十日の菊、六日の菖蒲(とおかのきく、むいかのあやめ)
- 女房の悪いは六十年の不作(にょうぼうのわるいはろくじゅうねんのふさく)
- 朋友は六親に叶う(ほうゆうはりくしんにかなう)
「十」を含むことわざ
- 明日の百より今日の五十(あすのひゃくよりきょうのごじゅう)
- 一から十まで(いちからじゅうまで)
- 一日暖めて十日冷やす(いちにちあたためてとおかひやす)
- 一日一字を学べば三百六十字(いちにちいちじをまなべばさんびゃくろくじゅうじ)
- 一を聞いて十を知る(いちをきいてじゅうをしる)
- いやいや三杯十三杯(いやいやさんばいじゅうさんばい)
- うかうか三十きょろきょろ四十(うかうかさんじゅうきょろきょろしじゅう)
- 男は二十五の暁まで育つ(おとこはにじゅうごのあかつきまでそだつ)
- 鬼も十八(おにもじゅうはち)
「年」を含むことわざ
- 商い三年(あきないさんねん)
- 秋の入り日と年寄りはだんだん落ち目が早くなる(あきのいりひととしよりはだんだんおちめがはやくなる)
- 顎振り三年(あごふりさんねん)
- いい年をして(いいとしをして)
- 家を道端に作れば三年成らず(いえをみちばたにつくればさんねんならず)
- 烏賊の甲より年の功(いかのこうよりとしのこう)
- 烏賊の甲より年の劫(いかのこうよりとしのこう)
- 石の上にも三年(いしのうえにもさんねん)
「不」を含むことわざ
- 相手にとって不足はない(あいてにとってふそくはない)
- 合うも不思議合わぬも不思議(あうもふしぎあわぬもふしぎ)
- 医者の不養生(いしゃのふようじょう)
- 一抹の不安(いちまつのふあん)
- 一生の不作(いっしょうのふさく)
- 後ろ弁天、前不動(うしろべんてん、まえふどう)
- 置き酌失礼、持たぬが不調法(おきじゃくしつれい、もたぬがぶちょうほう)
- 金の貸し借りは不和の基(かねのかしかりはふわのもと)
「作」を含むことわざ
- 秋荒れ半作(あきあれはんさく)
- 秋日和半作(あきびよりはんさく)
- 家を道端に作れば三年成らず(いえをみちばたにつくればさんねんならず)
- 一生の不作(いっしょうのふさく)
- 色を作す(いろをなす)
- 顔を作る(かおをつくる)
- 垣を作る(かきをつくる)
- 駕籠に乗る人担ぐ人、そのまた草鞋を作る人(かごにのるひとかつぐひと、そのまたわらじをつくるひと)



