三十六計逃げるに如かずとは
三十六計逃げるに如かず
さんじゅうろっけいにげるにしかず
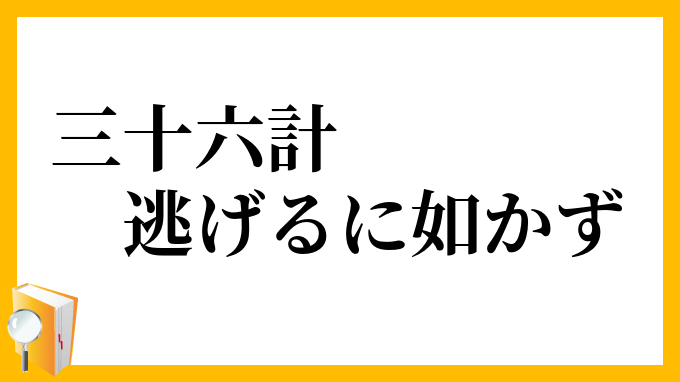
| 言葉 | 三十六計逃げるに如かず |
|---|---|
| 読み方 | さんじゅうろっけいにげるにしかず |
| 意味 | 様々な計略があるが、困ったときは逃げるのが最良の策だということ。
「三十六計」は、古代中国の兵法で使われた三十六種類のはかりごと。 三十六種類の計略のうち、逃げるという計略に及ぶものはないとの意から。 |
| 使用語彙 | 逃げる / 逃げ |
| 使用漢字 | 三 / 十 / 六 / 計 / 逃 / 如 |
「三」を含むことわざ
- 商い三年(あきないさんねん)
- 秋の雨が降れば猫の顔が三尺になる(あきのあめがふればねこのかおがさんじゃくになる)
- 顎振り三年(あごふりさんねん)
- 朝起き三両始末五両(あさおきさんりょうしまつごりょう)
- 朝起きは三文の徳(あさおきはさんもんのとく)
- 阿呆の三杯汁(あほうのさんばいじる)
- 雨垂れは三途の川(あまだれはさんずのかわ)
- 家を道端に作れば三年成らず(いえをみちばたにつくればさんねんならず)
- 石の上にも三年(いしのうえにもさんねん)
- 伊勢へ七度、熊野へ三度(いせへななたび、くまのへみたび)
「十」を含むことわざ
- 悪妻は六十年の不作(あくさいはろくじゅうねんのふさく)
- 明日の百より今日の五十(あすのひゃくよりきょうのごじゅう)
- 一から十まで(いちからじゅうまで)
- 一日暖めて十日冷やす(いちにちあたためてとおかひやす)
- 一日一字を学べば三百六十字(いちにちいちじをまなべばさんびゃくろくじゅうじ)
- 一を聞いて十を知る(いちをきいてじゅうをしる)
- いやいや三杯十三杯(いやいやさんばいじゅうさんばい)
- うかうか三十きょろきょろ四十(うかうかさんじゅうきょろきょろしじゅう)
- 男は二十五の暁まで育つ(おとこはにじゅうごのあかつきまでそだつ)
- 鬼も十八(おにもじゅうはち)
「六」を含むことわざ
- 悪妻は六十年の不作(あくさいはろくじゅうねんのふさく)
- 一日一字を学べば三百六十字(いちにちいちじをまなべばさんびゃくろくじゅうじ)
- 一の裏は六(いちのうらはろく)
- 後生願いの六性悪(ごしょうねがいのろくしょうあく)
- 五臓六腑に沁みわたる(ごぞうろっぷにしみわたる)
- 総領の甚六(そうりょうのじんろく)
- 十日の菊、六日の菖蒲(とおかのきく、むいかのあやめ)
- 女房の悪いは六十年の不作(にょうぼうのわるいはろくじゅうねんのふさく)
- 朋友は六親に叶う(ほうゆうはりくしんにかなう)
「計」を含むことわざ
- 一日の計は晨にあり(いちじつのけいはあしたにあり)
- 一日の計は朝にあり(いちじつのけいはあしたにあり)
- 一日の計は朝にあり、一年の計は元旦にあり(いちじつのけいはあしたにあり、いちねんのけいはがんたんにあり)
- 一日の計は朝にあり(いちにちのけいはあさにあり)
- 一日の計は朝にあり一年の計は元旦にあり(いちにちのけいはあさにありいちねんのけいはがんたんにあり)
- 一日の計は晨にあり一年の計は元旦にあり(いちにちのけいはあしたにありいちねんのけいはがんたんにあり)
- 一年の計は元旦にあり(いちねんのけいはがんたんにあり)
- 一計を案じる(いっけいをあんじる)
- 計算高い(けいさんだかい)
「逃」を含むことわざ
- 虎口を逃れて竜穴に入る(ここうをのがれてりゅうけつにいる)
- 地震の時は竹薮に逃げろ(じしんのときはたけやぶににげろ)
- 逃がした魚は大きい(にがしたさかなはおおきい)
- 二月は逃げて去る(にがつはにげてさる)
- 二月は逃げて走る(にがつはにげてはしる)
- 逃ぐるが一の手(にぐるがいちのて)
- 逃げ腰になる(にげごしになる)
- 逃げた魚は大きい(にげたさかなはおおきい)
- 逃げも隠れもしない(にげもかくれもしない)



