石の上にも三年とは
石の上にも三年
いしのうえにもさんねん
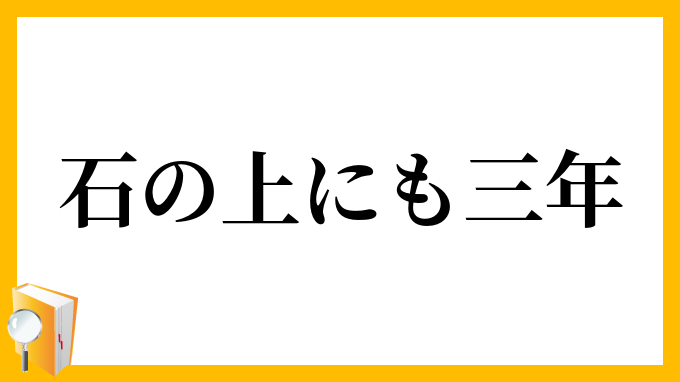
| 言葉 | 石の上にも三年 |
|---|---|
| 読み方 | いしのうえにもさんねん |
| 意味 | 辛抱すればいつか必ず成功することのたとえ。
冷たい石の上でも、三年座り続ければ暖まるとの意から。 |
| 類句 | 辛抱する木に金がなる(しんぼうするきにかねがなる) |
| 茨の中にも三年 | |
| 火の中にも三年 | |
| 使用語彙 | 上 |
| 使用漢字 | 石 / 上 / 三 / 年 |
「石」を含むことわざ
- 朝寝八石の損(あさねはちこくのそん)
- 雨垂れ石を穿つ(あまだれいしをうがつ)
- 石臼を箸に刺す(いしうすをはしにさす)
- 石が流れて木の葉が沈む(いしがながれてこのはがしずむ)
- 石亀の地団駄(いしがめのじだんだ)
- 石亀も地団駄(いしがめもじだんだ)
- 石地蔵に蜂(いしじぞうにはち)
- 石に嚙り付いても(いしにかじりついても)
- 石に齧りついても(いしにかじりついても)
- 石に裃(いしにかみしも)
「上」を含むことわざ
- 商い上手の仕入れ下手(あきないじょうずのしいれべた)
- 上げ潮に乗る(あげしおにのる)
- 上げ膳据え膳(あげぜんすえぜん)
- 上げ膳に据え膳(あげぜんにすえぜん)
- 上げたり下げたり(あげたりさげたり)
- 顎が干上がる(あごがひあがる)
- 梓に上す(あずさにのぼす)
- 頭押さえりゃ尻上がる(あたまおさえりゃしりあがる)
- 頭が上がらない(あたまがあがらない)
- 頭に血が上る(あたまにちがのぼる)
「三」を含むことわざ
- 商い三年(あきないさんねん)
- 秋の雨が降れば猫の顔が三尺になる(あきのあめがふればねこのかおがさんじゃくになる)
- 顎振り三年(あごふりさんねん)
- 朝起き三両始末五両(あさおきさんりょうしまつごりょう)
- 朝起きは三文の徳(あさおきはさんもんのとく)
- 阿呆の三杯汁(あほうのさんばいじる)
- 雨垂れは三途の川(あまだれはさんずのかわ)
- 家を道端に作れば三年成らず(いえをみちばたにつくればさんねんならず)
- 伊勢へ七度、熊野へ三度(いせへななたび、くまのへみたび)



