雨垂れは三途の川とは
雨垂れは三途の川
あまだれはさんずのかわ
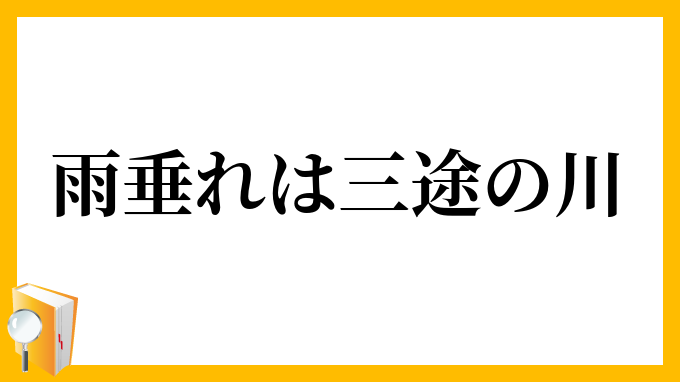
| 言葉 | 雨垂れは三途の川 |
|---|---|
| 読み方 | あまだれはさんずのかわ |
| 意味 | 家から一歩出れば、どんな災難や危険が待ちかまえているかわからないということ。
軒下から落ちる雨だれを、あの世とこの世の堺である三途の川に見立てて、家から一歩出たら十分に注意せよとの戒めのことば。 |
| 場面用途 | 危険 |
| 使用語彙 | 雨垂れ / 雨 / 川 |
| 使用漢字 | 雨 / 垂 / 三 / 途 / 川 |
「雨」を含むことわざ
- 秋の雨が降れば猫の顔が三尺になる(あきのあめがふればねこのかおがさんじゃくになる)
- 朝雨馬に鞍置け(あさあめうまにくらおけ)
- 朝雨と女の腕捲り(あさあめとおんなのうでまくり)
- 朝雨に傘いらず(あさあめにかさいらず)
- 朝雨に傘要らず(あさあめにかさいらず)
- 朝虹は雨夕虹は晴れ(あさにじはあめゆうにじははれ)
- 雨垂れ石を穿つ(あまだれいしをうがつ)
- 雨夜の月(あまよのつき)
- 雨、車軸の如し(あめ、しゃじくのごとし)
「垂」を含むことわざ
- 汗水垂らす(あせみずたらす)
- 雨垂れ石を穿つ(あまだれいしをうがつ)
- 功名を竹帛に垂る(こうみょうをちくはくにたる)
- 垂涎(すいぜん)
- 垂涎(すいぜん)
- 垂涎の的(すいぜんのまと)
- 名を竹帛に垂る(なをちくはくにたる)
- 能書きを垂れる(のうがきをたれる)
- 範を垂れる(はんをたれる)
「三」を含むことわざ
- 商い三年(あきないさんねん)
- 秋の雨が降れば猫の顔が三尺になる(あきのあめがふればねこのかおがさんじゃくになる)
- 顎振り三年(あごふりさんねん)
- 朝起き三両始末五両(あさおきさんりょうしまつごりょう)
- 朝起きは三文の徳(あさおきはさんもんのとく)
- 阿呆の三杯汁(あほうのさんばいじる)
- 家を道端に作れば三年成らず(いえをみちばたにつくればさんねんならず)
- 石の上にも三年(いしのうえにもさんねん)
- 伊勢へ七度、熊野へ三度(いせへななたび、くまのへみたび)
「途」を含むことわざ
- 一途を辿る(いっとをたどる)
- 門松は冥途の旅の一里塚(かどまつはめいどのたびのいちりづか)
- 官途に就く(かんとにつく)
- 途轍もない(とてつもない)
- 途方に暮れる(とほうにくれる)
- 途方もない(とほうもない)
- 日暮れて途遠し(ひくれてみちとおし)



