紙子着て川へはまるとは
紙子着て川へはまる
かみこきてかわへはまる
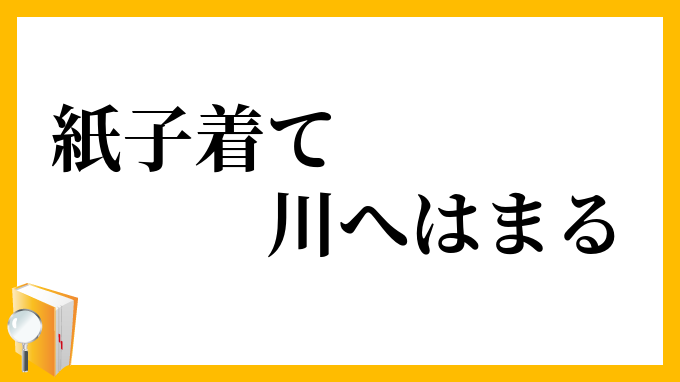
| 言葉 | 紙子着て川へはまる |
|---|---|
| 読み方 | かみこきてかわへはまる |
| 意味 | 軽率な行いによって、自ら破滅を招くことのたとえ。
「紙子」は、渋柿を塗った紙で仕立てた衣服。 紙の服を着て川の中へ入るという無謀なことをいう。 |
| 異形 | 紙子着て川へ入る(かみこきてかわへはいる) |
| 類句 | 墓穴を掘る(ぼけつをほる) |
| 使用語彙 | 紙 / 川 / 入る |
| 使用漢字 | 紙 / 子 / 着 / 川 / 入 |
「紙」を含むことわざ
- 青表紙を叩いた者にはかなわぬ(あおびょうしをたたいたものにはかなわぬ)
- 油紙に火が付いたよう(あぶらがみにひがついたよう)
- 油紙に火の付いたよう(あぶらがみにひのついたよう)
- 油紙へ火の付いたよう(あぶらがみへひのついたよう)
- 一枚の紙にも裏表(いちまいのかみにもうらおもて)
- 薄紙を剝ぐよう(うすがみをはぐよう)
- 折り紙付き(おりがみつき)
- 折り紙を付ける(おりがみをつける)
「子」を含むことわざ
- 赤子のうちは七国七里の者に似る(あかごのうちはななくにななさとのものににる)
- 赤子の腕を捩じる(あかごのうでをねじる)
- 赤子の手をねじる(あかごのてをねじる)
- 赤子の手を捩じるよう(あかごのてをねじるよう)
- 赤子の手を捻る(あかごのてをひねる)
- 赤子の手を捻るよう(あかごのてをひねるよう)
- 赤子は泣き泣き育つ(あかごはなきなきそだつ)
- 赤子を裸にしたよう(あかごをはだかにしたよう)
- 秋茄子は嫁に食わすな(あきなすはよめにくわすな)
- 秋の日と娘の子はくれぬようでくれる(あきのひとむすめのこはくれぬようでくれる)
「着」を含むことわざ
- 足が地に着かない(あしがちにつかない)
- 石に布団は着せられず(いしにふとんはきせられず)
- 烏帽子を着せる(えぼしをきせる)
- 狼が衣を着たよう(おおかみがころもをきたよう)
- 奥歯に衣着せる(おくばにきぬきせる)
- 親は木綿着る、子は錦着る(おやはもめんきる、こはにしききる)
- 恩に着せる(おんにきせる)
- 恩に着る(おんにきる)
- 替え着なしの晴れ着なし(かえぎなしのはれぎなし)
- 笠に着る(かさにきる)
「川」を含むことわざ
- 浅い川も深く渡れ(あさいかわもふかくわたれ)
- 飛鳥川の淵瀬(あすかがわのふちせ)
- 雨垂れは三途の川(あまだれはさんずのかわ)
- 海魚腹から川魚背から(うみうおはらからかわうおせから)
- 落ちれば同じ谷川の水(おちればおなじたにがわのみず)
- 落つれば同じ谷川の水(おつればおなじたにがわのみず)
- 泳ぎ上手は川で死ぬ(およぎじょうずはかわでしぬ)
- 河童の川流れ(かっぱのかわながれ)
- 金槌の川流れ(かなづちのかわながれ)



