落ちれば同じ谷川の水とは
落ちれば同じ谷川の水
おちればおなじたにがわのみず
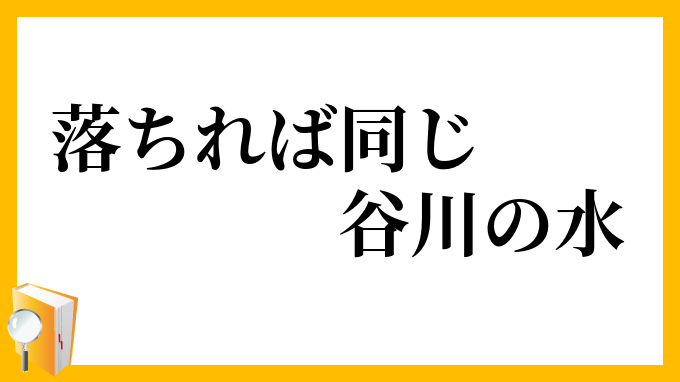
| 言葉 | 落ちれば同じ谷川の水 |
|---|---|
| 読み方 | おちればおなじたにがわのみず |
| 意味 | 出発点は違っていても、行き着く先は同じだということ。また、人間も身分や貧富の差があっても、死ねばみな同じであるということ。
雨・霰(あられ)・雪・氷など形はさまざまでも、地上に落ちてしまえば同じ谷川を流れる水になるとの意から。 「雨霰雪や氷と隔(へだ)つらん落つれば同じ谷川の水」との和歌より。 |
| 異形 | 落つれば同じ谷川の水(おつればおなじたにがわのみず) |
| 使用語彙 | 同じ |
| 使用漢字 | 落 / 同 / 谷 / 川 / 水 |
「落」を含むことわざ
- 秋の入り日と年寄りはだんだん落ち目が早くなる(あきのいりひととしよりはだんだんおちめがはやくなる)
- 秋の日は釣瓶落とし(あきのひはつるべおとし)
- 顎が落ちる(あごがおちる)
- 油を以って油煙を落とす(あぶらをもってゆえんをおとす)
- 一段落つく(いちだんらくつく)
- 一葉落ちて天下の秋を知る(いちようおちててんかのあきをしる)
- 胃の腑に落ちる(いのふにおちる)
- 鰯で精進落ち(いわしでしょうじんおち)
- 瘧が落ちる(おこりがおちる)
- 落ち武者は薄の穂にも怖ず(おちむしゃはすすきのほにもおず)
「同」を含むことわざ
- 畦から行くも田から行くも同じ(あぜからいくもたからいくもおなじ)
- いとこ同士は鴨の味(いとこどうしはかものあじ)
- 大家と言えば親も同然、店子と言えば子も同然(おおやといえばおやもどうぜん、たなこといえばこもどうぜん)
- 同い年夫婦は火吹く力もない(おないどしみょうとはひふくちからもない)
- 同じ穴の貉(おなじあなのむじな)
- 同じ釜の飯を食う(おなじかまのめしをくう)
- 同じ羽の鳥は集まるものだ(おなじはねのとりはあつまるものだ)
- 君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず(くんしはわしてどうぜず、しょうじんはどうじてわせず)
- 形影相同じ(けいえいあいおなじ)
「谷」を含むことわざ
- 恐れ入谷の鬼子母神(おそれいりやのきしもじん)
- 落ちれば同じ谷川の水(おちればおなじたにがわのみず)
- 空谷の跫音(くうこくのきょうおん)
- 進退維谷まる(しんたいこれきわまる)
「川」を含むことわざ
- 胡坐で川(あぐらでかわ)
- 浅い川も深く渡れ(あさいかわもふかくわたれ)
- 飛鳥川の淵瀬(あすかがわのふちせ)
- 雨垂れは三途の川(あまだれはさんずのかわ)
- 海魚腹から川魚背から(うみうおはらからかわうおせから)
- 泳ぎ上手は川で死ぬ(およぎじょうずはかわでしぬ)
- 河童の川流れ(かっぱのかわながれ)
- 金槌の川流れ(かなづちのかわながれ)
- 紙子着て川へはまる(かみこきてかわへはまる)



