同い年夫婦は火吹く力もないとは
同い年夫婦は火吹く力もない
おないどしみょうとはひふくちからもない
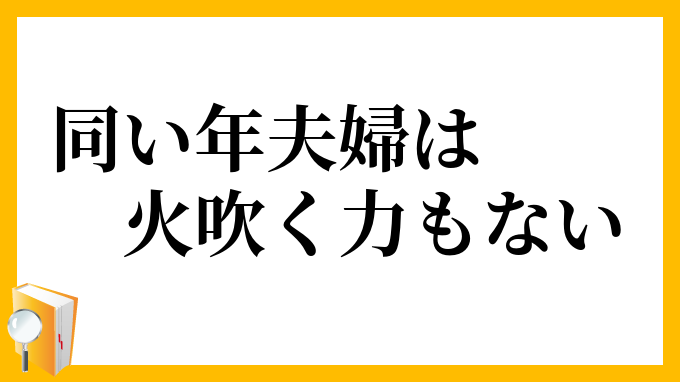
| 言葉 | 同い年夫婦は火吹く力もない |
|---|---|
| 読み方 | おないどしみょうとはひふくちからもない |
| 意味 | 同い年の夫婦は仲が良く、いつも笑ってばかりいるので、火吹き竹を吹いて火をおこすためのふくれっ面もできないということ。 |
| 場面用途 | 夫婦 / 親族 |
| 使用語彙 | 同い年 |
| 使用漢字 | 同 / 年 / 夫 / 婦 / 火 / 吹 / 力 |
「同」を含むことわざ
- 畦から行くも田から行くも同じ(あぜからいくもたからいくもおなじ)
- いとこ同士は鴨の味(いとこどうしはかものあじ)
- 大家と言えば親も同然、店子と言えば子も同然(おおやといえばおやもどうぜん、たなこといえばこもどうぜん)
- 落ちれば同じ谷川の水(おちればおなじたにがわのみず)
- 落つれば同じ谷川の水(おつればおなじたにがわのみず)
- 同じ穴の狸(おなじあなのたぬき)
- 同じ穴の狐(おなじあなのむじな)
- 同じ穴の貉(おなじあなのむじな)
- 同じ釜の飯を食う(おなじかまのめしをくう)
「年」を含むことわざ
- 商い三年(あきないさんねん)
- 秋の入り日と年寄りはだんだん落ち目が早くなる(あきのいりひととしよりはだんだんおちめがはやくなる)
- 悪妻は百年の不作(あくさいはひゃくねんのふさく)
- 悪妻は六十年の不作(あくさいはろくじゅうねんのふさく)
- 顎振り三年(あごふりさんねん)
- いい年をして(いいとしをして)
- 家を道端に作れば三年成らず(いえをみちばたにつくればさんねんならず)
- 烏賊の甲より年の功(いかのこうよりとしのこう)
- 烏賊の甲より年の劫(いかのこうよりとしのこう)
- 石の上にも三年(いしのうえにもさんねん)
「夫」を含むことわざ
- 秋風と夫婦喧嘩は日が入りゃ止む(あきかぜとふうふげんかはひがいりゃやむ)
- 一夫関に当たれば万夫も開くなし(いっぷかんにあたればばんぷもひらくなし)
- 親子は一世、夫婦は二世、主従は三世(おやこはいっせ、ふうふはにせ、しゅじゅうはさんせ)
- 漁夫の利(ぎょふのり)
- 三軍も帥を奪うべきなり、匹夫も志を奪うべからず(さんぐんもすいをうばうべきなり、ひっぷもこころざしをうばうべからず)
- 大丈夫、金の脇差(だいじょうぶ、かねのわきざし)
- 貞女は二夫に見えず(ていじょはじふにまみえず)
- 貞女は二夫を更めず(ていじょはじふをあらためず)
- 貞女は二夫を並べず(ていじょはじふをならべず)
「婦」を含むことわざ
- 秋風と夫婦喧嘩は日が入りゃ止む(あきかぜとふうふげんかはひがいりゃやむ)
- 親子は一世、夫婦は二世、主従は三世(おやこはいっせ、ふうふはにせ、しゅじゅうはさんせ)
- 西風と夫婦喧嘩は夕限り(にしかぜとふうふげんかはゆうかぎり)
- 似た者夫婦(にたものふうふ)
- 蚤の夫婦(のみのふうふ)
- 夫婦喧嘩は犬も食わない(ふうふげんかはいぬもくわない)
- 夫婦喧嘩は寝て直る(ふうふげんかはねてなおる)
- 夫婦喧嘩は貧乏の種蒔き(ふうふげんかはびんぼうのたねまき)
- 夫婦喧嘩もないから起こる(ふうふげんかもないからおこる)
「火」を含むことわざ
- 秋葉山から火事(あきばさんからかじ)
- 足下に火が付く(あしもとにひがつく)
- 足元に火が付く(あしもとにひがつく)
- 熱火子にかく(あつびこにかく)
- 熱火子に払う(あつびこにはらう)
- 油紙に火が付いたよう(あぶらがみにひがついたよう)
- 油紙に火の付いたよう(あぶらがみにひのついたよう)
- 油紙へ火の付いたよう(あぶらがみへひのついたよう)
- 暗夜に灯火を失う(あんやにともしびをうしなう)
- 家に女房なきは火のない炉のごとし(いえににょうぼうなきはひのないろのごとし)
「吹」を含むことわざ
- 明日は明日の風が吹く(あしたはあしたのかぜがふく)
- 羹に懲りて膾を吹く(あつものにこりてなますをふく)
- 阿波に吹く風は讃岐にも吹く(あわにふくかぜはさぬきにもふく)
- 泡を吹かせる(あわをふかせる)
- 息を吹き返す(いきをふきかえす)
- 江戸っ子は五月の鯉の吹き流し(えどっこはさつきのこいのふきながし)
- 大風が吹けば桶屋が儲かる(おおかぜがふけばおけやがもうかる)
- 大風が吹けば桶屋が喜ぶ(おおかぜがふけばおけやがよろこぶ)
- 臆病風に吹かれる(おくびょうかぜにふかれる)



