秋風と夫婦喧嘩は日が入りゃ止むとは
秋風と夫婦喧嘩は日が入りゃ止む
あきかぜとふうふげんかはひがいりゃやむ
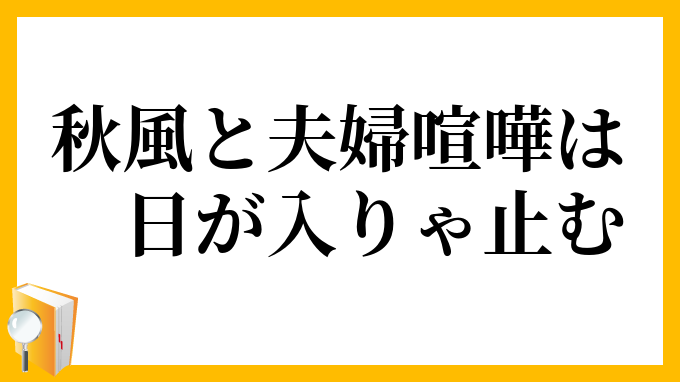
| 言葉 | 秋風と夫婦喧嘩は日が入りゃ止む |
|---|---|
| 読み方 | あきかぜとふうふげんかはひがいりゃやむ |
| 意味 | 秋風が日暮れになると静まるように、夫婦喧嘩も夜になるとおさまるということ。 |
| 場面用途 | 夫婦 / 親族 / 喧嘩 / 夫婦喧嘩 |
| 使用語彙 | 秋風 |
| 使用漢字 | 秋 / 風 / 夫 / 婦 / 喧 / 嘩 / 日 / 入 / 止 |
「秋」を含むことわざ
- 秋荒れ半作(あきあれはんさく)
- 秋風が立つ(あきかぜがたつ)
- 秋高く馬肥ゆ(あきたかくうまこゆ)
- 秋茄子は嫁に食わすな(あきなすはよめにくわすな)
- 秋の雨が降れば猫の顔が三尺になる(あきのあめがふればねこのかおがさんじゃくになる)
- 秋の入り日と年寄りはだんだん落ち目が早くなる(あきのいりひととしよりはだんだんおちめがはやくなる)
- 秋の扇(あきのおうぎ)
- 秋の鹿は笛に寄る(あきのしかはふえによる)
- 秋の日と娘の子はくれぬようでくれる(あきのひとむすめのこはくれぬようでくれる)
「風」を含むことわざ
- 秋風が立つ(あきかぜがたつ)
- 商人と屏風は直ぐには立たぬ(あきんどとびょうぶはすぐにはたたぬ)
- 商人と屏風は曲がらねば立たぬ(あきんどとびょうぶはまがらねばたたぬ)
- 明日は明日の風が吹く(あしたはあしたのかぜがふく)
- あったら口に風邪ひかす(あったらくちにかぜひかす)
- あったら口に風邪をひかす(あったらくちにかぜをひかす)
- 可惜口に風ひかす(あったらくちにかぜをひかす)
- 網の目に風たまらず(あみのめにかぜたまらず)
- 網の目に風たまる(あみのめにかぜたまる)
「夫」を含むことわざ
- 一夫関に当たれば万夫も開くなし(いっぷかんにあたればばんぷもひらくなし)
- 同い年夫婦は火吹く力もない(おないどしみょうとはひふくちからもない)
- 親子は一世、夫婦は二世、主従は三世(おやこはいっせ、ふうふはにせ、しゅじゅうはさんせ)
- 漁夫の利(ぎょふのり)
- 三軍も帥を奪うべきなり、匹夫も志を奪うべからず(さんぐんもすいをうばうべきなり、ひっぷもこころざしをうばうべからず)
- 大丈夫、金の脇差(だいじょうぶ、かねのわきざし)
- 貞女は二夫に見えず(ていじょはじふにまみえず)
- 貞女は二夫を更めず(ていじょはじふをあらためず)
- 貞女は二夫を並べず(ていじょはじふをならべず)
「婦」を含むことわざ
- 同い年夫婦は火吹く力もない(おないどしみょうとはひふくちからもない)
- 親子は一世、夫婦は二世、主従は三世(おやこはいっせ、ふうふはにせ、しゅじゅうはさんせ)
- 西風と夫婦喧嘩は夕限り(にしかぜとふうふげんかはゆうかぎり)
- 似た者夫婦(にたものふうふ)
- 蚤の夫婦(のみのふうふ)
- 夫婦喧嘩は犬も食わない(ふうふげんかはいぬもくわない)
- 夫婦喧嘩は寝て直る(ふうふげんかはねてなおる)
- 夫婦喧嘩は貧乏の種蒔き(ふうふげんかはびんぼうのたねまき)
- 夫婦喧嘩もないから起こる(ふうふげんかもないからおこる)
「喧」を含むことわざ
- 相手のない喧嘩はできぬ(あいてのないけんかはできぬ)
- 相手見てからの喧嘩声(あいてみてからのけんかごえ)
- 後の喧嘩、先でする(あとのけんか、さきでする)
- 売られた喧嘩は買わねばならぬ(うられたけんかはかわねばならぬ)
- 火事と喧嘩は江戸の花(かじとけんかはえどのはな)
- 火事と喧嘩は江戸の華(かじとけんかはえどのはな)
- 金持ち喧嘩せず(かねもちけんかせず)
- 喧嘩過ぎての空威張り(けんかすぎてのからいばり)
- 喧嘩過ぎての棒乳切り(けんかすぎてのぼうちぎり)
「嘩」を含むことわざ
- 相手のない喧嘩はできぬ(あいてのないけんかはできぬ)
- 相手見てからの喧嘩声(あいてみてからのけんかごえ)
- 後の喧嘩、先でする(あとのけんか、さきでする)
- 売られた喧嘩は買わねばならぬ(うられたけんかはかわねばならぬ)
- 火事と喧嘩は江戸の花(かじとけんかはえどのはな)
- 火事と喧嘩は江戸の華(かじとけんかはえどのはな)
- 金持ち喧嘩せず(かねもちけんかせず)
- 喧嘩過ぎての空威張り(けんかすぎてのからいばり)
- 喧嘩過ぎての棒乳切り(けんかすぎてのぼうちぎり)
「日」を含むことわざ
- 秋の入り日と年寄りはだんだん落ち目が早くなる(あきのいりひととしよりはだんだんおちめがはやくなる)
- 秋の日と娘の子はくれぬようでくれる(あきのひとむすめのこはくれぬようでくれる)
- 秋の日は釣瓶落とし(あきのひはつるべおとし)
- 秋日和半作(あきびよりはんさく)
- 明後日の方(あさってのほう)
- 朝日が西から出る(あさひがにしからでる)
- 明日は明日の風が吹く(あしたはあしたのかぜがふく)
- 明日ありと思う心の仇桜(あすありとおもうこころのあだざくら)
- 明日食う塩辛に今日から水を飲む(あすくうしおからにきょうからみずをのむ)
「入」を含むことわざ
- 間に入る(あいだにはいる)
- 合いの手を入れる(あいのてをいれる)
- 赤を入れる(あかをいれる)
- 商い上手の仕入れ下手(あきないじょうずのしいれべた)
- 秋の入り日と年寄りはだんだん落ち目が早くなる(あきのいりひととしよりはだんだんおちめがはやくなる)
- 足を入れる(あしをいれる)
- 足を踏み入れる(あしをふみいれる)
- 頭に入れる(あたまにいれる)
- 新しき葡萄酒は新しき革袋に入れよ(あたらしきぶどうしゅはあたらしきかわぶくろにいれよ)



